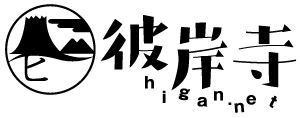先日、「毎日広告デザイン賞」に「イオンのお葬式」のために作られた公募作品が選ばれていたことが、Twitterを中心に物議を醸していました。
このデザインに関しては、いろいろ皆さん思われることもあるかと思います。引用しましたカレー坊主こと吉田武士さんのツイートは4万のいいねや1万4千を超えるリツイートがされ、注目されました。
私は、個人的には強烈な皮肉であるな、と感じました。それは、葬儀に関わる僧侶であったり、葬祭業に対しての皮肉であることは言うまでもありません。と、同時に、生鮮食品のようにパッケージングされたお位牌からは、イオンが葬儀を行うということに対しての皮肉ともなっているようにも思われました。それが果たして広告として機能するデザインなのか、ということは私は評価できませんが、しかし、現在葬儀であったり、仏事であったりの受け止め方や理解というものが、このようなものであるということを、よく表しているものなのかもしれません。
また、同じようなタイミングで、Amazonで「DIY葬セット」なるものもTwitterで話題となっていました。
これは棺や骨壷、そしてハンドブックなどがセットになったもので、確かにこのセットを使えば、葬儀社を介さずとも葬儀ができそうな気がしてきます。しかし実際には、遺体を運んだり、適切な処理を施したり、棺を運ぶことなどは、決して一人ではできないことですから、これがあればOKというものでは決してないようにも感じられました。
今回の件だけではありませんが、葬儀や仏事が疎かにされるような出来事が見られた際、必ず問われてくるのが僧侶の責任です。僧侶の怠慢やこれまでの姿勢が問題だということは、確かにその一因として間違いないことだと、私も思います。
そこで今回は、そもそも私たちはなぜ仏事、「お参り」をするのか、ということについて改めて考えたことを書いてみたいと思います。
●美しい虹と中秋の名月
先日、ある会合で、一人の先輩のお坊さんがこんなお話をしてくださいました。
ある朝早く、散歩していると、空にこれまで見たことないくらい美しい虹がかかっていました。あまりの美しさに感動したので、思わずその感動を誰かと共有したくなったのですが、早朝なので回りには誰もいない。それでも暫く歩くと、掃除をしている人がいて、いてもたってもいられず、「おはようございます」と声をかけました。するとその掃除をしている人は突然知らない人から声をかけられたことに驚いていましたが、その虹のことを話すと「教えてくれてありがとうございます!」ととても喜んでくれました。その人は、下を向いて掃除をしていたので、虹が出ていることに全く気づいていなかったようです。私もその人が虹に感動してくれて、とても嬉しい気持ちになりました。
と、このようなエピソードでした。
下を向いてばかりいると、空にどんなに美しい虹がかかっていても気づかない。誰かの歌にもこんなような歌があったような気もしますが、どんなに美しい虹が出ていても、それを見ようとしなければ、気づかないまま、ということは往々にしてあることでしょう。
同じようなものに、月があげられます。先日の中秋の名月もそうでしたが、外に出て月を見ようとしなければ、どんなに美しい月も、その人の目に映ることはありません。
このことをよく表しているのが、法然聖人という方が詠まれた有名な詩です。
「月影のいたらぬ里はなけれども眺むる人の心にぞすむ」
この詩は、月の光の届かない人里などないけれど、その光は眺めてみて初めて、その人の心に至り届く、ということを言い表しています。そして月は阿弥陀仏という仏さまのはたらき、南無阿弥陀仏を喩えたものだと言われています。
この法然聖人の詩の通り、私たちは、普段生活していると、ついつい視野狭窄になってしまうというか、視点が固定化されてしまうというか、狭い価値観でしか物を見れなくなってしまうということがあるように思います。仕事のことであったり、子育てのことであったり、人間関係のことであったり、勉強のことであったり。私たちの日常は、いろんな悩みごとや、やらなければならないことが目の前に満ち溢れていて、そこから目を離してみるということはなかなかできません。
しかしそれはちょうど、ずっと下を向いて掃除をしたままであったり、自分という家の中に閉じこもっていて、空にどんなに美しい虹や名月がかかっていても、気づかないままでいるのと同じようなものかもしれません。
●仏事の役割
そういう風に、視点が強張ってしまいがちな私たちに、「その視線をちょっと上に向けてみたら?」と教えてくれるのが、仏教の一つの役割であると思います。
そして、「仏事」や「お参り」をすることも、それに連なる行為だと思います。普段の生活の中ではなかなか気づかないこと、考えないこと、感じられないこと。そういうことに思いを向けるのが、仏事を行うという場であり、時間である。それは、自分のいのちについて考える場でもあり、死を想う場でもあり、そして、亡くなった人、大切な人との縁であったり、その人のはたらきが、実は今も届いているということを感じるための時間・空間なのです。
それは、普段見ようとしていないもの、なかなか目が向かないものに対して、目を向ける、ということです。釈徹宗先生は「宗教儀礼は日常の忙しさでどんどん縮んでいく時間を延ばすための装置である」というようなことをおっしゃいます。まさにその通りで、世俗の生活のなかで、ふっと立ち止まる。そしてちょっとだけ目線を変える。それによって、そこに厳然とあった虹や月に喩えられるような「はたらき」というものに、気づいていけるようになるのではないでしょうか。
さきほど、法然上人の詩では、月は阿弥陀仏という仏さまのはたらき、南無阿弥陀仏を喩えたものと書きました。その味わい方を少し変えて、月を「亡くなった人のはたらき」としてみると、どうでしょう。私たちがどうして人が亡くなった時や、ご法事、という場で「お参り」をするのか?ということの意味がほんの少し理解できるように思います。
「お参り」をする、ということは、そのような「はたらき」に気づき、出会うための行いなのです。
●存在のはたらき
しかし、そんな「亡くなった人のはたらき」などとものが本当にあるのか?ということは、非科学的だ、論理的ではない、というように疑問に思われる方もおられるでしょう。このあたりのことは、なかなか実感したり、言葉として表現したりすることは難しいものです。そんな中、先日、哲学者の森岡正博さんの書かれた『33個めの石 傷ついた現代のための哲学』という本を読んでおりますと、森岡さんが身近な人の死を通して、死生観が変わった、ということを書かれていました。その一節にはこうありました。
私は、死んだ人は私の記憶の中に生き続けているだけではなくて、実際に、世界の隅々に何かの形をとって残り続けていると思うようになったのだ。私は宗教を信じてはいないし、人間の魂といった存在もまた信じてはいない。しかしそれにもかかわらず、死んだ人は、なにか体温のようなものとして、あるいは吹きすぎる風のそよぎのようなものとして、あるいは季節の気配のようなものとして、この世に残り続けていると確信するようになったのである。
森岡正博 著『33個めの石 傷ついた現代のための哲学』
そして私は、自分にとっての追悼の意味もまたはっきりと理解するようになった。それは、死んでこの世から消え去ってしまった人に対して手を合わせているのではなく、死んだあともこの世に別の形をとって残り続けているその人に対して、手を合わせているのである。
私は、黙禱しながら、「あなたのことはけっして忘れないから、あなたもこれから私のことを見守っていてください」と祈るのである。
私ももしかすると、森岡さんと似たような死生観を持っているかもしれません。人は、その言葉や行動、そして存在すること自体、大きな影響力を持っています。そしてその影響力というものは、その人が亡くなったとしても、決して雲散霧消してしまうわけではありません。その人が為したことや、縁があった人を通して、その人が「在った」ということは残り続けることでしょう。そしてそれは縁が深い人ほど色濃く残り、その後の生涯にも影響を与えてくれています。つまり、亡くなった方の存在というものは、決して消え失せてしまうことなく、私の「いのち」に寄り添う「はたらき」となっているのです。
しかし、このような「はたらき」に気づいたり、感じられたり、ということはなかなかありません。日々の生活に忙殺されてしまっていると、それは尚更でしょう。だからこそ、私たちにとっては、そこに目を向けるという行いが必要となってきます。それこそが「お参り」をする、ということです。そして「お参り」をするということは、法然聖人の詩にあるように「月を眺める」ということです。月に目を向けたならば、その光が私たちの心に至るように、亡くなった方の「はたらき」にも、「お参り」という行為を通して目を向けた時に、私たちの心に感じられてくるものとなっていくのではないでしょうか。
仏事を勤めるということ。「お参り」をするということ。私がここに書いたことはほんの一端に過ぎず、本来もっといろんな意味や、意義があるものだと思います。しかし、そういうものが薄らぎ、忘れられていく中で、今回取り上げたような出来事が起こってきたとも考えられます。
このことがきっかけとなって、皆さんにも、仏事を勤めること、「お参り」をすることの意義を改めて考えていただけたらなと思います。