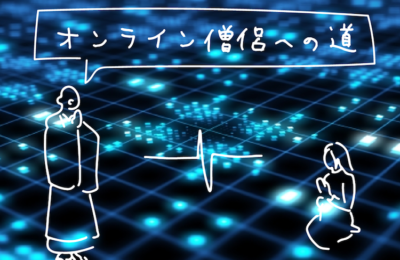2019年2月9日(土)、10日(日)の2日間、京都・本願寺伝道院にて「スクール・ナーランダ vol.4」が開催されました。
スクール・ナーランダは、浄土真宗本願寺派 子ども・若者ご縁づくり推進室が主催(企画:エピファニーワークス)する、こころの「軸」をつくる学びの場。これから社会に出る10〜20代の若者が、多様な価値観のなかで自分の「ものさし」をつくるヒントになるような、知恵や人との出会いの場をつくる”現代版寺子屋”です。
授業を行うのは、仏教を軸に科学者、エンジニア、芸術家など多様な分野から招聘された一流の講師陣。授業とディスカッション、そして仏教ゆかりの体験プログラムを組み合わせて行われています。
今回のテーマは十人十色の価値観が表現できる社会を真剣に想像してみる」。ファッションやダンスの世界で表現するクリエイター、進化論から人類を見つめる科学者、twitterを駆使して自分を表現するライター、「仏さまの世界」を表現する僧侶とともに学び、ともに考える場が開かれました。
レポート前編では1日目の授業の内容を一部抜粋にてお届けします。
●若者たちに開かれたお坊さんたちの”学びの場”
会場となった本願寺伝道院は、明治28年(1895)につくられた伊東忠太設計の近代の名建築。現在は、本願寺派僧侶の「教化育成の道場」、つまりお坊さんたちが学ぶ場に使用される建物であり、一般には公開されていません。スクール・ナーランダの2日間は、特別にこの厳かな建物が若者たちの学びの場として開かれました。

朝いちばん、ちょっと緊張した面持ちで集まってきた参加者は、8人ごとのグループに分かれて席につきました。各グループには、参加者と同年代で構成される「チーム・ナーランダ」のスタッフが入りサポートします。
授業が始まる前には、心と体をほぐす「アイスブレイク」も。全員で手をつないで大きな輪をつくり、右側から伝わってきた動きを左側に伝えていきます。だんだん、みんなの表情がほどけて柔らかくなり、あちこちで小さな笑い声が起きるまでになりました。


さて、場があたたまったところで、授業のはじまり。一人目の先生は、「minä perhonen(ミナ ペルホネン)」を主宰するファッションデザイナー・皆川明さんです。
●不器用だったからこそ一生の仕事にしようと思えた(皆川明さん)
皆川明さんが、自身のファッションブランド「minä(現minä perhonen)」を設立したのは1995年のこと。皆川さんが28歳になる年でした。オリジナルデザインの生地づくり、デザイン、生産の管理、ショップ運営まで、服をつくってお客さんに手渡すまでの様々な工程を手がけています。

スクール・ナーランダでは、皆川さんは自らが歩んできた人生の話を、ひとことひとこと、聞き手の心に届けていくようにしてお話されました。
・一生やると決めていたから成績の優劣は気にならなかった
高校生まで、陸上競技の長距離ランナーとして活躍していた皆川さんは、18歳のときに大きな怪我をして、陸上の道を諦めなければなりませんでした。しかし、高校卒業後にヨーロッパをバックパッカーとして旅していたとき、偶然にもファッションウィークのパリを訪れることになります。そこで、アルバイトする機会を得た皆川さんは、ファッションの世界から強い刺激を受けました。
「ジャージしか着ていなかった自分には、楽屋からちらっと見えるショーがとても華やかで強い刺激を受けました。怪我をして陸上競技をやめて、どうやって生きて行くのか探す旅でしたから、新しい経験だったファッションを一生の仕事に決めてしまおうと思いました」。
もともと「手先は不器用だった」という皆川さん。その”不器用さ”を「苦手というのは良いことかもしれない。40年、50年と生きていくなかで、ちょっとずつ成長がわかるのではないか」と前向きに捉えたそうです。
・A4のコピー用紙に書いた「せめて100年」
学生時代には、縫製工場やオーダーメイドのお店でアルバイト、その後はオリジナルファブリックで洋服をつくる会社で仕事をしたのち、28歳のときにつくったブランドが「minä(フィンランド語で「私」という意味)」でした。

「手先が不器用で、クリエイションの能力は高くないと思っていたから、布からつくって、かたちを決めて、すべての工程で自分の思うことをやれば、自分らしくなるのではないかと思ったんです」。
昨年、「ファッション業界全体では新品の衣服の約半数にあたる、年10億点が売れずに廃棄(あるいは安価に転売)されている」という報道があり話題になりました。
皆川さんが「minä」を立ち上げた1995年には、すでにそんな時代の兆しが見えていました。「せっかくつくられたものが、たった半年で価値を失うことでいいのだろうか?」と疑問を感じた皆川さんは、「そうではないやり方で、自分のブランドをつくる」ことを決意します。

「そのとき、A4のコピー用紙に「せめて100年」と書いています。100年もすれば、やっていることがだんだん深みを増して理想的な状態をつくれるんじゃないかと思ったので。自分の人生で何かを達成しようというよりは、100年先にどうなっていたらいいかを考えよう、と」。
「minä」を立ち上げてから数年間、皆川さんは朝4時からお昼まで魚市場で働き、午後から洋服づくりの仕事をしていたそうです。ファッションの仕事だけでは、生活を支えられなかったからです。でも、皆川さんはこの魚市場で「ファッションで大事にしていることをたくさん学んだ」と言います。
たとえば、マグロの競りの際に肉質を測るしっぽの肉。大トロの多いマグロは、しっぽでさえ同じクオリティがあるのだと知り、皆川さんは「自分のものづくりもどんなに細かいところも手を抜いてはいけない」と決めました。また、仕入れにくる料理職人さんは、腕のよい人ほど道具の手入れがよく、材料を見る目が良いことに気づくと、「技術を磨くことは材料を見る目を磨くことだ」と深く心に刻みます。

今の皆川さんは、「自分のブランドの仕事だけでやっていきたい」という当時の夢をかなえました。しかし、当時と今を比べると「種類は違うけれど、楽しさ、充実感、しあわせ具合は変わらないものだな」と感じていると話します。
人生のすべてを「ファッションの仕事」として捉えている皆川さんだからこそ、「(当時と今の)しあわせ具合は変わらない」と言えるのだと思います。
・人生の喜びをどう交換していくか?
1995年に「minä」として立ち上げたブランドは、2003年に「minä perhonen(perhonenは、フィンランド語で「ちょうちょ」)」に。毎年おおよそ100種類、これまでに約3000種類のオリジナルテキスタイルをつくってきたそうです。
皆川さんは、「minä perhonen」の洋服づくりがそこに関わるすべての人ーー糸屋さん、生地をつくる工場、縫製する人、そしてデザインする人ーーにとって、「生きているなかでの充実感を持つものになってほしい」と願っています。

「つくる人の生活の糧やよろこび、つかう人の喜びの交換の間にいるのがデザイナーだと感じています。だからこそ、社会のなかでのあり方、ものづくりの現場が継続するためのつながりをつくっていくことを大事にしたい。近江商人の三方よしは、『売り手よし、買い手よし、世間よし』と言いますが、『つくり手よし』や『未来よし』も加えて、それぞれが人生としての喜びをどう交換していくかが大事かな、と。心地よく、喜びが伝染していくようなことになるとよいと思います」。
世の中にあるモノは、誰かがデザインをして、手を動かしてつくったもの。「こんなものがあると素敵だな」「こんなモノがあれば暮らしが楽になるな」と考える人がいたから、わたしたちの手に届いています。「これが好きだな」「暮らしのなかに置きたい」と思って選ぶということは、そのモノをつくった誰かの思いを受け取ることでもあります。
「モノは物質ではあるけれど、思いひとつでちゃんと命を持つものだと思います。それは、物質のなかに記憶が入るからじゃないかと思う。消費という言葉をつかうと消えてしまう錯覚があるけれど、手にとってくれた人の人生にとどまるようなものをつくりたい。その人が愛着を持つものになり、人生を映すものになりたい」。

最後に、皆川さんはもう一度、18歳を振り返り「陸上競技で怪我をしたことが、結果的に自分の未来がつくられるきっかけになっている」と話されました。ものごとは、「成功か、失敗か」「よいことか、悪いことか」という尺度だけでは測りきれない。どんなものごとも「よいこと」を孕んでいるのだ、と。
「いろんな事象と向き合ってよく観察をして、自分が考え続けることが大切かなと思います」と授業を締めくくった皆川さんに、会場から深い拍手が送られました。
●小さな非日常をつくることから踊りが始まる(島地保武さん)
ふたつ目の授業の先生は、日本を代表するコンテンポラリーダンサー・振付師の島地保武(しまじ・やすたけ)さん。遠くに立っていてもまっすぐに目に飛び込んでくるような、佇まいのうつくしい人です。

2004〜6年を、日本唯一のプロフェッショナルのダンス・カンパニー「Noism」で、2015年まではドイツ・フランクフルトの「ザ・フォーサイス・カンパニー(The Forsythe Company)」に所属。今は日本を拠点としながらも、2018年にはフランス国立シャイヨー劇場のレジデンスプログラムに、日本人として初めて選ばれるなど、国内外で活躍されています。
皆川さんからのバトンを受け取るように、島地さんもまた自らの歩んできた道を振り返り、「どのようにして今があるのか」をお話ししてくださいました。
・「ダンス甲子園」に衝撃を受けて踊りはじめた
島地さんが、ダンスを始めたのは中学2年生のとき。当時人気だったバラエティ番組「天才・たけしの元気が出るTV」の「高校生制服対抗ダンス甲子園」というコーナーを見て衝撃を受けたそう。初めて見るボディウェーブを真似て塾で披露してみると友だちから喝采を浴びました。
Youtubeもダンススクールもない時代のこと、島地さんは「ダンス甲子園」をビデオに録画して擦り切れるまで見て練習を重ねました。高校では、「ダンス甲子園」のチャンピオンだったLL BROTHERSの影響もあり空手部に入部。そして部活を引退したのち、「身体を動かしたくて」ふたたびダンスを始めます。
「いろんな種類のダンスを学べるところはどこだろう?」と考えた島地さんは、大学では演技コースを選択。そこで、モダンダンスに出会います。

会場を歩き回ったり、空いている席に座ったり。会場との関係性を変化させながら授業をする島地さん。
「わからないから、きっと理解できなかったから、気持ちわるいか綺麗かわからないギリギリのところに惹かれて。そしたら、先生に『あなたいいわよ』とおだてられてノッちゃって、『よし、プロになろう。ダンスで食べていこう』と思いました。当然そんなに甘くはないんだけど、根拠のない自信だけはありました」。
ご両親に反対されながらも、島地さんはアルバイトをしながらダンスを続けました。ところが24歳の頃、バイトとパチンコを繰り返す”悪循環”にハマってしまい、そこにプライベートでもショックな出来事が重なります。
「そんななかで、活力をくれるものが踊りだったんですねえ。ということで、またダンスをはじめまして。どこにも所属せずにダンサーとして舞台に立つことを続けて。大学でダンスをはじめて8年後には、憧れていたウィリアム・フォーサイスが主宰する、ドイツのカンパニーに入ることができたんです」。
・手に持っているものの重さを感じてみる
「ザ・フォーサイス・カンパニー」に入ったところまで話すと、「残り時間あと10分」になったことに気がついた島地さん。「もうそんなに?」と驚きながら、「ひとつだけ、運動しよっか」と提案しました。

「今、手に持っているものはありますか? その重さを感じてみてください。ペンの重さ、自分の手でもいい。最小限の力で持って、重さを感じてみてください。能楽師の方に教えてもらったんですけど、ものを綺麗に動かすには重さを感じたらいいそうです。ということも、自分の体もそうなんじゃないかな。空間のなかを動くんじゃなくて、自分の体を、頭の重みを感じてどこかに持っていくようにしてみて」。
会場にいる人の動きが、小さく変化しはじめました。力を込めて握っていたペンがふっとやわらかく持ち上げられるだけで、空間が変化していくのがわかります。島地さんは、さらに「椅子の重みを感じてみよう」と呼びかけました。みなが立ち上がって椅子を持ち上げます。
「主役は椅子だと思ってください。自分は脇役です。非日常にしていきます。音を立てないように、後ろ歩きをしましょう。じゃあ、椅子の座面にふだんは乗っけない、体のどこかを乗せてみて」。
島地さんの言葉によって、自分自身の身体と動き、周りにあるものとのあたらしい関わりをつくりはじめる参加者たち。じわじわと場に動きが生まれていくのですが、それはどこか「いつも」とは違った表情を持つ動きです。

「右にあるものを左手で取って、左にあるものを右手で取る。それは、日常ではやらない非効率的なことかもしれないけれど、それによって動きができて、それが連動することで踊りになっていくと思う。つり革をあえて持ちにくい手で持って、階段を後ろ向きに上がっていくという動きを日常に入れると、そこに非日常が生まれます。持っているもの、自分の身体の重さを感じて、身体を空間に運んでいくことをちょっと意識して見ると面白いかもしれません」。
ダンスというと、特別な動きやかたちをつくることのように思われがちだけれど、ほんの少しふだんの動きをズラすことから、踊りが始まっていくーー島地さんがそこにいるだけで、日常に隙間ができて空間がやわらかくなるように感じられました。
●ランチの精進料理「お斎」と「匂い袋づくり」ワークショップ
ランチは、本願寺御用達の老舗「矢尾治」さんによる、浄土真宗の精進料理「お斎」をいただきました。食後には「八尾治」さんへの質問タイムも。初めて食す人も多かったようですが、みんな「お斎」に興味津々でした。


みなで手を合わせて、食前の言葉、食後の言葉を唱えます。
食事の後は、2つのグループに分かれて、本願寺門前の老舗「薫玉堂」さんによる匂い袋づくりワークショップと、本願寺ツアー(書院拝観)を交代で行いました。



本願寺ツアーでは、通常非公開の書院を拝観。かつては、ご門主が賓客を迎える空間だった「白書院」、歴代ご門主が寺務をされた「黒書院外観」、現存する最古の能舞台「北能舞台」などを見学します。なんと、書院だけで7つもの国宝があるのだそう。お坊さんによるくわしい説明つきで、じっくりと見ることができて本当にぜいたくです。


ランチとワークショップ、本願寺ツアーでリフレッシュしたのち、ふたたび午後の授業がはじまりました。
●”自分らしさ”はどうつくられていくのか(藤丸智雄さん)
1日目最後の授業の先生は、浄土真宗本願寺派僧侶の藤丸智雄さん。岡山理科大学で非常勤講師として倫理を教えるとともに、浄土真宗本願寺派総合研究所の副所長も務めておられます。

藤丸さんは、大学の授業で行う調査のなかで「必ずみんなの意見が一致する調査がある」と言います。それは「自分らしさは大切だと思いますか?」という質問。100人中、97、8人は「そう思う」と答えるなか、2、3人は「人に合わせることも大事だと思う」と、同調圧力を感じさせる意見を出すそうです。
藤丸さんは「では、自分らしさを表現できる社会になるには、どうしたらいいだろうか?」と問いかけました。
「誰かの自分らしさ、他人らしさに気づいて、承認していける社会になれば、みんなが自分らしさを表現できるようになるのではないでしょうか。自分が自分らしくあるのはけっこう難しいです。むしろ、自分が他人らしさを表現するところに良さがあるんじゃないかと思っているんですね」。
日本のことわざに、仏教に由来する「袖振り合うも多生の縁」というものがあります。「この世での人との出会いは、前世でむすばれた因縁によるものかもしれないから、どんな出会いも大切」だと考えるのです。たった一度しか会わない人でさえ「多生の縁」があるのなら、家族や友人であればどれほど深い因縁があるのでしょうか。

藤丸さんは「今起きていること(出会い)の連続をよく理解することこそが、自分らしさをつくるのではないか」と話されました。
「わかるということは分類することでもあります。良いか悪いか、内か外かと分けることから、少数意見を排除する同調圧力が働いてお互いを承認しあえなくなります。そうではなくて『出会ったんだ』ということになると、相手を理解しようとするので他人らしさを認められるのではないでしょうか」。
藤丸さんの「自分らしさとは?」という問題提起を引き継ぐかたちで、3人の先生方による鼎談がはじまりました。
●鼎談とグループディスカッション
授業の後は、エピファニーワークスの林口砂里さんが司会する、先生方の鼎談が行われました。林口さんは3人の授業の内容を振り返りながら、「自分らしさとは?」という問いを深めていきました。

・「自分らしさ」と「無我」の意外な関係?
たとえば、縦長の長方形に30のドットが描かれている「minä perhonen」のマークについて。林口さんが「このドットは個性の集まりだとおっしゃっていましたよね?」と問いかけると、皆川さんは「たくさんの個性、人格が入ってひとりの人間になっているんじゃないかと思っている」と答えました。
すると、今度は島地さんに「自分のなかのいろんなものを表現されているのでは?」と話を運びます。「一番いいのは、自分がない状態でそこにいること」と答えた島地さん。
「特に、人と踊る時には思いもよらぬことが起きるから、それに対処していくのが楽しいんです。僕がどうしたいかということは強く持っているけれど、本当はなくしていきたいというか。まず関係性があって、自分がいるということを目指しています」と話されました。
どこか仏教的な島地さんのお話に、「仏教では、自分らしさと一見相反する”無我”という言葉があります」と答えた藤丸さん。「おふたりがお話されたように、誰かから受ける何かによって自分が変化することを需要することが、本当の意味での出会い」だと言います。さて、この鼎談を経て参加者のグループディスカッションはどんなふうに展開したのでしょうか?
・自分らしさは「自分ひとりだと見えてこない」
グループディスカッションは、チーム・ナーランダのスタッフがファシリテーションをする形で進行しました。1日の授業の内容を振り返りつつ、一人ずつが感想や意見を話し、グループ全体で議論がはじまります。



後半は、先生方がグループを訪問するかたちで質疑に答えました。ランチタイムや本願寺ツアーなど、先生方と直接話す機会がたくさんあるのも、実はスクール・ナーランダの大きな魅力のひとつだと思います。

最後は、各グループ2分ずつの発表でディスカッションの内容を共有しました。チームの多くは「自分らしさとは?」「個性とは?」「同調圧力から逃れるには?」というテーマで話合っていたよう。興味深いことに、複数のグループが「他者との関係性のなかで自分らしさは見つかる」と他者の存在に言及していました。また、いくつかのグループは「自分らしさ」を求められることのしんどさにも触れていました。
発表後、先生方からコメントがありました。皆川さんが「月を見ると、三日月だな、半月だなと思うけれど、いつも月は球体。自分の状況や角度によって、他者も違って見えるということだと思う」と話すと、多くの参加者がノートにペンを走らせるのが見えました。また、島地さんは「人と真剣に話す時間がすごく重要だなと思う。他人らしさに興味を持つことが自分に返ってくるのでは」とコメントすると、みな頷きながら聞いていました。
藤丸さんは「個性的であれと言いながらも、個性的であれる場がつくられていないこともある。結局は、自分が何をしているときが楽しいのか、心の素直な声を聞いていくことではないか」と話されました。たしかに、「みなと同じようにせよ」と言われたり、「個性的であれ」と言われたり。10〜20代の頃は、学校や世の中から、「自分らしさ」を求めたり封じ込めたり、「どっちなの?」とため息をつきたくなることがあったなぁ……と思います。

そんな年代だからこそ「心の軸」となる何かについて、考えるひとときを持つことがとても大切なのだと改めて思わされました(後編に続く)。