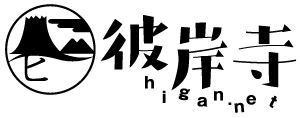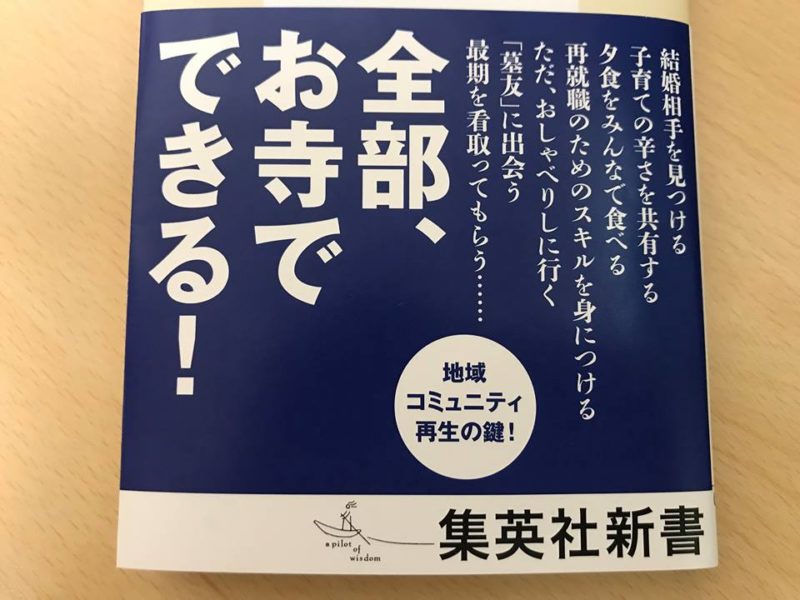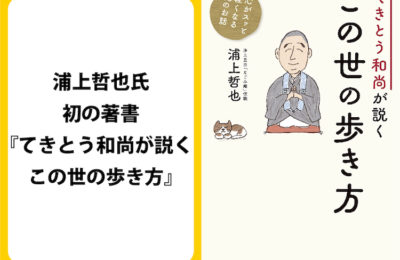星野哲さんは、元朝日新聞の記者さん。「人生のエンディングを社会でどう支えるか?」に関心を寄せ、約30年に渡り取材・研究を続けてこられました。今回、7月13日発売の新著『「定年後」はお寺が居場所』(集英社新書)は、これまでの取材・研究を通して出会ってきたお寺に感じておられる可能性を綴られた本。彼岸寺の読者のみなさんにも届けたいと思い、星野さんにご寄稿をお願いし、ご快諾をいただくことができました。ぜひ、ご一読ください(杉本恭子)。
—
『「定年後」はお寺が居場所』(集英社新書)という拙著を上梓した。
内容を一言で要約すれば、「生きているうちにお寺に行こう!」という呼びかけだ。定年後とは関係ない内容なので、書名は著者自身にも謎である点はさておき、お寺が地域コミュニティの中で大切な居場所になりうることを、事例をもとに書いている。
居場所とは、文字通り人が集ったり、何か問題や課題を抱えた人たちがひと時を過ごしたりする場といった意味で使っている。社会的リソースとしてお寺をとらえた内容だ。居場所としてのお寺や、多様な人を受けいれてくれるお坊さんにどうしたら出会えるのかということを、私の体験から記してもいる。彼岸寺についても、ほんの数行だが触れている。
2つの「もったいない」
私は30年以上前、お墓や葬儀の変化に興味をいだいたのがきっかけで、人生のエンディングを社会でどう支えるかに関心をもち、取材・研究を続けている。その過程でお寺に出会い、少なからぬ魅力的なお坊さんたちからご縁をいただいてきた。そんなお坊さんたちとお付き合いするうちに、2つの意味で「もったいない」と思うようになった。それが拙著を上梓したいという動機になった。
一つは、お寺がもつ可能性を、一般の人たちが知らない「もったいなさ」だ。
お坊さんは自覚しないままに、自然と人々のためになる活動を日常的にしている人が少なくない。高齢者の愚痴を聞いたり、子どもの安全に目を向けたり、民生委員や教誨師として活動したり。当たり前だと思ってしていることが、人々に寄り添い、手を差し伸べる活動になっている。それが、お寺をホッとする場所にしたり、人と人とのつながりを生み出したりしている。
そのことがあまりにも世の中から知られていない。それどころか、「坊主丸儲け」的な偏見にさらされている。お寺に行けば、もしかしたら自分の抱えている悩みが軽くなったり、課題解決につながったりする可能性があるにもかかわらず、その可能性に多くの人が気づいていない。その可能性の一端でも知ってもらいたいと思った。
だから、子育てや貧困、過疎、エンディングサポートなどの社会課題をいくつか設定して、その解決に寄与していると思われる、できるだけ「わかりやすい」活動を中心に取り上げた。目を引くお寺やお坊さんを取り上げることで、可能性の大きさを認識してもらえればと考えたのだ(取り上げた事例は、たとえば大阪の應典院など「お寺業界」では有名なお坊さんが少なくない。だが、お坊さんのことはお坊さんが思う以上に世の中には知られていない。そのことを編集部とのやり取りの中で私自身が痛感させられた)。
浮世離れだからこそ
もう一つの「もったいない」は、僧侶の側に向けてだ。自分たちがしていることや信仰に、あらためての自覚と自信を持ってほしかった。
現代社会では宗教自体、その寄って立つ基盤がどこにあるのか、そもそも人々が認識している宗教とは何か、その意義や意味がどこにあるのかがあやふやになっている。社会学者Z・バウマンが指摘する「液状化」だ。それでも、いや、だからこそ、宗教者には人々と、社会と、「対話」をしてほしいと思っている。
いま、資本主義の価値観がすべてを覆いつくしたように「より上へ、より多く、より大きく、より速く」と、多くの人々は絶え間なく駆り立てられている。地域コミュニティや家族といった社会的中間集団が弱体化・解体し、むき出しの個人があらゆる問題に直接向き合わざるをえなくなっている。
本書で私は僧侶を「浮世離れ」の存在だと記した。それは悪い面もあるが、いい意味で「経済ファースト」の価値観とは異なるものを提供しうる存在だと思っているからだ。
また、むきだしの姿で傷ついた人々がひと時を過ごし、癒される場として、寺がアジール的な場として機能しうると思う。先述したように、意識しないまま、人のためになっている活動をしているお坊さんは少なくないし、事例にあげたお坊さんたちの活動に私は敬意を抱いている。要はお坊さんに、自分たちの可能性に意識的になってほしいし、自信を持ってほしいのだ。
たしかに「浮世離れ」だけに、対話の仕方にいささか難のある僧侶もいるし、何かがズレていると感じる僧侶だっている。だが、社会の中で自身の活動や信仰がどのような意味を持つのか考え、その意義に自覚的になるだけで「対話」はかなり進むのではないかと思っている。
ほんの少し自覚的になるだけでかみ合う部分は広がり、周囲の反応はまったく違うものになるはずだ。それだけに、「もったいない」と感じている。自覚的とは、対話とはどのようなものなのかを、僭越ながら本書からくみ取っていただける点があればいいな、と思っている。
橋渡しになれば
社会の側にも偏見があると先述した。だから、いまさら感はあるかもしれないが、本書では「サードプレイス」や「ソーシャルキャピタル」「ソーシャルサポート」といった社会学の用語を使って、お寺が社会的リソースとして大切な、有効性のある存在であることを説明した。お寺や仏教に関心のない人にも、できるだけ「届く」言葉を探してのことだ。
本書が少しでも僧侶と社会の間の「橋渡し」の役割が果たせれば、望外の喜びだ。そのことで、お寺が社会にとって大切な「居場所」として認識されればいいと思うし、お寺の居場所が社会にあり続けてほしいと願っている。
 星野哲(ほしの・さとし)
星野哲(ほしの・さとし)
立教大学社会デザイン研究所研究員、(一社)介護デザインラボ理事。元朝日新聞記者。東京墨田看護専門学校非常勤講師。人生のエンディング段階を社会でどう支えるかを取材・研究する。市民が主体となった社会のありようを重視するなかで、寺院の役割にも着目している。単著に「終活難民-あなたは誰に送ってもらえますか」(2014年、平凡社)、「遺贈寄付 最期のお金の活かし方」(2018年、幻冬舎)ほか。
[amazonjs asin=”4087210421″ locale=”JP” title=”「定年後」はお寺が居場所 (集英社新書)”]
[amazonjs asin=”4344032659″ locale=”JP” title=”遺贈寄付 最期のお金の活かし方”]