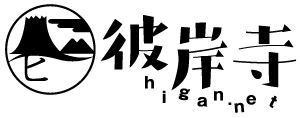西蓮寺編集部(浄土真宗本願寺派)で『 i 』という雑誌を発行している小西慶信です。これまで様々な特集の企画を通して、他者との関わりの中に生じる生きづらさについて考えてきました。今回は「能力の低さへの厳しい眼差し」にまつわる話を取り上げます。
======================================================================
「一瞬で済む業務連絡を、わざわざ電話してくる人ってムカつきません? メールだったら、こっちの手があいたときに返信できるのに、電話だと鳴るたびに手元の仕事を中断しなくちゃいけないから効率下がるんですよね。あれって、伝えたいことの要点を文章でまとめられないから、話の雰囲気で伝えようとしてるんですよ。自分が人の時間を奪ってるってことを想像できない人が多いんですよね」
ずいぶん昔に目にした、とあるインタビュー記事の一場面です。ぼーっとスマホを眺めていたときに、たまたま目に飛び込んできた一節だったにも関わらず、妙に記憶に残っています。
――人の時間を奪ってる
このフレーズが記憶に残っているのは、単に聞き慣れない言葉だったからではありません。「奪われた」という表現を使えば、相手を一方的に加害者に仕立て上げることができるし、自分は被害者になれる。そうすればたくさんの共感を集められる。そんな態度がひどく傲慢に思えたからです。でもそれ以上に、自分も誰かの時間を奪っているのではないか、そう思われているのではないかと不安になったからでもありました。
数年前まで、私は90代後半にさしかかる祖父と同居していました。が、これがなかなか大変でした。 「おじいちゃんがベッドから落ちた」という祖母の大声が深夜に響き渡ることも珍しくなく、その度に起こされます。また耳が遠いのでわざわざ耳元まで近寄って話さなければならず、特に聞こえづらい日は叫ぶようにして話さなければなりませんでした。日々のわたしの作業は中断を迫られ、集中を奪われます。祖父のささやかな「できなさ」がいちいち癇に障ったのです。
祖父はわたしの手を借りるたびに、「すまんのぉ」とか「ありがとのぉ」といった言葉を伝えてくれる人でした。しかし、そうした出来事が積み重なってくると、だんだんと何かに束縛されているような息苦しさを覚えます。身の回りのことが自分でできないと、どうしても他人の手を頼らざるを得なくなる。誰かが、その人のためにいろいろと面倒をみなければならない。そうした時間が繰り返されるうちに、いつしか「手を差し伸べる」ことを強いられているように感じてしまうのです。
――わたしの時間が奪われている
ふっと頭の中に浮かんだ言葉に、思わずギョッとしました。受け入れられないと拒んだはずのその一言が、私の息苦しさを悔しいほどに言い表していたからです。
能力に対する信仰
哲学者・鷲田清一は、ものの価値をその生産性から測ること、あるいは〈いのち〉の本質を生産に見ることを「生産力主義」と呼んでいます。「 ――できる」「 ――与える」「 ――役に立つ」ことに価値を見出す立場です。その意味で、〈若さ〉がその活力において愛でられ、〈老い〉は遠ざけたいもの、回避したいものとみなされる。
人の生を「できる」という基準で考える限り、老いていくことは、ひたすら「できる」世界が縮小してゆく過程をたどらざるを得ません。ここにむなしさが介在すると鷲田は言います。なぜなら、人や社会の役に立つというかたちでしか、私たちは意味を見出す方法を知らないからです。だんだんと「できる」ことが減って誰の役にも立てなくなるどころか、人の手を借りなければ生きていけなくなります。そうなって「自分はお荷物、厄介者でしかないのではないか」と問わないで生きているひとはどれほどいるだろうかーーと。そういう無力感やむなしさの中でしか〈老い〉を捉えられなくなっているということを、鷲田は「老いの空白」と呼んでいます。
しかし、ふと疑問に思うことがあります。例えば介護のようなサービスは当然それを必要とする人がいて初めて成り立ちます。供給側に価値を見出すには、需要サイドの存在が不可欠であり、両者は相互に補完しあう関係であるはずです。それなのになぜ、一方は優れていて他方は疎ましいとみなされてしまうのでしょう。
近年は介護が社会化――つまり介護の担い手を家族だけのものとせず社会全体で支えていこうという流れが広まっています。しかし、ケア・サービスの関係性には、「サービスの受け手はそこから降りられないが、与え手は降りられるという非対称性があり、そこにサービスが権力関係へと転化してしまう契機がある」と鷲田は指摘しています。加えて、そもそも介護を受けるということは、それ自体が本来他者に秘匿にしてきた、みずからの身体のケアを、否応なく他者に委ねなければならないという事態を含んでいます。つまり、ケアの場面においては少なくとも、能力の優劣に権威勾配が存在しているのです。
都合のいい人
祖父は、亡くなる一年ほど前に一人で立つことはおろか、ベッドに腰掛けた姿勢でも身体をまっすぐに保つことができなくなりました。また、ある日急に意識が遠のくような事態に見舞われ、急いで救急車を呼ぶと、その日のうちに入院することになりました。
入院してもらえたのは正直「ありがたい」という思いがありました。これで夜中に大声で起こされたり、ベッドから椅子に移りたいと言われることもなくなります。自分の仕事や作業の手をとめて、わざわざ介添する必要もありません。それまでは祖父の希望を叶えるには誰かが時間と手を尽くさなければなりませんでした。一方が自由を望めば望むほど他方の自由が制限されていく。どうしたってそう感じてしまう自分を直視しなくて済むのも、気が楽でした。
入院に際して説明を受ける際、「回復後、多少自分で動けるようになったら退院しましょうか。ご家族の方はどの程度動けるようになることを希望されますか」と介護士の方から尋ねられたときは驚きました。そういうのってこっちで指定できるものなんだ、と。
「まあ理想を言えば、自分で立って、歩行器を使って歩けるくらいになってくれると助かりますけど……」と素直に答えました。「わかりました。精一杯サポートします」と介護士。
これで、一番身近で支えていた祖母もぐっすり眠れるようになるだろう。家族みんなで胸をなでおろしました。けれど肩の荷が下りたはずなのに、なぜかすっきりしません。帰って来るならできるだけ手のかからない状態になってからであってほしい。そんな本音が自分の中で小さくうずくのです。
できないことが「迷惑」と捉えられる時代で
近年、老老介護という言葉を耳にするようになりました。また最近は、ヤングケアラーの存在が社会問題として世間に認められつつあります。ケアにまつわる痛ましい事件がニュースで取り上げられるたびに、誰にも頼ることができず一人で(あるいは家族で)抱え込んでしまった者の痛みが、ネットでは多くの注目を集めています。
だからこそ、ケアの負担は社会全体で担っていくべきだと私も声を挙げたいと思っています。逆に「家族同士で支え合う姿は素晴らしい」という物語を過剰に美化し吹聴することは危険であるとさえ感じます。祖父を病院に預けることは何も間違っていません。仕方のないことなんです。 それでも、自分の身体の中に無視できない声がある。
――私の時間が奪われている
――帰るなら、できるだけ手のかからない状態になってからであってほしい
そんなことを考えていたとき、偶然こんな投稿が目に留まりました。
スーパーに片手が不自由な女性がいた。レジの人が手伝っていた。私の前でバッグに詰め終えたので「片付けますね」と私がカゴを戻したら「あ、すみません!すみません!ありがとうございます!」と何度も頭を下げた。こんな小さなことに、いちいち恐縮して頭を下げなきゃいけないなんて…と悲しくなった。「人に迷惑を掛けてはいけない」とか「自分のことは自分でしろ」とか、小さい頃から言われ続けたことが呪いとなって、そうできなくなった時に人を余計苦しめると常々思う。誰もが当たり前に助け合う社会だったら、申し訳ないなんて思う必要はないし、いちいち感謝する必要もない。
(文筆家・樋口直美氏のX投稿より)
何度も頭を下げたというその女性に祖父の姿が重なります。私が手を貸すたびに申し訳なさそうにしていた祖父の姿が。そういえば、入院していたときの祖父は、担当の医師や看護師から「素直な人だ」と評判がよかったそうです。きっと聞き分けのいい患者を演じていたのでしょう。そうやって慎ましく遠慮する姿を「できない者」の理想として掲げていいのだろうか。誰かの手を借りなければならない人々は、遠慮して生きなければならないのでしょうか。
そんなことはないはずだ。そう言える自分でありたいのに、その言葉とは相反する自分勝手な考え方が私の中にありありと存在しているのを感じます。
生きるのに遠慮など要るものか。
たった一言のはずなのに、伝えられないまま祖父とは死別しました。別にそのことに後悔があるわけではありません。それでもなお、ふとした瞬間に、あの頃の祖父の姿が胸の奥に去来します。