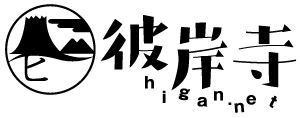「未来の仏教対談」は、今という時代をどうとらえ、これからの仏教をどう創造していくのかという若き僧侶たちの問いを巡って行われる、日本仏教界のリーダーたちと松本さんによる真摯な対談シリーズ。
第三回は奈良・東大寺、「奈良の大仏」で知られるあのお寺に、森本公誠長老を訪ねました。
森本長老は、15歳のときに東大寺に入られ、京都大学文学部でイスラム史を専攻。華厳宗の僧侶であると同時に、イスラム史の研究者として優れた業績を積み上げてこられた方です。2004〜2007年には、第218世東大寺別当・華厳宗管長を勤められました。
長い歴史を紡いできた東大寺というお寺に、森本長老がご自身をどのように掛け合わせてこられたのか。前編では、「学問寺」である東大寺において、森本長老が続けてこられた学問の道についてお話を伺いました。
(構成:杉本恭子)

森本長老と松本紹圭は“インドつながり”!?
松本紹圭さん(以下、松本)
一番最近、森本長老にお会いしたのは、日印友好交流年に関連した首相官邸での食事会でご一緒させていただいたときでしたね。
森本公誠長老(以下、森本長老)
私を呼んでいただいたのは、現職の管長だったときにインドに講演をしに行ったことがあるからだと思います。大仏開眼法要のときの導師は、菩提僊那というインドの僧侶でしたから、その話をしてほしいと言われたのです。「当時の日本は世界的な視野においてどう見られていたのか」「日本での仏教のあり方」「東大寺はどういうお経を根拠にして建てられたのか」というようなお話をさせていただきました。
どこにご縁ができるかはわからないんですけども、頼まれたことであればとにかく挑戦してみる。最近やっていることは、そういうことの積み重ねじゃないかと思いますね。
松本
たしか、同席した方達のなかで、僧侶は森本長老と私だけだったと思います。私はインド・ハイデラバードにMBA留学したというちょっと珍しい経歴から「インド」つながりで呼んでいただいたのだと思いますが、森本長老はイスラム研究に長年打ち込んでこられたユニークなご経歴をお持ちです。
今回は、そんな森本長老独自の僧侶としてのあり方について、いろんなお話を伺いたいと思って参りました。
15歳で東大寺にご縁を持たれたときに遡るのですが、「学問寺」であるということに惹かれたと伺っています。京都大学ではイスラム史をご研究され、エジプト・カイロ大学にも留学されましたそうですね。イスラムに親しんでこられたことは、宗教者としてのあり方にも反映されているのでしょうか?

森本長老
せっかく東大寺に入ったからには、「自分としてはここで何をすればいいのか?」と考えたのです。東大寺という大きなお寺を維持管理しないといけないのはもちろんですが、「しかし、それだけのために来たのだろうか?」と。
昔の「学問寺」というのは、時代に合わせて「人々とどう接するのか」「国家とどう接するのか」ということを念頭において学問をしてきました。では、これからの現代において「学問寺」はどうあるべきか、将来的にも有意義な問題点というものを、まだ若い、学生ながらに探していたわけです。たまたま、そういうなかでイスラムというテーマが浮かび上がってきたということですね。
「学問寺の僧侶」として選んだイスラム史
松本
東大寺に関わっていくお立場として「何を使命としてやっていくのか」というときに、「学問」というものがひとつ大事な要素としてあって。「今日の学問寺はどうあるべきか」とお考えになり、宗教を超えていくことの重要性から、イスラムに関心を寄せられたのでしょうか。
森本長老
いやいや、いきなりそこまではなかなかいかないのでね。中学、高校と少しずつ考えていったのだと思いますよ。特に、大学に入るとね、当時は「お寺なんて古くさい。宗教なんて時代遅れだ」という時代でしたからね。
松本
1950年代前半、マルクス主義全盛の時代ですね。
森本長老
マルクスはその著書で「宗教は民衆の阿片である」と宗教を批判しましたから、マルクスに心酔する周りの学生たちもそのように見ているわけです。また、当時の知識人の言い方としては「日本のお寺にあるのは、葬式か観光仏教だ」とガンガン入ってくるわけです。
そこではじめて「現代の社会では、宗教はまったく不必要なのか?」という問いが生まれ、どういう視点を持てばいいのかと考えたのです。せっかく大学に入れてもらったのだから、「東大寺」という肩書きを外れても「自分」としていられるものとして学問をやろう、と。
そこで、学問として仏教学や仏教史を学ぶという選択肢もあったのだけど、当時の私はあまり仏教に魅力を感じていなかったんです。

松本
魅力を感じなかった「仏教」というのは、具体的には教義の内容でしょうか?
森本長老
いやあ、子どもの頃に経験していた、お葬式に来られたお坊さんと親戚の者との受け答えであるとか、そういったことしか最初はわからないわけです。東大寺には檀家はいないし、葬式もやらないけれど、お寺のなかだけで一生を送るのかということだったんでしょうね。若いからこそ「何か、自分で見つけられるものはないだろうか」という気持ちがあったのだと思います。
松本
「自分で見つけられるもの」としての学問を、大学のなかに求められたのですね。
森本長老
京都大学文学部に入ったなら、東洋史が一番いいと言われまして。当時の東洋史は講座数が多くて、第三講座まであったんじゃないかな。主任には、いわゆる京都学派の中心を担われた宮崎市定先生をはじめとして、中国史を研究する優れた先生方がおられました。そうなると、先輩たちの多くは中国史を選んでいましたから、「未開拓の分野としてイスラムが残っているな」というくらいの単純な考えだったんです。
「護教」ではなく「科学」としての学問を求めて
松本
イスラム教は、ある意味においては、仏教とは全く違う宗教だと思います。イスラム史を通して、仏教を見つめ直すということも意図されていたのでしょうか。
森本長老
そうそう、まったく異質な宗教を学ぶことによって、逆に仏教のことがわかるんじゃないかとは考えていました。仏教そのもの、身内のことをやるとどうしても教学になる。どこのお寺にも教学はありますが、それは護教の学問ですよね。
松本
たしかに、批判的に見ようとするものではないですね。
森本長老
でしょう? だけど、いわゆる科学としての学問は、批判的な目でも見なければいけない。日本はそれをできなかったから、第二次世界大戦という結果を生んだのだと思います。戦争中は、偉い学者の先生たちでさえ、護教的にしか国家を見ることができなかった。もちろん、批判的な方もおられたけれど、それは身を危うくすることでもありましたからね。
「なぜ、学問があるのか」を考えると、批判的なものの見方を受け入れていかないと、まともな社会、国家は成立しないのではないかと感じていました。

松本
戦前の日本は、国家単位である種カルト的に一つの方向に進んでしまって、大変な過ちを起こしてしまったということに対する危機意識をお持ちになっていたのでしょうか。
森本長老
国民学校(小学校)では「天皇陛下万歳」「鬼畜米英撃ちてしやまん」と教えていた先生方は、天皇陛下が人間宣言されると「アメリカ万歳」とばかりに手のひらを返しました。そして、大学に入ると進歩的な先生方はマルクス主義ばかりで、「ソ連万歳」になってしまう。「なんでそうなるのか」という思いがありました。
松本
そうなると、今度は“マルクス護教的”な学問になってしまいますね。しかし、同世代の学生たちもまた子どものときに戦争を体験していたはずです。「なぜ、大人たちは180度手のひらを返したようになるんだろう?」という疑問を持つ可能性があるのに、なぜそうならなかったのでしょうか。
森本長老
やっぱりね、京都大学に入ってくるような学生さんは、良い家庭の坊ちゃんが多いんじゃないかなぁ。時代が時代ですから、なかには生活が苦しくて食事もちゃんと食べられない人もいましたし、経済的な理由から卒業できない人もありましたけれども。
戦争中の国家神道の代わりに、すがりつくものとしてのマルクス主義があって、みんながわーっとなびいていくわけですね。日本人は変わらないなと思いました。
その点、東洋史の先生方はほとんどブレませんでしたね。約4000年に渡って、絶えず王朝がくるくる変わっていった中国の歴史のなかに、一本筋が通ったものを見つけようと学問を進められていましたから(後編に続く)。