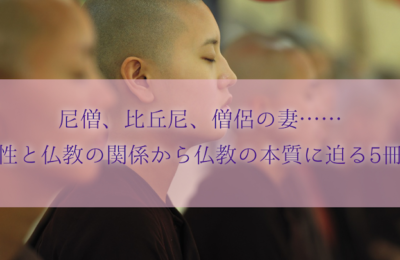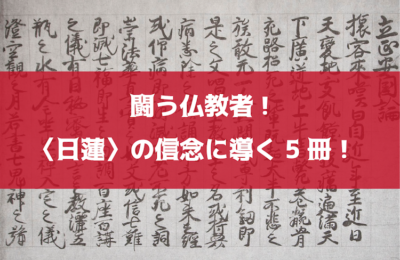今回のテーマは「死者」です。より具体的には、葬儀や供養です。日本の仏教が、ほぼほぼ「葬式仏教」として成り立っていることは、周知の事実かと思います。よって、葬式仏教の前提である「死者」について考えることは、日本仏教とは何かを語る上で、欠かせないテーマの一つです。
大前提として確認しておきたいのですが、仏教は本来、死者を対象としたものではありません。私という生きた人間のための教えです。あるいは、私というやがて死ぬ人間のための教えです。ここは決してゆずれません。
とはいえ、さまざまな成り行き=縁が積み重なり、日本の仏教は死者に対するプロフェッショナルになっています。その「プロ」であることの意味を、どう受けとめるべきか。この点について考えるために役立ちそうな本を、わりと最近に出版されたものを中心に紹介していきたいと思います。
①『「霊魂」を探して』 鵜飼 秀徳 著
[amazonjs asin=”4044001936″ locale=”JP” title=”「霊魂」を探して”]
『寺院消滅―失われる「地方」と「宗教」』(日経BP社、2015年)が大きな話題になった著者による最新刊です。現代日本人の死者とのかかわりや、「霊魂」観について、多面的に考察しています。特に、そこでの宗教者の役割に注目している点に、高いオリジナリティがあります。
東日本大震災の被災地で、「霊魂でもいいから、(亡くなった人と)会いたい」と語る人びとに出会った著者は、そうした死者に対する切実な思いを、現在の宗教者、とりわけ僧侶(著者自身も浄土宗僧侶です)がどう受けとめているのかについて、実態調査を試みようと決意します。僧侶1335人に対する「霊魂に関するアンケート調査」(有効回答は802人)や、新宗教も含めた教団への取材、さらには地域の拝み屋さん(霊能者)からの聞き取りなど、さまざまなアプローチがとられています。
僧侶へのアンケート調査については、宗派ごとの相違が際立っており、興味深いです。なかでも独特なのは、死者の霊魂の存在を、教義的に明確に否定している浄土真宗です。「あなたは「霊魂」の存在を信じますか」の問いに、「信じる」と回答した僧侶は、日蓮宗80%、真言宗75%、浄土宗62%、曹洞宗52%といずれも過半数を超えたのに対し、真宗僧侶は8%と、突出した低さです。
一方で、実際の現場で「供養」「鎮魂」「除霊」のような(霊魂の存在がたぶん前提となる)行為をしたことがあるかどうかについては、真宗僧侶も31%がイエスと回答しています。教義的な信仰と、現場での実践とのあいだに微妙なズレが生じているわけで、ますます興味深いです。
さらに、各宗教団体への取材結果を分析した部分では、「霊魂の存在を認める傾向が強い」か否かと、「宗教者に法力が備わると考える」か否かという、二つの指標に基づき、各教団をチャート化しています。このうち、どちらも肯定的なグループには、真言宗や日蓮宗など、密教や祈祷を重視する団体が入り、そしてその完全に対極の、いずれにも否定的なグループには、浄土真宗と創価学会がお隣どうしで並んでいます(この図、いろいろと面白いです)。
つまり、一口に現代日本の宗教者といっても、霊魂のとらえ方をめぐって、かなり多様な考え方があるということです。それは、上記したような大きめの教団に属する宗教者だけでなく、イタコなど、多くは個人営業している民間の宗教者の場合も同様です。たとえば、本書に登場するあるイタコさんは、死者の語りを取り次ぐ「口寄せ」について、「口寄せは日常の会話そのものだと思っています。生きている人も死んだ人も分け隔てなく語り合う。それが亡くなった人にとって、とてつもない喜びになる」と述べています。死者の存在を、生者と同じレベルでとらえているわけです。日本の宗教者の、一つの究極的なあり方でしょう。
こうした宗教者から見た死者・霊魂論のほかにも、現代の「空き家問題」の原因の一つに仏壇や神棚に宿る「魂」の処理問題があるとの指摘とか、あるいは「幽霊」の経験についての省察など、なかなか考えさせられる記述が盛りだくさんです。私たちの霊魂のゆくえを探る上での、示唆に満ちた一冊です。
②『葬式仏教の誕生: 中世の仏教革命』 松尾 剛次 著
[amazonjs asin=”4582856004″ locale=”JP” title=”葬式仏教の誕生-中世の仏教革命 (平凡社新書600)”]
日本ではなぜ、おもに仏教が葬式を担当しているのでしょうか? その歴史的背景を学ぶ上で、本書は今のところもっとも手軽な本かと思います。よりクラシカルで重要な本として、圭室諦成『葬式仏教』(大法輪閣、1963年)がありますが、ややとっつきにくいので、初学者はまず、こちらの新書から入るのが適当かと思います。
仏教伝来から後、日本では僧侶が葬式にかかわることが、ちょくちょくありました。しかし、そこまで密接な結びつきはありませんでした。というのも、地位の高い僧侶(官僧)たちが、死体から発せられる「穢れ」を嫌がったからです。死体の「穢れ」に感染したとされる僧侶は、しばらく謹慎した後でないと、寺院での重要な行事に参加することがゆるされなかったのです。これでは、葬式仏教など成立しそうもありません。
ところが、鎌倉時代のころから、仏教界での地位や対面よりも、自己や他者の救いを重んじる活動をしたいと願う僧侶(遁世僧)たちが出現します。そんな彼らが、宗教的なニーズが満たされていない人びとのために、葬儀や供養の実践に取り組みはじめます。たとえば、新しいかたちの法事を設計したり、迫力のある巨大板碑や五輪塔を造り上げるなどして、「穢れ」をものともしない、死者に対するケアのあり方を確立していくわけです。こうして、葬式仏教の基盤が形成されていきます。
こうした大転換を、本書の著者は「革命」だったと評します。日本の仏教は、もともと葬式のプロフェッショナルになる必然性はなかった。というより、日本的な「穢れ」の観念が、仏教と葬式を分断し続ける可能性もあった。しかし、死者のケアに仏教者のあるべき道を見出した、中世の僧侶たちがいた。彼らの仏教に対する強い信念が、葬式仏教という「仏教革命」を引き起こしたというわけです。
その「革命」の意義は、やがて江戸時代頃から葬式仏教が自明になっていくにつれ、見失われていきます。ある時期以降には、「葬式仏教」は日本仏教に対する批判的なレッテルにもなってしまいました。けれど、そのルーツをたどれば、そこには僧侶たちの仏教に対する真摯な問い直しの運動があった。そうした歴史を思い出すことは、現在の葬式仏教の価値を見直すことに、きっとつながってくるはずです。
③『葬儀業界の戦後史: 葬祭事業から見える死のリアリティ』 玉川 貴子 著
[amazonjs asin=”4787234331″ locale=”JP” title=”葬儀業界の戦後史 (名古屋学院大学総合研究所研究叢書)”]
現代日本では、死者のプロフェッショナルの筆頭にあげるべきは、葬儀業界で働く方々でしょう。仏教(僧侶)が日本の葬祭文化の中心にいたのは昔の話で、いまでは葬祭業界こそが第一、仏教は同じ死者のプロとはいえ、重要度は相対的に低いと思います。
こうした現状は、いかにしてもたらされたのでしょうか。それを、戦後の葬祭業界の変遷についての社会学的な研究を通して明らかにしているのが、本書です。とりわけ、葬祭業界が「人の不幸でお金をとる」商売として批判されてきたという経緯を重んじながら、しかしなお、日本人の生活のなかに定着し、活躍の場を拡げていく過程を検証していきます。
たとえば、昨今でも結婚式には多額の費用を投入してハッピーな気分になれる人びとが、葬式にお金がかかると不機嫌になる場合が少なくないです。同じ儀式でも、「幸福」と「不幸」で価値判断が大きく違うわけで、後者のお客さんを相手にする葬祭業者は、ときに批判や差別を被ってきました。
この種の批判は、同様に「人の不幸でお金をとる」ところのある、仏教界にも向けられてきました。とはいえ、批判の度合いが全然違いました。僧侶が、死者とかかわる伝統を背景とし、また「宗教者」という特別枠に入れられているのに対し、葬祭業者は、無防備なまま死者と向き合うビジネスに取り組まなければならなかったからです。
たとえば、1960年代から販売されるようになった、とても立派な祭壇の例です。これは、おもに都会で亡くなった人の最期を美しく飾る新しい文化の創造でしたが、当然いままでになかった費用がかかり、人の不幸に乗じた「営利目的の行為」として、ときに批判されてきました。戦後に政府主導で開始された、新生活運動による葬儀の簡素化の奨励も、葬祭業界による新サービス開発への疑念を強める要因となったようです。
しかし、戦後一貫して進んでいった地域社会の解体は、葬祭業の役割を、大きく拡大させていきます。1980年代には既に、葬儀の際の「僧侶、神官、牧師の紹介」や、「お布施についての助言」といった宗教的に大事な部分を、葬祭業者がサポートするようになっています。のみならず、「正しい葬儀のやり方とは何か?」をめぐるノウハウや基準が、地域社会や僧侶ではなく、葬祭業者のもとに集中していくようになります。
こうして次第に、私たちの暮らしに必要不可欠な存在になっていった葬祭業ですが、依然として反感を買いやすいことは変わりません。結果、業界ではさまざまな困難を抱えながらの経営拡大が目指されます。たとえば、1980年代以降に建設ラッシュが見られた葬儀会館については、地域社会に嫌がられないよう外観に配慮し、また商業主義と見なされないよう、パンフレット等で顧客の「心」が何より大事といったアピールがなされます。
そして、こうした困難さの重荷が最もダイレクトにのしかかってくるのが、現場の職員の方々です。身内が亡くなったという、多くは不服な思いのもとに業者と向き合う顧客に対し、彼らの心のケアをしながら同時に、会社の利益のためにも「商品」を売りつけないといけない。こうした感情の負担の大きいハードな仕事は、職員一人ひとりの利他的な感性を磨く一方、ある種のやりがい搾取ももたらしうる。なかなか難しい問題です。
いずれにせよ、さまざまな困難を抱えながらも葬祭業界の存在意義は一貫して大きくなってきており、近年では介護事業に参入する業者も出てきました。死者だけでなく、現代人の死にゆく過程も含め幅広くサポートする仕事になる可能性があるわけです。仏教を上回る、死者に向き合うプロとしての重要度が、今後ますます高まっていくのではないでしょうか。
④『日本鎮魂考: 歴史と民俗の現場から』 岩田 重則 著
[amazonjs asin=”4791770560″ locale=”JP” title=”日本鎮魂考 ―歴史と民俗の現場から―”]
死者の性格は、その人の生き方によって変わり、また死に方によっても変わります。平均寿命を超えて大往生を遂げた死者と、災害や事故や戦争によって若くして亡くなった死者とでは、性質が大きく異なります。その相違に応じて、弔いや鎮魂の文化も、多様に展開してきました。本書は、そうした死者の文化の多様性について、歴史資料の分析と日本各地のフィールドワークの成果を組み合わせ、じっくりと考えを深めています。
特にクローズアップされているのは、まずもって江戸時代の死者をめぐる文化です。先に、中世において葬式仏教の基盤が形成されたと述べましたが、一人ひとりの死者が「ホトケ」として丁寧に供養され、お墓などで祈念/記念されるようになるのは、江戸時代になってからです。あるいは、豊臣秀吉や徳川家康をはじめ、生前にグレートな業績を残して逝った人びとを「カミ」として崇める風習も、江戸時代から盛んになりはじめます。
このうち、特に後者の風習が全面的に展開されるようになるのが、近代です。戦死者を「英霊」としてカミ扱いするシステムが、近代の国家権力によって創造されていったからです。彼ら戦死者たちの霊は、当初、通常の死者とくらべて、兵士としての個性を際立たせるかたちで顕彰される場合が多かったようです。ところが、戦争の時代が長く続き、やがてあまりにも多くの戦死者が出てくるのにつれ、その個性は薄れていきました。戦死者という「異常死者」が、無個性的になるほど大量に発生した、「異常」な時代がちょっと前の日本にはあったわけです。
こうした「英霊」の大量発生は、各地の寺院のなかにもその影響を及ぼしていきます。寺院境内の「忠霊殿」に、「忠」または「忠義」といった文言を組み入れた戒名の位牌が、無数に安置されていったのです。総力戦のさなか、忖度の大好きな仏教界が国家を全面支援していた事実はよく知られますが、そうした国家と仏教の結託は、寺院における死者供養の文化のなかにも見られたというわけです。
いずれにせよ、これら大量の戦死者たちは、先の東日本大震災の犠牲者の一部と同じく、若くしてその生を中断された者たちです。そうした者たちについて、著者は折口信夫が発した「未完成の霊魂」という言葉によりながら、よくよく意識を向けることの意義を説きます。
たとえ天寿をまっとうした人間であっても、彼や彼女の人間関係のあり方によっては、容易に無縁の存在となり、さまよえる霊魂となりうる。そうであれば、手厚い供養の対象となり続ける「完成した霊魂」ではなく、「未完成の霊魂」の視点から死者について考え続けることが、今後の私たちにとっては大事なのではないか。「無縁社会」が指摘されたりもする昨今、これは、非常に意義深い提言ではないかと思います。
⑤『水子供養 商品としての儀式: 近代日本のジェンダー/セクシュアリティと宗教』 ヘレン・ハーデカー 著
[amazonjs asin=”4750345997″ locale=”JP” title=”水子供養 商品としての儀式――近代日本のジェンダー/セクシュアリティと宗教”]
1970年代、日本にかつて存在しなかった新しい宗教的風習ないしは儀礼が、急激に拡大し、全国各地に定着していきました。水子供養です。おもに霊能者たちがその必要性を語り出し、それを週刊誌などのメディアが大々的に宣伝したことで、寺院をはじめとする伝統宗教のなかでも、水子供養がたびたび行われるようになりました。
本書は、この新しい宗教文化が発生してくる歴史的・社会的背景をふまえた上で、それが日本の宗教史上、どのような意義をもっているのかを解明した本です。原著は1997年に英語で出版されており、部分的に少し古びた記述もありはします。しかし、水子供養という戦後に発明された死者儀礼の実態について、ここまで鋭く分析した著作は、ほかにないと思います。
日本の伝統的な信仰のなかに、中絶された胎児が祟りとかをもたらすので、供養しないといけない、といった発想は、ほとんどありませんでした。お地蔵さんが子どもを守護してくれるという考え方は、近代以前からかなり広まっていましたが、祟る胎児のために女性が地蔵にすがるような行動は、ほぼなかったわけです。
ところが戦後になると、「水子」が主体的に生者に害を及ぼすという信念が、生み出されます。一つの要因として、胎児写真の普及により、女性とお腹のなかの子どもの一体感が必ずしも自明でなくなり、胎児の自律性が高まったことがあります。そこに、戦後の「優生保護法」や産児制限の政策による、妊娠中絶経験者の激増があわさって、祟る胎児というイメージが、リアルに受けとめられやすい状況ができあがりました。
こうした文脈のもと、霊能者や、商売気の強い宗教者たちが、水子供養のススメを説くようになります。祟る胎児を供養せよという、センセーショナルなメッセージは、同時代のオカルト・ブームの後押しも受けて、週刊誌の恰好のネタになります。雑誌には、霊能者による水子供養の種類や料金表が掲載され、これらの情報に触れて「水子」の存在を思い描くようになった女性たちは、水子供養の消費者になっていきました。
水子供養のニーズは、やがて寺院に対しても向けられるようになります。僧侶は死者儀礼のプロなのだから、水子供養もできるに違いないという連想です。戦後の「新商品」である水子供養は、もちろん経典には書かれていないし、特に霊魂とか祟りといった発想をとらない浄土真宗を中心に、否定的な態度をとる僧侶が大半でした。しかし、供養を求める檀家や地域住民の願いを一刀両断するのも何なので、受け身的に「水子供養」してきた寺院も、少なからずありました。
死者をめぐる仏教的な文化が生まれるとはどういうことか、実に考えさせられる事態です。しかも、この供養文化は仏教のみならず、神道や修験道や新宗教のなかにも浸透していくのです。宗教や宗派を超えて普及したということは、やはり戦後の日本人の宗教的な感性に、強くうったえかけるところがあったからでしょう。
現在でも、水子供養は日本のあちこちで行われており、のみならず、台湾や韓国などにも伝播しています。かなり商業主義的な流れから生まれ広まった風習とはいえ、現代人の死者観の多様性や、その仏教とのかかわり方を理解する上で、依然として重要な文化としてあり続けているのかと思います。
以上、日本の死者を扱った本を、できるだけ幅広いジャンルからピックアップして紹介してみました。死者とは何か、とりわけ仏教にとって死者とは何かを考えるためには、歴史学、民俗学、宗教学、社会学など、さまざまなアプローチからの検討が必要なことが、わかってくるかと思います。死者とその文化について考えた本は、もちろん生者について考えた本にくらべればずっと少ないですが、それでも、けっこう多種多様にあるわけです。
そして、日本ではその死者の文化の中心に、これまで仏教がありました。今後もあり続けるかどうか、それは不透明なところがあります。けれど、もし仏教が死者とかかわり続ける必要があると信じるのであれば、その信念を豊かにするための知識を、今回取り上げたような本から得るのもよいかと思います。