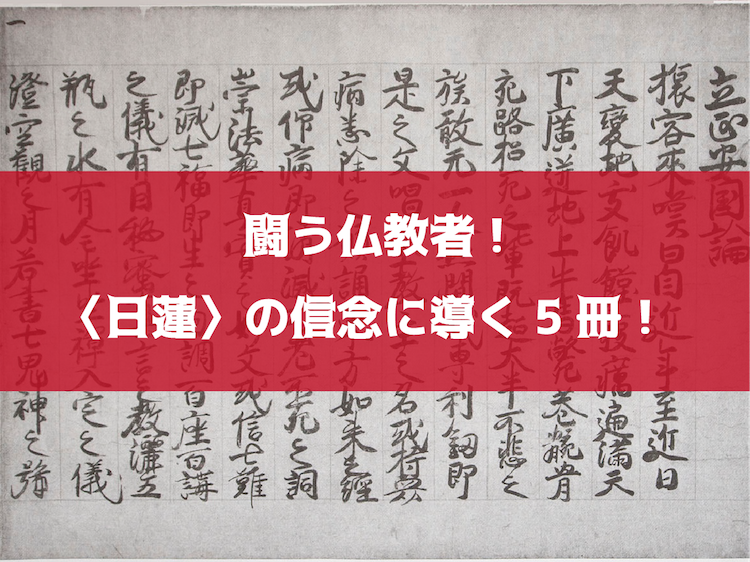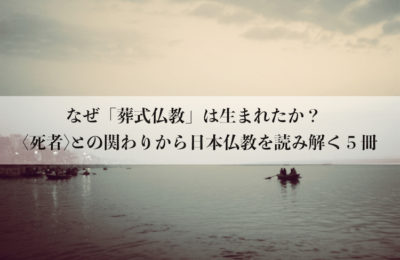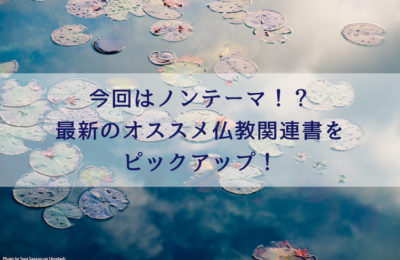今回は日蓮です。アクティビスト感の強い方ですね。場合によっては攻撃的ですらある。真言・禅・念仏・律、これら他宗派へのヘイトである「四箇格言(しかかくげん)」は、わりとよく知られているでしょう。
そのため、空気と忖度の国の仏教界では、しばしば敬遠されがちです。けれど、宗教とは本来、攻撃的なところのあるものです。ある宗教が普及するには、どこかに「攻め」の姿勢がないといけないからです。
そういった意味では、日本仏教のなかで最も「宗教っぽい」仏教者が、日蓮であると言えるかも知れません。宗教としての仏教とは何か? ここに紹介する日蓮に関する複数の本に導かれながら、少し考えてみたいと思います。
①『日蓮:われ日本の柱とならむ』 佐藤 弘夫 著
日蓮の生涯と思想について、きちんとした研究をふまえ、かなりバランスよく記述している本です。特に著者の専門である思想史的な説明がわかりやすく、文章も精彩に富んでいて、日蓮の仏教にかけるパッションと、現実の政治や社会に対するクールな認識が、よく理解できます。
鮮やかな論述から学ばされる点は多いですが、やはり、日蓮が法華経(題目)にひたすら一途な宗教者として自己確立していく過程が、興味深く読めます。そこに、日蓮という人間の個性が、よくあらわれているように思うからです。
日蓮は、法然の専修念仏への苛烈な批判者として頭角を現します。その批判の当初の理由は、すべての宗派を尊重する融和主義の立場から、法然の思想の排他性を疑問視したことにありました。仏教にはいろいろなスタイルがあるのに、「念仏のみ」はおかしいだろう、というスタンスです。
これは当時の仏教界では常識的な考えで、逆に法然(や親鸞)は非常識なので、ときに白眼視され、遂には弾圧を被ったわけです。よって初期の日蓮は、ふるまいは攻撃的ではあれ、思想的には体制側の人間だったわけです。
ところが、法然の念仏が次第にファンを増やし、また弟子筋のなかには「念仏のみ」の立場を放棄して、他宗派との共存をめざす融和主義を採用する者も増えていきます。かくして、念仏はますます支持を集めますが、これに納得いかなかったのが日蓮です。
念仏は、存在するに値しない「悪義」である。念仏のせいで今の世の中はろくでもない状況になっている。日蓮はそう批判し続けます。しかし、念仏の人たちはすでに他宗派との共存を重んじているので、それを批判するのは、当時の常識である融和主義からの逸脱となりました。
やがて、日蓮は念仏のみならず、真言も禅も律も批判するようになります。「法華のみ」となるわけです。法然の「念仏のみ」批判からスタートした日蓮は、その批判的な活動の果てに、遂にはかつての法然がいたような位置に自らを置くに至ったのです。「ミイラ取りがミイラに」的な何かとも言えますが、そこに自己の信念をラディカルに突き詰めた偉大な宗教家たちの、魂の継承を見て取ることもできるでしょう。
法華経(題目)の原理主義者と化した日蓮の、揺るがぬ姿勢はすごいです。かつての師僧が久しぶりに訪ねてきて、自分はいま念仏にハマっていて阿弥陀仏の仏像を5つも造ってしまったのだが、これだと救われないかな? と日蓮に質問したところ、日蓮は「阿弥陀仏を五体作ったからには、五度無間地獄に堕ちられることになるでしょう」とキッパリ回答します。かつてお世話になった師に対するこの配慮の無さは、ある意味すがすがしいです。
日蓮はこのように強固な宗教的信念に生きた人ですが、一方で政治的な判断は冷静でした。どれだけ正しい教えも、ときの権力のバックアップがなければ広まらないと認識しており、ロビー活動に積極的だったのは周知の事実でしょう。
そして、日蓮が政治権力との結託を重視したのは、宗教は個人の内面的な自己満足にとどまっていては意味がない、と確信していたからです。いま目の前にあるこの世界に、仏法が貫徹した理想社会(仏国土)を実現し、その社会で生きるすべての人間が、悩み苦しみのないリア充になるべきだ。そう信じた日蓮は、宗教の普及と国家の事業は不即不離と理解したのです。
このような宗教による現実社会(政治)への介入は、現代日本ではあまり好まれません。けれど、そもそも世の中を変える力のない宗教に未来はあるのでしょうか? 日蓮とともに、改めて考えてみるに値する問いかと思います。
②『日蓮:殉教の如来使』 田村 芳朗 著
戦後の日本仏教研究に多大な影響を及ぼし、自身も法華宗の僧侶であった仏教学者による、日蓮論です。1975年に刊行された本(の再刊)ですが、日蓮をどう捉えるかに関し、いまだ新鮮な知見を与えてくれる名著です。
サブタイトルに「殉教の如来使」とあるとおり、日蓮の「殉教者」「(釈迦如来の)使徒」としてのイメージを際立たせた描き方をしています。そのため、「殉教」や「使徒」を重視する、ほかのある宗教との類似性がしばしば指摘されます。もちろん、キリスト教です。
一般に、キリスト教と似ていると言われがちなのは、親鸞(浄土真宗)です。どちらも、唯一の神/仏(阿弥陀如来)への信仰を大事にし、他力的な性格が色濃いからでしょう。けれど、予言宗教・殉教精神・使徒意識などの諸要素から見た場合、むしろ日蓮のほうにキリスト教と通じるところがないか、と著者は述べます。
確かに、法華経の教えを広めるため攻めの布教を繰り返し、そのせいで迫害され、処刑されそうにもなった(が、奇跡が起きて助かった)日蓮の人生は、イエス・キリストを思い起こさせる部分があります(イエスのほうはもちろん処刑されてしまってますが)。神の国の到来を語るイエスと、蒙古襲来を予言する日蓮の口ぶりには、共通性がありそうです。
きわめつけは、『法華経』には仏天の加護と安穏な暮らしが説かれているにもかかわらず、なんで自分は迫害されまくってるのかと疑問に思う、日蓮の苦悩です。著者は、そこに十字架上のイエスの「わが神、わが神、なんぞ我を見棄て給ひし」という叫びを重ねあわせます。ほんと、似てますね。
実際、戦前にも日蓮に共感するキリスト者はいて、たとえば内村鑑三です。著書『代表的日本人』で、仏教者ては日蓮を取り上げ、その「単独、世に抗す」姿を称賛してます。内村もまた、自らの一途な信仰のために、周囲から迫害された経験がありました。たとえ「単独」でも神のために頑張ろうとした、立派なキリスト者です。
日蓮には、キリスト教に通じる何かが強くある。キリスト教徒が全人口の1%どまりで、世界的に見ても広まりにくいこの国で、日蓮がときに敬遠されるのには、あるいは必然的な理由があるのかもしれません。
③『戦国仏教:中世社会と日蓮宗』 湯浅 治久 著
法然、親鸞、道元、日蓮らの仏教は、一般に「鎌倉新仏教」と評されます。鎌倉時代に生まれた、新しいタイプの仏教だからです。しかし、この時代には彼らの教えはメインストリームにはならず、より昔から続いている宗派(奈良の諸宗派や、天台宗や真言宗)のほうが力を持っていました。
「鎌倉新仏教」の諸宗派がプレゼンスを拡大するのは、戦国時代になってからです。よって、これらの宗派は「戦国仏教」と理解したらどうだろう、という考えが、一部の歴史学者のなかにあります。本書は、この考え方をベースにして、日蓮の没後、彼の教えがいかに広がり定着したのかを明らかにします。
まず注目すべきは、日蓮の門弟の分裂です。「法華のみ」を通した日蓮でしたが、その弟子のなかには、あるいは勢力を拡大するため、あるいは迫害を回避するために、法華経とは直接関係のない神々に祈りを捧げたり、他宗派と合同の儀式を執り行ったりする僧侶が出てきます。こうした妥協を是とするか否かで、門弟の立場が別れていくわけです。
いま「妥協」と述べましたが、「法華のみ」を諦めた弟子も、ただの体制迎合主義者だったとは言えません。兵乱や飢饉が世を覆うなか、人々をその悲惨さから救うため、神々に祈ったりしていたわけです。原理主義者の日蓮であれば、おそらくこうした態度を批判したでしょうが、まあ、弟子たちの真摯な願いも察することができます。
いずれにせよ、こうした妥協もともないながら、日蓮門下の勢力は徐々に拡大します。そして戦国時代に入り、有力な武士のもとに一揆が形成される際、日蓮宗その他の新興仏教の教えや儀式が、集団をつなぐための媒介として役立つことになります。
さらに、政情不安定な時代のなか、戦没のみならず餓死による死者が大量発生し、人々の葬儀や供養へのニーズが著しく高まります。こうした危機の時代のニーズに応えられた、日蓮宗などの新勢力は、従来からあった村落のお堂を自宗の施設として転用し、あるいは旧来の信仰集団(講)も取り込むことで、「戦国仏教」として社会に定着していくのです。
このように、日蓮宗などの「鎌倉新仏教」が、現代日本にも一定の影響力を持つに至った背景には、開祖の後継者たちの現実との妥協や、戦乱の時代に生じた数多くの暴力や死の世界があったわけです。宗教は、その教えの真理性だけではなく、社会状況への適応性にも左右されながら普及するという事実が、歴史を学ぶとよくわかってきます。
④『近現代日本の法華運動』 西山 茂 著
日蓮の教えは、近代以降に新たな生命を与えられ、大きなムーブメントを起こします。代表的な運動が、日蓮主義と、法華系の在家教団(僧侶ではなく在家信徒が中心の宗教団体)の二つです。本書は、それらの運動の実態について、長年にわたり調査・研究してきた著者による、集大成的な一冊です。
日蓮主義は、田中智学という人が主導した仏教運動です。軍人の石原莞爾や作家の宮沢賢治も、この日蓮主義の信奉者でした。明治の後半から大正期にかけて隆盛していきますが、日蓮の思想を現代に甦らせようというのが基本的な趣旨です。そのため、田中智学とその影響下にあった人々は、日蓮と同じく、宗教と国家・社会との関係に、かなりこだわってました。
彼らは、日本という国は日蓮仏教の教えで教化/強化されないと、「ただの日本」に過ぎず不十分だと考えます。よって、日本の中心である天皇が法華経に帰依し、全国民もそれにならい、政治と宗教が完全に一致した「あるべき日本」を達成すべきと説きます。そして、そのパーフェクトな日本が、やがて世界を統一すると信じました。
ところが、そんな「あるべき日本」はなかなかやって来ないし、日本が抱える数々の問題もぜんぜん解決されない。その理想と現実のズレに悩んだ日蓮主義の使徒のなかには、たとえば井上日召のように、テロを起こして急進的な社会変革を目指す者すら出てきます。
あるいは、石原莞爾は関東大震災の発生にショックを受けて、日本が世界を統一するための「世界最終戦争」が迫っているんじゃないか!? という強迫観念にとらわれたりします。普通に考えると妄想にしか思えませんが、しかしこの予言宗教感は、日蓮の教えには忠実とも言えます。
一方、法華系の在家教団としては、やはり戦後に大躍進する創価学会が有名でしょう。同会の二代目の会長である戸田城聖は、日本の敗戦や、隣国での朝鮮戦争の勃発をふまえ、これは皆が(法華経の)正しい仏法を信じないから起きた惨事だと述べます。「邪宗教、低級仏教によって、仏の真言にそむく仏罰である」とのことです。20世紀にも、日蓮流の批判精神は確かに生きていたわけです。
また、正しい仏法の広まりによって現世がハッピー・ワールドになるという日蓮流の構想も、創価学会に着実に受け継がれています。再び戸田の発言を引けば、「御本尊様は功徳聚である。御本尊を信じ、自行化他の題目に励むことによって、病人は健康体に、貧乏人は金持ちに、バカは利口になる」ようです。これは、たぶん多くの人々が望む世界ではないでしょうか。
かくして、日蓮の夢は中世社会で途絶せず、明治以降の近現代、そしておそらくは今もなお、確かに引き継がれているのです。そして、その影響力はこれまで決して小さくなかったし、今後もおそらく続いていくのでしょう。
⑤『日蓮』 山岡 荘八 著
最後に、小説を一つ取り上げたいと思います。作者の山岡荘八は、徳川家康ら日本史上の超有名人についての大河小説の数々で名をはせた人物です。日蓮を題材にした本作(原著、1952年)は1巻だけで、この著者としては短く、日蓮の半生しか描かれてません。また、史実からほど遠い記述も多々あります。
とはいえ、日蓮が目指したのものは何だったのかを、ざっくりとつかむのに、十分に優れた作品だと思います。とにかく、文章が素晴らしい。日蓮がそこに生きたであろう世界が、想像力豊かに、美しく明晰な文章で構築されており、読んでいて退屈しません。
若き日蓮が寺院(仏教)に入った理由は、現在の通説では、学問するため、となっています。法然や道元が経験したような身内の不幸は、子どもの頃の日蓮にはありませんでした。むしろ、優秀だけど社会階層が低めの家の子が入寺して勉強するという、中世社会に一般的な慣行に、日蓮も従っただけ、というわけです。
しかし、この小説では、無常な世の中で愚かに行動する人間への諦観からの出家、というストーリー展開です。目前で繰り広げられる、色恋や家族関係をめぐる誤解やすれ違いや刃傷沙汰の果てに、少年日蓮は、人間の知恵のはかなさを痛感します。「めいめいがめいめいの描いたまぼろしに向かって、白刃をかざし、息を切って駆けている」のは、何たる不幸かと。そこで、こうした無明の世界を超えるための、たった一つの「真実」を求めて、彼はやがて発心するに至ります。
こうして仏教を学びはじめた日蓮ですが、それぞれ矛盾しあういろいろな宗派の教え、とりわけ既存の仏教のあり方を根底からひっくり返す、法然の浄土教の台頭に戸惑います。いったい、「どれがほんとうの釈尊の宗旨なのか?」あるいは、「釈尊は何宗であろうか」と。
彼の疑問に対し、先輩僧侶は「釈尊の宗旨は・・・・・・八宗十宗。みな寄せたものであろうよ」と答えます。しかし、その程度の「みんなちがって、みんないい」的な腰の据わらない回答が、一途な日蓮に通用するはずがありません。「そんな答えならば聞くまでもない」とがっかりして、彼は彼の真理を探す旅に出ます。
結果、日蓮がたどり着いた「釈尊の正意」は、何であったか。次のように語られます。
小さな自己保全、小さな所有の慾念から解放されて、宇宙も生物もすべてをふくめて一つの生命体であることに気づけという点にある。人のために物質があるのでもなく物質のために人があるのでもない。それに気づかず、人が人の支配をのぞみ、人が物を支配しようとしてゆくところに争いの種は無限に根を張り、人間には永遠に自由はないと叫んでいる/人と物とを二元に考える・・・・・・この錯倒した思想をそのままおしすすめると、やがて物が人を支配し、財物が人を殺すという人間否定の悲劇文明が生まれて来る。
これが釈迦の「正意」かどうかは微妙ですが、なかなか妥当性の高そうな思想であるとは思います。現代日本で「財物」に支配されていない人なんかほとんどいませんもんね、自戒を込めて書いてますが(笑)
以上、日蓮でした。冒頭に述べたとおり、宗教っぽい仏教者ですね。トラブルや抵抗をものともせず、自らの超越的な信念とともに進撃していく。あるいは、現状を徹底的に批判しながら、しかし、この世界に理想世界をもたらそうとして奮闘する。生き生きとした宗教運動らしい性格が、日蓮と、その影響を受けた人々の活動にはよくあらわれています。
そういう意味では、現代の伝統仏教の大勢は、あまり宗教っぽくないのでしょう。その落ち着きぶりを肯定するか、あるいは宗教としての無力さを反省するか。日蓮に関する本からは、多くの示唆が得られます。