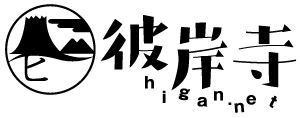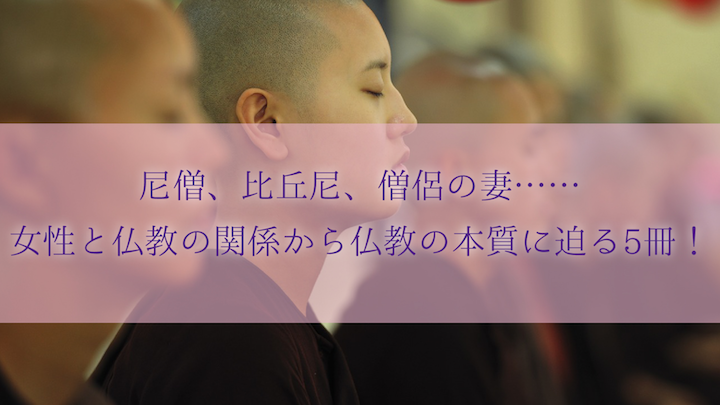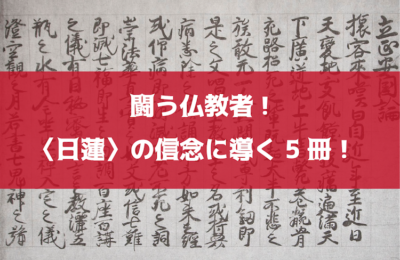今回のテーマは、「仏教と女性」の関係です。人類には大きく分けて二つの性別があるわけですが(実際にはもっと複雑ですが、ここではひとまずざっくりと)、このうち、女性は仏教とどうかかわってきたのか、あるいは、どうかかわっているのか、という問いについて考える上で参考になる本を、ご紹介していきたいと思います。
仏教と女性といえば、まずは尼僧が重要になるでしょう。尼僧こそが、女性として生まれ仏教を伝えてきた人びとの、代表格です。とはいえ、もちろん尼僧以外にも、仏教と深くかかわってきた女性たちは、少なくないです。ということで、特に尼僧に注目しながらも、もう少し広い視野から、仏教と女性に関する「これは」と思える書物をピックアップしていきましょう。
①『テーリー・ガーター: 尼僧たちのいのちの讃歌』 植木 雅俊 著
最初期の経典のひとつであり、古代インドの尼僧たちの心模様を描いた詩集、『テーリー・ガーター』。中村元の訳による『尼僧の告白』(岩波文庫)が定番ですが、中村のお弟子さんである著者が、改めて現代語訳し、詳しい解説を付したのが、この本です。
登場するのは、友人がおらず孤独に悩む女性や、子どもを亡くして悲しみのどん底にいる女性や、異性にモテすぎて慢心している女性などです。彼女たちが、釈迦の教えを受け入れ、心を改めたことで、苦しみや欲望まみれの生活から解放され、真の安らぎを得られた喜びを、赤裸々に語っています。
なかには、女性蔑視の風潮が強いヒンドゥー教の社会のなかで、ある尼僧さんがヒンドゥー教のハイクラスの男性修行者を説き伏せ、見事、仏教徒に改宗させたエピソードなども含まれています。これは世界の宗教史上でも、画期的なことではなかったかと、著者は指摘しています。確かにそうでしょう。
こうした男女差別を超える思想をはっきりと持っていたのが、釈迦にほかなりませんでした。彼は男性だけでなく、女性たちにも同等に「いらっしゃい」と声をかけ、出家者として快く受け入れていたようです。人間は生まれによって差別すべきではなく、その行いによって評価すべきとか、差別はそもそも人間の言葉が生み出した思い込みでしかないとか、現代でもパーフェクトに妥当そうな意見を述べていたわけです。さすが。
なお、釈迦は女性の出家に際して、男性には要求されない「八つの条件」(八敬法)を課したとされています。それは、明らかに男性僧侶の優位を規定した趣旨のもので、なぜ平等主義者のはずの釈迦が、そのようなルールを設けたのかについては、いろいろと議論されてきました。
この問題について、著者は、これは釈迦が定めた方針ではなく、後世に教団の運営にあたっていた残念な男性僧侶が、釈迦の教えをわきまえず、勝手に加えたものだろう、と見ています。当方にはその見解の真偽を判断する能力はありませんが、まあ、十二分にありそうな話だと思います。
いずれにせよ、本書は仏教と女性の関係を、そのルーツにさかのぼって平明に語ってくれる良書といえます。
②『日本史の中の女性と仏教』 吉田 一彦・勝浦 令子・西口 順子 著
日本の古代から中世にかけての仏教と女性の歴史について学ぶのに、とても参考になる一冊です。1997年に寺院のホールを会場に、市民講座として行われた連続講義に基づく内容で、総じてわかりやすいです。日本史が好きな方であれば、確実に面白く読めると思います。
仏教が日本に入ってからしばらくのあいだは、男女がおおむね平等に仏教にかかわっていたようです。男性僧侶も尼僧も、それぞれの寺院/尼寺で修行や学問をし、国家的な儀式に参加していたとのこと。出家者だけでなく、一般庶民も男女を問わず、仏教を熱心に信仰していたようで、それは『日本霊異記』に記されたさまざまな物語から、よく見えてきます。
こうした状況は、しかし、時とともに次第にバランスを崩していき、男性僧侶だけが公の舞台で活躍するようになっていきます。尼僧たちの地位が、目に見えて下落していくわけです。あるいは、かつては男性僧侶の寺院と尼寺がセットで建立されていたのに(たとえば奈良の東大寺と法華寺)、男性僧侶の寺院だけがソロで建てられたりするようにもなりました。
にもかかわらず、出家する女性の数自体は減らなかったどころか、むしろ増えていったようです。彼女たちは、国家権力の中心的な場からは疎外されながらも、その周辺や、あるいは一般庶民のために、宗教者として活躍するようになりました。そうした彼女たちの社会的位置づけの実態についても、本書は詳しいです。
また、日本史における仏教と女性といえば、やはり、日本を代表する妻帯僧である親鸞が導いた、浄土真宗について考えなくてはいけません。そして、本書にはきちんと、「真宗史のなかの女性」について語られている章があります。仏教史における女性の位置についての入門書として、とにかくオススメできます。
③『プロの尼さん:落語家・まるこの仏道修行』 露の団姫 著
現役の尼僧かつ、落語家という、スペシャルな二足のわらじを履いた著者の半生記です。14歳にして「死んだらどうなる?」「普通って何?」「差別をなくすには?」という巨大な疑問を抱えた著者が、その後、仏教と落語に夢中になって、やがて双方の道を究めるため精進するようになっていく過程が、ユーモラスに語られています。
著者が選んだ仏教は、特に法華経の教えです。法華経に出会ったことで、それまで「着ぐるみ」のようであった自分のなかに、はじめて生きた「人」が入ったように思うという話が、なかなかグッときます。「法華経が無かったら、自殺していたかもしれません」という告白は、もし仏教がなければ死んでいたはずの読者であれば、誰もが共感できるでしょう。
こうして、法華経の教えを広めたいと願うようになった彼女は、天台宗の僧侶になることを決意します。日蓮宗も選択肢として考えたそうですが、念仏にも心引かれるところがあったため、法華経の題目と阿弥陀如来への念仏の両方ができる、天台宗を選んだとのこと。そのいわゆる「朝題目、夕念仏」の実践を、「頑張る自分」と「お任せする自分」のハイブリッドとしてとらえているあたり、非常に興味深く読みました。
そして、実際に尼僧として活動しはじめると、「女の人が出家して丸坊主にしている」という姿を見ただけで、宗教的な感銘を受ける人びとに多く出会ったり、「尼さん=瀬戸内寂聴さん」というイメージが日本ではあまりに強力なのに、だいぶ戸惑ったりしたそうです。この辺は、現代日本における尼僧の位置づけを理解する上で、実に示唆深いです。
それから面白いのが、著者が弟子入りした落語家の師匠がクリスチャンで、また、著者の結婚相手も(師匠とは関係なく)クリスチャンという、妙なめぐり合わせです。仏教を固く信じながら、師匠を尊敬し、夫を愛する彼女ゆえ、そこから一種の「宗教間対話」が生まれてくるのですが、この辺の記述もすごく刺激的でした。
④『ミャンマーの女性修行者ティーラシン:出家と在家のはざまを生きる人々』 飯國有佳子 著
現代のミャンマーには、尼僧のようだけれども、いわゆる比丘尼(女性の出家者)ではない、「ティーラシン」という女性修行者がいます。ミャンマー全土に、4万人を超えるティーラシンと、約3000ヶ所の尼僧院が存在するらしいです。そのティーラシンの日々の暮らしと、彼女たちの修行生活をとりまく社会的な制度について、現地調査にもとづきコンパクトに論じたのが本書です。
ティーラシンは、剃髪して、戒律をちゃんと護り、瞑想やパーリ語経典の学習を、ものすごく熱心に行っています。日本の「出家者」とは大違いだといってよいでしょう。にもかかわらず、比丘尼として自律することはできず、男性僧侶に付き従いながら、「熱心な在家信徒」の立場に置かれ続けています。
彼女たちが、なぜ比丘尼になれないのかといえば、スリランカや東南アジアの上座部仏教の社会で、比丘尼のサンガが解体されてしまったという、歴史的な経緯があります。正式な授戒を行えるサンガが存在しない以上、尼僧として修行生活していても、仏教社会では比丘尼としては認められないわけです。そのため現在、上座部仏教の正式な僧侶は、全員が男性ということになります(東アジアの大乗仏教の場合は違いますが)。
こうしたなか、出家の世界における男女平等を目指す、比丘尼サンガの復興運動が、国際的にわき起こってきました。1980年代半ば頃から、現在に至るまで、上座部仏教の伝統を継ぐアジアの各地で行われています。西洋的なフェミニズムの影響が強いこのグローバルな運動ですが、おおむね各国の社会の保守的なサンガの抵抗にあい、あまり順調には進んでません。
そして、本書の知見として何より重要なのは、この問題の当事者に最も近いはずのティーラシンもまた、比丘尼サンガの復興運動に対し、否定的であるということです。というのも、彼女たちはこれまで、男性僧侶のサンガとの緊密な関係を結びつつ、在家信徒からの喜捨(布施)によって、生計を成り立たせてきたからです。比丘尼サンガを自立させることは、この暮らしの構造を脅かしかねない。ゆえに、復興運動に対する女性修行者たちからの反発も大きいわけです。
ということで、彼女たちはイヤイヤ「熱心な在家信徒」の立場に甘んじているのではなく、積極的に出家と在家のはざまを生きているのです。そこには、女性仏教者として確かなプライドを見て取ることができますが、一方で、仏教界に存在する古臭い男女差別を、うまく撤廃することの困難さも感じさせられます。
本書が検討しているのは、あくまでもミャンマーのケースですが、日本の仏教の現状について反省するのにも、きっと役に立つはずです。
⑤『妻帯仏教の民族誌:ジェンダー宗教学からのアプローチ』 川橋範子 著
「妻帯仏教」。日本仏教の一つの性格を、端的にあらわした言葉です。日本は世界仏教史のうえでもかなり例外的に、僧侶が結婚して家庭を築くのが、ほぼ当たり前の社会になっています。こうした風習が受け入れられているのは、ほかにはネパールの仏教界など、ごく一部です。本書は、その妻帯仏教の視点から、日本仏教の現状を批判的に考察しています。
僧侶が結婚することの、何が問題なのでしょうか? 釈迦が創始した仏教の根幹の一つである戒律を、完全にぶち壊しているというのが、究極の問題ですが、いささか理念的過ぎる話かも知れません。より具体的なレベルでは、僧侶の妻という、女性をめぐる問題があります。「出家」しているはずの僧侶の結婚相手という、通常の論理を用いては説明できない存在をめぐって、いろいろな問題が起こりやすいのです。
一昔前には、僧侶が亡くなると、その妻が寺院から追い出されてしまう、なんてことがけっこうあったようです。浄土真宗を除いては、どの宗派もタテマエとして「出家」の教団ということになっているため、僧侶の妻の立場が危うかったわけです。今日では、現実に妥協して僧侶の妻に対するさまざまな保障がなされています。それでも、「出家」の理念は依然として護持されているため、僧侶の妻の位置づけは、相変わらずデリケートな問題となっています。
こうした仏教界の女性をめぐる問題を、深刻にとらえている本書の著者は、仏教界の体制変革のための運動に自ら参入しつつ、その経験を、学問的にも鋭く分析しています。僧侶の妻だけでなく、尼僧や女性信徒など、仏教界にかかわる女性たちには、それぞれの苦しみがあり、それぞれの救いがあり、それぞれの可能性を持っている。彼女たちが仏教徒や僧侶として生きやすい環境を、どう創り上げていったらよいのか。著者は、きわめて真摯に問うています。
本書は、ジェンダー研究の知見を取り入れた宗教学の専門書でもあるため、多少、難しい内容の本ではあります。とはいえ、決して読みにくい本ではないです。それは、本人も僧侶の妻であり、仏教と女性との関係を当事者の目線から深く問うている著者のパッションが、本書の文章に、生き生きとした魅力を与えているからでしょう。
以上、仏教と女性というテーマに関する本について語ってみました。①の本で示されているように、仏教は本来、人間社会に存在するありとあらゆる差別を、人類の妄念が生み出したナンセンスとして否定する宗教です。ところが、歴史のなかで仏教の教義や組織には、性差別的な発想がじゃんじゃん採用されてきました。
現代日本でもなお、女性差別的な思考が身についてしまっている男性僧侶とかも少なくないです。そういう人たちを見ていると、今すぐ爆死してくれないかなと思うことが、ときどきあります(比ゆ的な意味で)。
そんな現状を遠目で見つつ、二つの性に分かれがちな人間にとって、仏教とは何か、そういう本質的な問題について考えていくため、上記の本などを、是非、手に取っていただきたいなと思います。