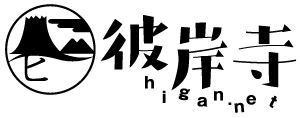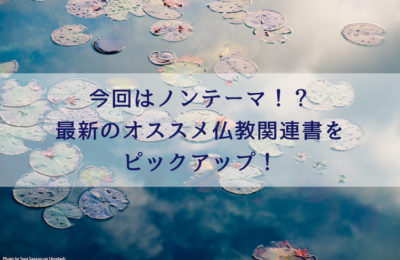今回のテーマは「仏教と哲学」です。昨今、お寺を会場にした哲学の勉強会やトークイベントが、しばしば開催されているようです。おそらく、仏教と哲学の近さが意識されているからでしょう。
どう近いのでしょうか? 人間や世界の本質について、じっくりと考える点で近いのです。もっとも、哲学の目的が、その考えを徹底して突き詰めていく点にあるのに対し、仏教の場合は、あくまでもその考えが「覚り」や「救い」の役に立つか、といった点にあるのは、大きな違いかとも思います。
とはいえ、人類がこの地球上で行っている実に多様な営みのなかでは、両者はまるで「家族」のように類似した活動であると言えます。そして、その類似性について自覚的な人たちの書く本は、仏教がこれまで蓄積してきた、「じっくり考える」テクニックの現代的な可能性を、鮮やかに示してくれています。そうした本を、いくつかご紹介させていただきます。
①『超越と実存: 「無常」をめぐる仏教史』 南 直哉 著
[amazonjs asin=”4103021322″ locale=”JP” title=”超越と実存 「無常」をめぐる仏教史”]
現代における「考える僧侶」の代表のような著者の、最新作です。まず、世界の思想には、仏教と仏教以外しかない、という大胆な断定からはじまります。すなわち、ただただ人間の「実存」のありようの考察に徹する仏教と、「実存」に加え何らかの「超越」を設定する仏教以外の思想ということです。
仏教において「実存」は、「無常」「無我」「縁起」等の観点から、その実体性を否定すべきものとして理解されます。実体がないのにもかかわらず、「自己」にこだわることで、人は苦しむというのが基本的な了解です。ところが、その仏教も長い歴史のなかで、「仏性」や「本覚」や「浄土」や、なんちゃら如来などの「超越」的な実体を、自らの思想のなかに取り込んできました。
これら、仏教のオリジナリティを薄める「超越」は、いかなる思想的意味を持っているのか。この重大な問いに対する、批判的な探究の作業を、インドの釈迦から中国仏教をへて日本の鎌倉仏教まで、仏教史を大づかみに振り返りながら試みたのが、本書です。
インドの大乗仏教は、竜樹などを除いて、おおむね仏教の思想に「超越」性を加えてきました。中国の禅や浄土教で、この傾向がますますはっきりします。日本では、もともと「ありのまま」の思想が大好きなところに、最澄や空海が持ち込んだ密教によって、その「ありのまま」自体が「超越」性を獲得してしまいます。法然は、そこに一神教的な「超越」の思想を導入し、日本仏教史上の「革命」を起こしますが、そのラディカルさは後世にはうまく受け継がれませんでした。
こうした見取り図のもと、著者はしかし、親鸞と道元に、「超越」とも「ありのまま」とも異なる、仏教の本来的な思想の、日本的展開を見て取ります。超越性とつながらない「無意味」な念仏をただ唱えるという境地に達した親鸞と、「仏」は行為のなかにしか存在しないとして、「成仏」を修行のなかに解体した道元。この両者の思想は、形而上学ではなく、形而「外」学であると著者は指摘します。このあたりがおそらく、本書のクライマックスでしょう。
なお、四半世紀ほど前に、一部の仏教学者が「批判仏教」という、本書と似たような作業を既に行っています。ただし、本書はそうした学問的な議論とは異なり、あくまでも著者個人の「実存」的な問いに基づく、思想の冒険といった感触です。既存の学問的なルールにはこだわらず、仏教の核心とは何かを、自前の概念を用いてとらえようとする。その試みは、本書の帯にあるとおり、まさに「仏教史の哲学」と言えるでしょう。
②『入門 哲学としての仏教』 竹村 牧男 著
[amazonjs asin=”4062879883″ locale=”JP” title=”入門 哲学としての仏教 (講談社現代新書)”]
哲学は西洋発の学問で、仏教は「東洋思想」ではあれ、哲学ではないという考えが、わりとあると思います。本書は、そうした発想を強く否定し、仏教を哲学としてとらえます。そして、そこに西洋哲学の議論と対等に渡り合える、どころか、西洋のそれを超えた哲学のあり方を読み取っていきます。
「存在」「言語」「時間」など、いずれも哲学の大きなテーマです。これらについての考察を、著者は仏教の教義や論説に基づき展開します。たとえば、心とモノをひっくるめて、その実体を否定する存在論や、言語の解体のなかから言語の果てを追究していく言語論、時間の流れをすべてこの絶対的な「今」に集約していく時間論など、仏教が世界や人間をどう理解してきたのかについて、さまざまな教説を引きながら説明していきます。
あるいは、「関係」の哲学として究極的に深められている仏教を、西洋のディープ・エコロジーの哲学にはるかに先立つ、環境問題の解決に貢献する理論として検討しています。いわば応用哲学的な側面からも、仏教の教説の奥深さを見直しているわけです。
こうした著者の解説を読んでいくことで、仏教のいろいろな教説の概要を学べるとともに、哲学的な思考方法のトレーニングにもつながります。実に有益な一冊です。また、本書は仏教の哲学的な再解釈の試みとしても優れています。たとえば、仏教の代表的な思想の一つである唯識の教えを、著者は、「識」という心の問題ではなく、唯「事」と解釈します。そして、唯識は主客二元論を超えた「事的世界観」を示していると論じます。とても刺激的な見解です。
なお、このように仏教を哲学として理解していくスタイルは、著者の研究対象の一つである、西田幾多郎と鈴木大拙の宗教哲学の影響下で行われています。実際、本書の「絶対者」についての章では、西田による「無の絶対者」の哲学の意義が強調されています。
仏教と哲学の関係について考えた先人たちは、すでにけっこういるわけです。本書は、そうした先人たちが築き上げてきた伝統を引き継ぎながら、著者の豊かな学識を活用して、仏教の哲学的側面はどういうところにあるのかを、とても平明に記した好著と言えます。
③『思想としての仏教入門』 末木 文美士 著
[amazonjs asin=”490151041X” locale=”JP” title=”思想としての仏教入門”]
②の本と似たようなタイトルで、問題意識も重なる部分はありますが、書かれている内容はだいぶ異なります。基本的にはタイトルどおりの仏教入門書で、仏教の基礎知識を幅広く学べます。一方で、その知識の整理の仕方に、著者のオリジナルな思想がよく見て取れます。そして、その背後には著者の哲学への強い関心があります。
西洋哲学は、19世紀のニーチェや、20世紀以降のポストモダン思想などによって、哲学の自己破壊と再生を続けてきた。このダイナミズムに、仏教も学んでいくべきではないか。それが著者の考えです。日本人の思考に根深くインストールされている、伝統思想としての仏教を、西洋哲学にならい現代に通じるかたちで再生する。それが著者のもくろみです。
著者いわく、仏教は「無我=無自性=空」を説き、おおむねポジティブではなくネガティブな世界像や論理を提示する傾向があります。竜樹のような、否定に否定を重ねる論理クレーマーが、妙に尊敬されたりしています。そのため、仏教は社会を支える思想としては弱いところがあり、実際、しばしば他のポジティブな宗教(ヒンドゥー教や儒教や資本主義など)に圧倒されてきました。仏教は「過渡期の思想」になりやすいと、著者は鋭く指摘します。
他方で、やたらとポジティブになる場合もあります。たとえば、生まれたままの人間やありのままの自然を、「仏」として全面的に肯定したりします。生きているうちは仏教とほとんど関係のなかった人間が、死んだ後にやすやすと「極楽浄土」で暮らせるようになったりもします。きわめてのんきな発想ですが、しかしこのポジティブ感ゆえに、日本に仏教が定着したことの意味は、よくよく考えるべきだろうと著者は述べています。
あるいは、『法華経』に説かれる永遠の仏や、浄土教の阿弥陀如来など、現代ではおおむね非科学的でファンタジックな存在を、どう考えたらよいか。その一つの回答として、これらは私たちと「他者」との関係を深く問い直すための何かなのではないかと、新鮮な考察の糸口を与えてくれます。こうしたロジックの展開の裏側にも、著者の西洋哲学の学びが確実にあります。
日本という場にこだわって、仏教で思考することの可能性を多彩に示してくれる、最高の入門書ではないかと思います。
④『清沢満之が歩んだ道:その学問と信仰』 藤田 正勝 著
[amazonjs asin=”483183842X” locale=”JP” title=”清沢満之が歩んだ道”]
先に、仏教と哲学の関係について考えた先人として、西田幾多郎に言及しました。その西田が「日本の哲学者」として大西祝とともに高く評価したのが、清沢満之です。清沢は、明治時代を代表する仏教者でもありましたが、その生涯と思想について、コンパクトにまとめたのが本書です。清沢についての本は、ほかにもたくさんありますが、特にその哲学について初心者にもわかりやすいよう明快に論じた著作としては、これが随一でしょう。
清沢は、仏教と哲学が交わる道を真摯に歩んだ人物です。まだ西洋哲学の翻訳書や解説書の乏しい時代に、哲学書をものすごく熱心に読み込み、ひたすら考えを深め、これを自らの宗教哲学を創り上げるための素材としました。彼にとっては、この哲学的な探究と、仏教者としての信仰が、互いに切り離せないものとなっていました。じっくりと考えることなく信仰を受け入れることはできないと、とても真面目な態度で仏教に向き合っていたのです。
本書で詳しく解説されるとおり、その宗教哲学の根幹をなすキーワードは、「有限」と「無限」です。有限な存在であるはずの人間は、ときに有限性を超えた次元への思考に誘われる。なぜか。人間が本来的に、その無限なるものとのかかわりのなかで存在しているからだろう。いかにしてか。自己の内面を見つめることで、そこに無限への扉を見つけることもあれば、無限からの働きかけによって、それに気付くこともあるだろう。では、無限に接近した人間は、どうなっていくのか。そこから新たな生き方や倫理が切り開かれていく・・・
こうした清沢の哲学は、やがて、西田幾多郎らの日本哲学において別のかたちで継承され、あるいは、哲学的な思考を好む後続の仏教者たちに、大きな影響を与えていきます。仏教と哲学の交差する場所を、日本で最初期に体験し、そこからかなり興味深い哲学的な実践を行ってみせた、清沢満之という人物。その生涯と思想は、これからの仏教と哲学の関係について考えていく上でも、豊かな示唆に富んでいます。
⑤『〈仏教3.0〉を哲学する』 藤田 一照×永井 均×山下 良道
[amazonjs asin=”439313592X” locale=”JP” title=”〈仏教3.0〉を哲学する”]
明治期にはじまった仏教と哲学の対話ですが、その現代における最先端的な試みが、本書に記録されています。日本の大乗仏教(とりわけ禅)と、東南アジアや欧米で人気のマインドフルな瞑想を組み合わせた〈仏教3.0〉を模索する、藤田一照氏と山下良道氏の名コンビ。この二人が、永井均氏という、現代日本で最もストレートに哲学している哲学者と、全力で語り合った本です。
永井氏は、きわめて独創的な〈私〉の哲学を探究しています。この世界には何百万種類もの生き物がいて、何十億人もの人間がいるのに、なぜ、この、これが、私なのか? という問いを核心とする哲学です。自分の身の回りや広い世界には、それぞれの「私」がいるよね、という話ではありません。なぜか、何の根拠も無く、ここに、〈私〉が存在しているという謎をめぐる探究です。
何を言っているのかよくわからない人は、本書か、あるいは永井氏の別の本を読んでください。いずれにせよ、そんな超当たり前でいて超根源的な問いを深めている永井氏が、健康上の理由などから瞑想をはじめ、その実際的な効果を実感し、やがて、藤田氏と出会い、意気投合したことから生まれたのが、本書ということになります。
非常に面白いのが、上記した永井氏の〈私〉の哲学が、藤田氏&山下氏が考える〈仏教3.0〉の思想と、言葉遣いはだいぶ異なりながらも、おおよそ同じ景色を見ながら実践されていることが、本書から伝わってくることです。〈仏教3.0〉では、瞑想をいくらやっても仏教の正しいものの見方がわかっていないとダメ、ということで大乗仏教を改めて見直そうとしているのですが、その取り組みが、永井氏の哲学と驚くほど共振しているのです。
その共振ぶりのもと、仏教の「無常」や「無我」といった、単純な説明だと「すべては変化する」「いつまでも続く独立した私なんで存在しない」のようになる、あまり面白くない話を、哲学的にどう鍛え直していったらよいかが議論されます。あるいは、自己と他者との関係や、死の意味が、仏教と哲学を行き来しながら、深く深く問われていきます。
仏教のアップデートには、やはり哲学の視点や知見が必要だ。そう確信させてくれる快作です。
以上、哲学との関係で仏教を「じっくり考える」ための本を紹介してきました。どの本も、「ありがたい法話」とかにはない新鮮さがあって、仏教にあまり関心のない読者にも、グッと迫ってくる言葉が少なからず含まれているかと思います。
哲学は「概念の創造」だという定義がありますが(國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』岩波書店)、仏教の場合も、やはり、常に新しいコンセプトを創っていくことが求められると思います。そして、そうした創造的な営みのためには、おそらく、ひとりひとりが「じっくり考える」時間が大事になってくるのではないでしょうか。