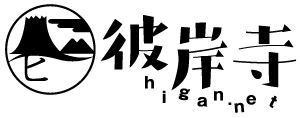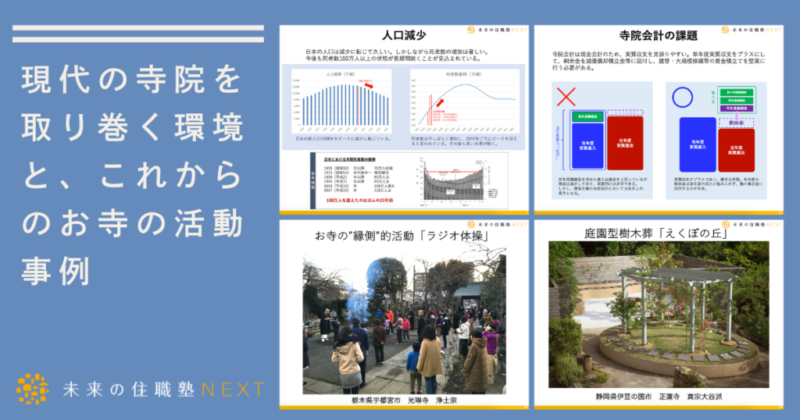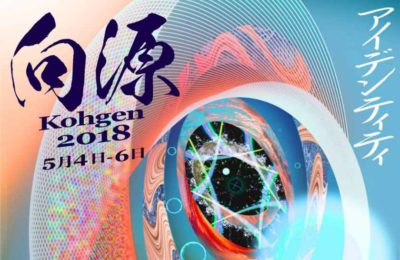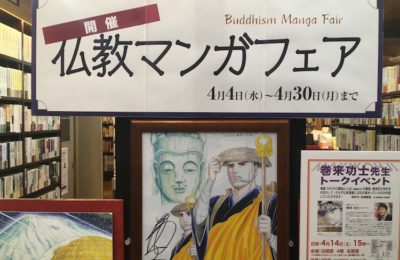未来の住職塾NEXT 講師の遠藤卓也と申します。
お寺の持続的な運営と、宗教者のリーダーシップにまつわる学びの場「未来の住職塾」は令和7年度で通算14期目を迎えます。5月に開講予定(現在、受講生を募集中!)の「未来の住職塾NEXT R-7」に先行して、毎年恒例となる「体験講座」を開催致しました。
現在、未来の住職塾のYouTubeチャンネルにて最新の体験講座の映像をフル公開しています。前半60分は木村共宏講師による「寺院を取り巻く環境 – 内外環境について」。後半は私、遠藤卓也が「これからのお寺の活動事例 – 未来の住職塾修了生の事例より」というタイトルで30分お話ししています。
お寺の運営に携わる方であれば、どなたでも学びのある内容になっていますので、よろしければぜひご覧いただき、「未来の住職塾NEXT R-7」受講検討の参考にしていただければ幸いです。
お寺の現場を見聞きして感じる変化
私は、未来の住職塾をこれまで13年間続けながら、寺院の継続について危機感を持つ方々と共に学んできましたが、やはりコロナ以降、寺院を取り巻く環境はものすごいスピードで変化していると感じます。
各寺院を訪れる中で見聞きした中から、私が現在抱いている実感を挙げてみたいと思います。
葬儀の多いお寺、葬儀の少ないお寺
“多死社会” と言われてきた時代に差し掛かり、ご葬儀の機会が格段に増えているというお寺の声を聞きます。ご葬儀やご法事に対応していくために、お手伝いの方を頼もうとしても、地域での僧侶の人数が減っており、お願いできる人がいない。住職一人でなんとか対応しているため、とにかく日々が忙しく今後のお寺のことを考えたり、将来を見据えた施策に着手する余裕がない。多忙による時間不足に悩む声が届きます。
一方で「数ヶ月にわたってご葬儀がない。こんなことは今までなかった」というお寺もちらほら。この差は何故でしょう。人の生死にまつわることですから「たまたま」なのかもしれません。お寺として関わっている檀家さんの数にも違いがあります。しかし「たまたま」として見過ごして、それでお寺は続いていけるのでしょうか。やはりご葬儀やご法事によるお布施は、寺院を持続していくための大きな支えとなっているからです。
いくつか理由は考えられますが、例えば身近な人が亡くなった際に、菩提寺に連絡していないというケースも考えられそうです。TVでも街なかでも「インターネットでご葬儀を依頼」できるという広告が溢れています。お寺との接点が少ない場合などは菩提寺に連絡するという発想がなく、スマホで検索して「安価な家族葬」というイメージのあるネット業者さんに依頼している場合も増えてきているのではないでしょうか。
起きている現象の原因を探っていくと、実は「檀信徒とのコミュニケーション不足」が一因であるという可能性も考えられそうです。檀家さんが次世代と別居している場合などは特に関係構築が難しくなっています。
そんな中で、お寺の本堂で行なう「お寺葬」に力を入れるお寺さんが各地で出てきています。「お寺でご葬儀できますよ」と、日々の関係性の中で周知をしておくこと。そして、ご葬儀の機会をお寺で共にすることで、次世代檀信徒との絆をより深めることにつながります。葬儀の会場費が抑えられるということも、メリットとしてお伝えすることができます。

未来の住職塾では、これまで「お寺葬」に関する勉強会を何度か開催してきました。様々な宗派の青年会さんに呼んでいただいて、「お寺葬」に関する講師をさせていただくこともあります。
写真レポート|お寺葬勉強会&お寺の事業計画書発表会
https://note.com/fbl/n/n2ea235bdbdd8
登壇のご報告|2024年11月@旭川市 曹洞宗 – 12月@越前市 浄土宗&真宗出雲路(遠藤)
https://note.com/fbl/n/n497028d938fd
インターネットによる法事依頼の増加
ホームページをもっているお寺では「初めてのご縁の方から法事の依頼が増えている」というお話しも聞きます。よくある話としては、ネット経由で業者さんに葬儀を頼んだところ、四十九以降の法事は対応してもらえなかったり、葬儀での印象がよくなかったためにあらためて近隣のお寺を探しているというケース。これも、ネットでの葬儀依頼が増えていることの影響がありそうです。
できればご葬儀から、いやそれよりも前にご縁がつくれるといいのですが、、、。
墓じまいと樹木葬ブーム
とある勉強会の質疑応答の際に、私の講演を聞いてくださったご老僧がこう言われました。「自坊は家族のお墓のご縁で成り立っている。家族のお墓がどんどん減ってしまったらどうなるのか?どうすればいいか?」
おっしゃるように、先祖代々のお墓の墓じまいが進み、個人のお墓や納骨堂、共同のお墓に移行している時期です。後のないご家族が増えている中で、仕方のない変化です。都市部に人口が集中していることも、地方のお墓の墓じまいに拍車をかけています。
ライフスタイルの変化に応じて、様々な形・仕組みのお墓が増えてきました。特に「永代供養墓」「樹木葬」はもはや定番の検索キーワードになりつつあります。お寺にも多様な形式のお墓を備えておくことが重要と考える方もいらっしゃるでしょう。
そういったお寺側のニーズに着目し、「永代供養墓・樹木葬を始めませんか?」と持ちかける業者さんも増えてきました。例えば「樹木葬の造成に関する寺院の負担はなし。営業も契約も業者が行うので、契約時の冥加金の◯%を収めてください。」そんな営業を持ちかけられた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この「◯%」が「え、そんなに?」と躊躇する割合だったりもするのですが、「お寺さんとしては、契約者さんからのご葬儀やご法事の依頼が増えますから」という売り文句。
この事業にトライして、どのような結果になるかは本当にケースバイケースだと思います。メリット・デメリットどちらも考えられるでしょう。しかし大切な境内の墓地区域を使う事業になるので、どうするかは様々な視点からよくよく検討した方が良さそうです。
事業をおこなうための予備知識
では、自坊にも永代供養墓や樹木葬や納骨堂を設けようと思い、業者さんに連絡をした場合、造成費用の見積もりや共に事業を進めていくための計画や契約内容を提示されます。見積書や契約書の妥当性を判断するためには、お金や法律の知識が必要となってきます。そして、蓄えてきた資金を投じたり、境内スペースを使用するにあたっては、長期的な視点での検討が求められます。
特定の業者さんと組まずに、寺院主導型で永代供養墓や樹木葬をつくり、周辺地域の支持を得ているケースもあります。事業に挑むハードルはあがるかもしれませんが、自身の思うように進めていくことができるため、そういった選択肢を選ばれるお寺も少なからずあります。

また、収益事業を志向するお寺さんも増えてきていると感じます。宿坊、お寺カフェ、寺子屋など、お寺の特徴を活かした副業を行なうことで、将来に向けてお寺の持続可能性を高めておこうという種まき的な意味合いが主です。
規模は小さかったとしてもお寺で収益事業を始めるわけですから、資金計画の立案方法や税金の知識など、やはりお金に関する知識を求めている方が増えてきています。
園経営との両立の難しさ
お寺が行なう事業として、幼稚園・保育園・子ども園経営は古くからの定番ですね。未来の住職塾にも住職であり園長(または副住職であり副園長、など)という方が数多く参加なさっています。学校法人や社会福祉法人からの収入があることで、住職としての報酬を下げることができるため、中小規模の寺院を持続的に成り立たせていくことができます。
しかし単純に考えて園長と住職を両立させていくわけですから、属人的となり非常に負荷がかかりやすく「とにかく住職・園長が大変」という事態を招きやすいのも事実と言えるでしょう。この点は、家族・親族がうまく配役されて共に経営を担っている場合が多いのですが、昨今ではコンプライアンスの配慮や職員の不足。少子化などで、園経営の悩みも複雑化しています。二足のわらじでやっていけるような時代ではなくなってきているのだと感じます。
家族・親族に限らずに適切で優秀な人材を探し、園にもお寺にもしっかりしたマネジメント体制を構築していかなければなりません。
「短期視点の対策」と「長期視点の計画」
以上、あえて課題的なトピックを並べてみましたが、未来の住職塾NEXTではこうした諸々の課題に対して、短期的な視点で「とるべき対策」のナレッジも蓄積されつつあります。また、こうした課題に対峙しながらも、長期的な視点で計画を進めている修了生たちの事例もたくさんあります。(その一部は「体験講座」動画の中でご覧いただけます)

未来の住職塾NEXT 受講のメリットの大きな一つとしては「情報が集まってくること」があると思います。私が各地で集めてくる情報・知見もありますし、塾生たちが毎回持ち寄ってくれる現場情報や事例の数々があるのです。
「宗教者のリーダーシップ」講師の松本紹圭さんは、最近では海外での活動が多いため、海外の最新事情を塾に持ち込んでくれます。それはとても良い刺激になりますし、これからの日本社会の変化を予見するにおいても必要な情報であるでしょう。
「お寺のマネジメント」講師の木村共宏さんはマネジメント経験が豊富であり、事業計画や資金計画、法律など多岐に渡る知識を有しているため。個別の寺院の運営・経営に関する相談にも親身にのってくれます。
また、未来の住職塾NEXTは女性の受講が多いことも特徴的です。その学びやすさを支えているのが松崎香織さんです。お寺が女性にとってもっと活躍しやすい場になっていくように、さまざまな活動をされています。
そんな4名で、各地のお寺さんの学びをサポートしている「未来の住職塾NEXT」です。この記事を読んで何かを感じられた、寺院運営に携わる方にはぜひ、体験講座の動画をご覧いただき、5月開講予定の「R-7」の受講をご検討いただければ幸いです。(願書締切は 4/15 となっています)

共に学び、共にご自坊のこれからを考える時間を過ごしましょう!!
・未来の住職塾NEXT R-7 講座詳細|https://mirai-j.net/next
・未来の住職塾NEXT R-7 体験講座(動画)|https://youtu.be/53rSXoS9yqg