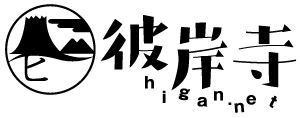言葉に関わる仕事をしているせいか、日本語の意味を考えるのが好きです。
同じ音だけれど違う漢字を宛がわれて、まったく別々な場所に置かれている言葉が、実は重なり合う意味を持っていることに気づくと視界が広がったような感じがします。たとえば「話す」と「離す」。人はつらいことや悲しいことがあると、何度も同じ話を繰り返し聞いてもらいたくなります。たぶん、「話す」ことで「離す」ことをしているんじゃないかな? と考えたりするのです。
「さようなら」という言葉については、須賀敦子著『遠い朝の本たち』の中で紹介されていた、アン・モロー・リンドバーグのエッセイの一節からその語源を知りました。アンは飛行家のチャールズ・リンドバーグの妻だった人。彼女は夫妻で東京を訪れたときに「さようなら」という言葉に出会ったようです。
「この国の人たちは、別れにのぞんで「そうならねばならぬのなら」とあきらめの言葉を口にする」。英語(goodbye)でも、フランス語(adeiu)でも「さようなら」は「神とともにあれ」「神のみもとで再会しよう」というように、別れは神さまが守っているのに、日本の人は「そうならねばならぬのなら」と別れていくのかと彼女は驚きを綴っています。
「そうならねばならぬのなら」と「あきらめる」。「諦める」は「明らめる」に通じています。これらの言葉は、日本語を母語としてきた人たちが、別れゆくこ とは「そうならねばならないのなら」と明らかにする、そういうものなのだと受け入れていたことを教えてくれているのだと思います。
でも、最近なんだか「さようなら」という言葉を使うことが減ってきたような気がします。「バイバイ」「またねー」「じゃあね」などと言うことが多くなるにつれて、「さようなら」は少し重たい言葉に感じられるのでしょうか。
「さようなら」。
口にするとやわらかで、とてもきれいな音がします。そして、日々のご縁をありのまま受け入れていくしなやかな覚悟を秘めた言葉だなあと思うのです。