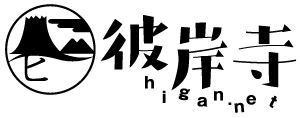今年の冬至は12月22日、北半球で最も夜が長く昼が短い日です。柚子湯に入ったり、かぼちゃを煮て食べる習わしがあるのは、太陽と過ごす時間の短さを、身体を温めることで補い生命を守ろうとしているようにも思われますね。
わたしにとって、この日は柚子湯を楽しむ日であると同時に、ひとつの死を通して死と親しく語り合う日でもあります。
2年前の冬至の日、わたしは東京の知人たちから届いた訃報を手にしていました。「通夜は今日22日」「告別式は23日」と日付の数字だけを拾い上げて、カレンダーの前で手のひらに乗せた心をぼんやりと揺らしていたときのことは、今もまだ生々しい感触を残しています。
「余命半年を宣告されて、いまは9か月目を生きている。驚いただろ?」。ひさしぶりのメールに書かれていた言葉の意味と、相変わらずな強がりのアンバランスさ。最後に会ったときの声に出す言葉がすべて呑みこまれてしまうあらがいようのない静謐さ。発熱した手がわたしの手を包んで「絶対に治すから、またおいしいものを食べに行こうな」と約束したときのこと。
そんなことをリピート再生しては、「絶対って言ったのに」と埒もないことを思い続けていました。たぶん、わたしは、告別式に行っても他の人と一緒にこの気持ちに”告別”できない。東京での式に行かないと決めたとき、これからずっと太陽と地球がめぐるたびに訪れる約束の日に、繰り返し別れを告げることでこの死を受け入れていきたいと思ったのでした。
約束という言葉には、「守る」とか「果たす」という動詞が寄り添います。守られなかった約束は、ひとつの命とともに果ててしまいました。そのことに思いをめぐらせながら、いつか私が死ぬときにはこの約束もまた完全に果てて消えるのだろうと、ふと自らの死にも触れてみるのです。そしてもちろん、会えなくなった人と過ごした時間や場所、語りあわれた言葉にも。
わたしたちは、時計の針やカレンダーが運び去ることのできない思いを、胸の底に重ねて折りたたんで持ち続けているのだと思います。そして、その思いに接続する日付や場所、あるいは映画や音楽に触れたときだけ、会えなくなった誰かや失ってしまった何かがふわっと立ち現われるような経験をします。過ぎ去りしものとの邂逅は、きゅっと締めつけられるような息苦しさや切なさをともなうことも少なくありません。でも、「悼む」ことは「痛む」こと、その「痛み」のなかにしか失われたもにつながる回路はないのだろうと、わたしは思っています。