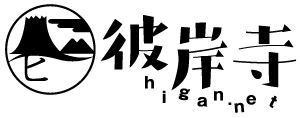歌手であり、お坊さんでもある二階堂和美さん(以下、ニカさん)インタビューです。
実は、私は歌手としてのニカさんのファン。すごく会いたいけれど、ずっとその一歩が踏み出せずにいました。「ニカさんに会いたい」という気持ちだけでは、「坊主めくり」ができないと思っていたのです(案外、ストイック)。
でも、2011年7月に発表されたアルバム『にじみ』を聴いて気持ちが決まりました。ニカさんが全曲作詞作曲を手がけたこのアルバムからは、仏教がにじんでいるのを強く感じたからです。それでもまだ尻込みしていた私の背中を押してくれたのは、『お寺座LIVE』の雪山俊隆さん。「ニカさんに取り次いであげるよ」と温かく背中を押してくれて、ようやくインタビューを申し込むことができたのでした。
ニカさんの人生のこと、『にじみ』のこと、そしてお坊さんとしてのニカさんのこと。広島のニカさんのお寺で行った超ロングインタビューを3回に分けて、週一回更新でお届けします。ぜひ、最後までおつきあいください。
のびのび育った”三つ子の魂”がステージに

——小さいころから大学に行くまでは、ずっとこのお寺で育ったんですか?
母が仕事を持っていたので、私は1歳から4歳まで山口県の母の実家に預けられて、三年間を祖父母と三人で暮らしたんです。姉はお寺の近所の人に見てもらっていたらしいけど、私の時はさらに思い切ったようで(笑)。
でもね、それは私にとって、すごくよかったと断言できることで。おばあちゃんたちは家族が会いに来て帰るときに「すごくつらそうでかわいそうだった」って言うんだけど、ほんとに祖父母がかわいがってくれたから完全に安心していたし、いろんな意味で豊かな感情を育んでもらったと思う。
だから、4歳でこっちに帰ってきてからのほうがむしろ居心地悪くて(笑)。実家なのに、きゅーっと縮こまっちゃった。保育園に行っても運動ができないからいじめられるし、お寺ってちょっと特殊だし、母は小学校の先生だったからいわゆるご近所づきあいも他の家のお母さんたちとはちょっと違う。だから、子どもの頃はすごく内気で引っ込み思案な感じだったんですけど、変わってくるもんですね。
——変わってくるもんですね(笑)。ステージ上では「三つ子の魂百まで」の部分が出ているんでしょうか。
そうだと思うんですよね。のびのび育ててもらった部分が20歳を過ぎてからだんだん生きてくる感じがあって。でも、お寺の縁側でめちゃくちゃ踊り狂っている8ミリ映像が残っているのね。全盛期だったピンクレディをマネして歌って踊って、家族にも「わー、上手上手!」みたいにほめてもらって調子に乗ってたんだろうね(笑)。
2006年に、広島クラブクアトロでライブしたときに両親が見に来たんですけど、ステージで歌い踊る私を見て、「小さい時に縁側で踊り狂ってた和美とまったく同じだった!」ってすごいびっくりしていました(笑)。
バンドデビューは骸骨のアルバムで「ナナナナナナッ!」
——音楽活動はいつからはじめたんですか?
高校2年生の頃にはじめたコピーバンドが最初でした。合宿のバスでカラオケみたいなのが回ってきて歌ったら、「二階堂は歌がうまい」ってなって「ボーカルやって」って言われたんです。CDをぱっと渡されたら骸骨の絵がついてて「ええー?」みたいな。
——骸骨の絵のアルバムって、誰だろう?
ガンズ・アンド・ローゼズっていうバンド。その頃、すごく流行っていたんです。私は竹内まりやとか聴いていたからそんなの全然知らなくて。でも、バンドやってみたい!っていう憧れはあったし、せっかく話が来たから「ナナナナナナッ!」(ガンズ・アンド・ローゼズ「welcome to the jungle」の一部)ってやっていて(笑)。当時は親も心配だったと思うけど。
——突然、娘がシャウトしながら歌の練習をはじめたら…(笑)。
フギャー!とかね(笑)。歌詞の意味がわかったらもっとまずいよね。受け身ではじめたことだったので、「ブラック・サバスやろう!」「ふむふむ」「アンスラックスは?」「なんでもいいよ」みたいな感じだった。大学に入ってからも最初はジャニス・ジョプリンのコピーバンドをやったりしていました。
——ニカさんが歌うジャニス、聴いてみたいなあ。大学は山口のほうに行かれたんですよね?
そう。ちょっと意固地なところがあって「都会に出るのはナンパだ」みたいな感じで、あえて地元に近いところを選んで。ほんとは出てみたかったくせにね。あの頃はインターネットもないし、山口って県内に一軒もタワーレコードみたいなお店やライブハウスもないし、コンサートも誰も来ない。でも、同級生や先輩に面白い人がたくさんいて、いつも誰かの家でレコードを聴いてあーだこーだ言っていました。ちょっと上の世代の人たちの学生時代の遊びに似ていたのかもしれないね。少ない情報から、どうにかおもしろいことを探す感じは、今思えばとってもいい経験だったなって思う。
人生の「いやぁ、まいった!」で仏教にまた出会って

——大学のときは何を勉強していたんですか?
教育学。学部のときは小学校教員の、大学院では美術教育の勉強をしていました。絵を描いたり写真を撮ったり、美術の制作に熱を上げてましたね。教育実習に行くとすごく熱くなったし、まんざらでもなかったんです。でも、教員採用試験も厳しい時代で、それよりもレコード会社にテープを送って反応がくる打率のほうがよかったのね(笑)。どっちも狭き門なんだったら「私、音楽のほうが向いてるんじゃないかな?」と思って。
——とはいえ、東京に出ていくのはかなり勇気がいることだったんじゃないかな。
うん、勇気いった。都会に出ることを、どこかかっこわるいと思っていたし。でもレコード会社の人にスカウトされたことや、当時つきあっていた人が東京の人だったこともあって、もう、ここは調子づいてみよう!と。結局、将来は寺に戻ることを条件に、恋人も紹介して、親も渋々納得して東京に出してくれたんです。
最初は東京も全然おもしろくなかった。おもしろくなってきたのは、スカウトされたレコード会社を離れてから。でもそうやって音楽活動が調子に乗りはじめころ、家族との約束が浮上してきて。もともと3年くらいっていう目安だったから。そしたらもう急に拒絶反応が出てしまって。うわーっ!ていろんなことを次々にすべてひっくり返してしまった。これまで押さえ込んでた自分のわがままみたいなのが、突如、全部吹き出してしまったんです。
当時結婚していた相手とも、その人の親とも、自分の親とも、ものすごく激しくぶつかりました。もう全部が「うわー、ひどいな、人間」みたいな感じで。何もかも自分が招いたことなんだけど「うわ、ひっどい」と思って。ほんとに、誰ひとりとして信用できないというか、今まで何だったのかっていうか。みんな自分の言い分ばかりを、がーって言って。そういう私が一番そうなんだけど。「いやー、まいった!」と思ってね。
そういうごちゃごちゃーっとした、自分の一番大きな挫折みたいな経験をして、ようやく「ああ、仏教が言ってたのはこういうことだったんだー」みたいなね。そんななかで徐々に「あー、仏教だぁ」みたいになれたんです。
「自分が決めた道だから」が一番あやういんだよね
——今は笑ってお話しされていますけど、その当時は本当につらかったと思います。そんななかで「あー、仏教だぁ」と思ったのはどういうところだったのでしょうか。
自分の物差しをあてにするのは、すごくあやういものであるっていうのは、仏教がずっと言ってきていることだからね。まず、「それは本当だな」と思いました。「この人こそは」「これは私が選んだ道だから」っていうのが、あまりにも簡単に壊れていってしまって。ほんとに、「自分の決めた道だから」というような言葉がすごく虚しく思えるようになってきて。

——「自分が決めた道だから」。アーティストにはすごく似合う言葉ですよね。
そうなの! だからほんとにすごく、自分のなかで大きく変わって。自分はなにがしのものでもないっていうか(笑)。でもね、それ以前にぼんやりでも仏教を聞いていたことがよかったのかなと思っていて。まったく仏教を聞いたこともなかったら「ああ、こういうことだったんだ」とも思えなかったと思うし、「しみる~!」ってなる前に聞かされておくことは、やっぱり必要な気がするんですよね。
——実は、私もしばらく前に、身近な関係が全部壊れるような経験をして。こんなにお坊さんの話を聴いているのに、ある条件下では自分の心も鬼のようになるし、どこまでも弱くなってしまうことを実感して、はじめて仏教が骨身にしみました。
ほんとにそうだよね。仏教をよりどころに生きていても、そういうことが起きるとどうしようもなくなる。醜くなってしまう。だからこそ、親鸞聖人が言われていた「本当に自分ではどうにもできない」っていうことが、どんどん骨身にしみるようになってくるんだよね。もうね、鬼のようになる自分っていうのは、どうしようもないんですよ、坊さんでも誰でも。けれど、その受け止め方、受け流し方を習うっていうのが、仏教なんじゃないですかね。
日常に縛られて出てくる爆発力
——広島に帰ることは、東京に出るときとはまた違う勇気や覚悟が必要だったんじゃないでしょうか。
うん、ほんとにそう。あれだけ家族を振り回しておいた挙げ句の帰郷ですからね、すごく大きな覚悟でした。広島に帰ってお寺を継ぐということは、「新しい恋愛をして二人の城を築く」とか「出会いによっては海外に移住」とか、そういう可能性を自ら断ちきったということでしたからね。でも、まずはガタガタにしてしまった家族との関係を修復することが一番大きな目的だった。
家族との生活の中で音楽をやっていくっていうリズムをつかむまでには何年もかかりました。『二階堂和美のアルバム』というアルバムの制作が動いていたから、かろうじて音楽を続けることができたけれど、そうでなければ続けていられなかったかもしれないですね。実際に、帰ってからしばらくは自分の時間を作れなかった。一か月くらい楽器を触らないこともざらでした。でも、可能性を自ら狭めたことによって、良く言えば、地に足がついたんです。ずっとうわっついてましたから。
——お坊さんをすること、音楽を続けることが人生の軸になったんですね。
そうですね。私の場合は縛られてようやく出てくる爆発力があったのかな。帰るところのある強みっていうか、日常があるからこそはじけられる。ライブの時だけはぶわーっとやれる。自分にとっては、それが性分に合っていたのかもしれないです。
今は新しい人と出会って、新しい家族ができて、近くに頼れる音楽家もいて、いろんな事が自然な形でやれているので、縛られているとさえ思わなくなっています。
でもずっと、自分がしでかしてしまった事、振り回してしまった人たちに対する懺悔の気持ちがついて回るからこそ、お坊さんとして生きていけるんだと思ってます(第2回へつづく)。
プロフィール
二階堂和美/にかいどうかずみ
http://www.nikaidokazumi.net/
1974年広島生。浄土真宗本願寺派僧侶。高校時代よりバンド活動を開始、1997年からギターを弾きながら歌うスタイルでソロ活動を開始。1998年、山口から東京へ移住。1999年ファーストアルバム『にかたま』以後、5枚のアルバムと2枚のミニアルバム、国内外のミュージシャンと数々の共作アルバムをリリース。2004年に広島へ帰郷する。天使のようなやさしい歌声から力強くソウルフルな歌声まで自由自在にあやつり、天真爛漫なステージでは聴く人の心と身体を和ませる。2011年、全曲を自ら作詞作曲したはじめてのアルバム『にじみ』を発表、高い評価を受ける。『mina” perhonen(ミナ ペルホネン)』の2011 秋冬の映像モデルにも抜擢された。