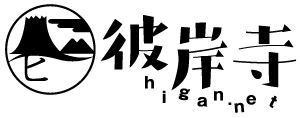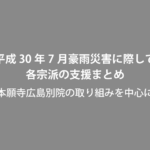思い返せば、自分が始めて「仏像」と出会ったのは中学生の時、京都へ修学旅行へ行った時のことだったでしょうか。写真で見たことのあった広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像を目の当たりにし、「アルカイックスマイル」と評されるその柔和な表情に心を打たれたことを今でも覚えています。その後、京都に住む期間に東寺の立体曼荼羅や三十三観音の千手観音の迫力に圧倒され、地元に戻ってからも何度も京都や奈良を訪れては、様々なお寺に安置された仏像と対面し、それぞれの仏像の美しさや力強さ、そしてその歴史や込められた想いなどに感動を覚えたものです。
私も通過したこのような「仏像」との向き合い方は、昨今の「仏像ブーム」と呼ばれた現象とも通じるものでしょう。多くの人が仏像ファンとして、おそらく私と同じように、仏像として表現された一種のアートとしての精巧さや美しさに魅了されたのではないでしょうか。
しかし本来「仏像」とは、仏さまの姿を表したもので、その姿を通して仏教の理想を表現するものでした。同時に、お寺の「本尊」として崇敬の念を持って大切に尊ばれてきたもののはずです。では、一体いつの頃から、「仏像」が本尊としての意味合いではなく、美術・芸術の視点から見られるようになってきたのでしょう。今回ご紹介する『仏像と日本人』は、まさにその私たちの仏像との向き合い方のルーツを解きほぐそうとする1冊です。
著者の碧海寿広(おおみとしひろ)さんは主に近代仏教の研究者で、これまでも近代における日本仏教に関する著書を出版されてきました。そんな碧海さんの今回の新著『仏像と日本人』では、仏像を論の中心に据えながら、日本の近代における寺院を巡る大きな変化や、お寺や仏像と関わる人々の変化を一つ一つ丁寧に紐解いていかれます。それによって、京都や奈良を始めとした古寺を巡り仏像を「鑑賞する」という文化が、時代の変化に影響を受けたものであり、かつ「仏像」が秘める「美」に魅了された人々によって耕されてきたものであったことが浮き彫りにされていきます。
江戸時代の「開帳」や寺社を参拝する巡礼という流行に始まり、明治期の廃仏毀釈、日本人と「美術」の概念との出会いによる日本の美術の再発見、そしてそこに垣間見える国家の意識。大正期に入ると、仏像といかに向き合えるかが一つの「教養」として受け取られ、次第に仏像における宗教性が薄められていく。しかしそこから再度、仏像における宗教性が再発見されながらも、戦争という大きなうねりの中に、また仏像も取り込まれていってしまう。近代という大きな変化の時代にあって、仏像への人々の向き合い方も大きく移り変わっていくことが、本書を通して明らかにされます。そしてその時間軸の延長線上にいる私たちが「仏像」と対峙し、感動を覚えるというような出会いができるのは、決して当たり前のことではなかったということに気づくこともできることでしょう。
さらに、いとうせいこう・みうらじゅんを一つの発端として起こってくる「仏像ブーム」によって仏像を見ること(見仏)が一つのカルチャーとして一般化・大衆化・観光化したこの時代。仏像を「本尊」とする寺院は、いかにその現実と向き合っていくべきかという部分にも言及され、これからのお寺を考える上でも実に示唆に富んだ内容となっております。
仏像ファンにとっては仏像の新たな魅力の再発見、そしてこれから仏像との新しい出会いを経験される方には、より深い視座と感動をもたらしてくれるであろう1冊です。