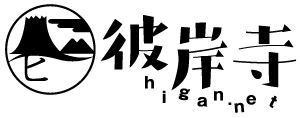数年前から初詣は東京の築地本願寺へ行っています。今年も晴天に恵まれるなかお寺を訪れた際、境内の一角にあった書店「築地本願寺ブックセンター」が閉店していることに気づき、ちょっと驚きました。ググってみると、昨年の6月に店じまいしていたとのことで、気づくのがだいぶ遅かったわけですが…。2017年11月の開店から約4年半の営業を終えたそうです。わりと短い寿命であったと言えるでしょうか。
いろいろと経営上の理由がありそうですので、あまり軽率なことを言うべきではないのかもしれませんが、やはりお寺を訪れた際に「仏教の本」を買って読む人はそう多くはないのだろうな、というのが率直な印象です。ブックセンターと同じ建物の中にある「築地本願寺カフェ Tsumugi」のほうは相変わらずの盛況ぶりで、休日に食事やお茶をしながら楽しそうに談笑している人々は、まるで極楽浄土にいるかのように幸せそうに見えました。
これは「仏教の本」が大好きな筆者としては残念な出来事でしたが、とはいえ、この数年のあいだに、「仏教の本」に関する明るい話題も当然ありました。その最たるものが、もっぱら仏教書を扱う京都の老舗書店、法藏館さんによる2020年の「法藏館文庫」の立ち上げでしょう。世評の高い一般向けの仏教書をはじめ、文化史や哲学、宗教学関連の「これは」と思える本を次々とお手頃価格で文庫化しており、ツウな読書人らを歓喜させています。
その法藏館文庫のラインナップにある、個人的なオススメをいくつか挙げてみましょう。
まずは、石田瑞麿の『地獄』。旭川の本願寺派の寺院に生まれるも「仏教を本気で勉強するなら僧籍は取るな」という父の教えに従い在家を貫いた著者が、地獄とは「人間界」の悲惨さを説くための方便であるという観点から、地獄の歴史を明快に解説した本です。
あるいは、唐木順三の『禅と自然』。近代的な思惟の乗り越えを企図した著名な文芸評論家が、道元の実存哲学や一休の「自然」な生き様、芭蕉の旅と創作にあらわれた無常の精神などを例に、禅の本質を達意の文章で伝えてくれます。
やや専門的な著作も紹介しておきましょう。唐代の僧・義浄が著した『南海寄帰内法伝』の現代語訳(宮林昭彦・加藤栄司訳)。「七世紀インド仏教僧伽の日常生活」という副題の通り、7世紀のインドの僧院における暮らしのディティールが精彩に記述された本です。アジアの仏教史を検証する上で欠かせない第一級の史料ですが、僧侶たちの衣食住からトイレのマナーまで、具体的なトピックが盛りだくさんで面白いです。あたかも大昔のインドの寺院をフィールドワークしているかのような読書感。
また、フィリップ・C・アーモンド(奥山倫明訳)『英国の仏教発見』は、少し変わり種の仏教書をお求めの向きには最適の一冊でしょう。近代以降、それまでキリスト教を重んじてきた英国の人々が、仏教という「新宗教」をどう受け入れ解釈してきたか、そのダイナミックな歴史が丹念に検証されています。こちらは何と法藏館文庫のオリジナル作品。実に素晴らしい企画の本だと思います。
法藏館文庫だけでなく、たとえば講談社学術文庫や角川ソフィア文庫など、より昔からある人気の文庫レーベルでも、今に至るまで仏教関係の名著や入門書が様々に刊行され続けています。この数年のあいだだけでも、「仏教の本」をめぐる状況は着実にアップデートされ改善されているわけです。「仏教の本」がベストセラーになることは昨今では稀ですが、それでも各種の仏教書に対する一定のニーズがあるからこそ、こうした現状が成り立っているのでしょう。
彼岸寺さんは、この20年間、インターネットというニューメディアを通して仏教に関する親しみやすく幅広い情報を、やはり着実に提供されてきたかと思います。書籍というオールドメディアと相互に影響を与え合いながら、仏教をめぐる情報や言葉はたえず更新され続けている――。そこから、今後どのような新しい「仏教の本」が生まれてくるのでしょうか。その可能性を想像するだけでも、仏教と本を愛する人間(私だ)のウェルビーイングはぐっと高まるのです。