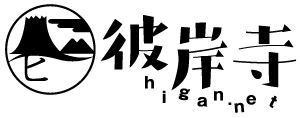浄土宗大蓮寺・應典院の秋田光軌です。前回は「演じる仏教、煩悩の哲学」というタイトルに触れながら、本連載の概要について書きました。従来の「信じる」という立場からではなく、浄土仏教のおしえを「浄土の物語」として扱い、それを「演じる」という立場に身を置くことで、はたして仏教とのどのような関わり方が可能になるのでしょうか。
「浄土の物語」の具体的な検討や、実際に演じるための指針について書く前に、この第2回ではまず物語論の知見を確認し、物語とは何なのか、それが私たちの生に果たしている大事な役割や危険性を見ておきたいと思います。さらにその後の何回かにわたって、物語の視点から初期仏教や浄土仏教の特徴を大づかみに把握することで、連載全体の記述を理解するための足場を形づくることができるでしょう。
ストーリーとナラティブ
さて、前回から物語ということばを連発しているわけですが、多くの方は物語ということばから、テレビドラマや小説などで普段親しんでいるようなものを連想されたはずです。特定のできごとが時間の流れの中で展開する、いわゆる起承転結がある物語のことですね。どんなに非現実的で荒唐無稽な内容であったとしても、私たちはそうしたできごとの積み重ねに一定の納得を感じ、熱い涙を流すことだってあります。特定のできごとが時系列順に展開する、ひとまとまりの連なりのことを、この連載では「ストーリー(story)」と呼ぶことにしましょう。ストーリーとしての物語は、生活のなかで気分転換のために出向く映画館のスクリーンや、大きな期待とともに開いた本の中に、あるいは電車の広告やインターネットにも溢れています。そして、ストーリーとしての物語にはこんなイメージもあるのではないでしょうか。それは小説家や映画監督や劇作家、あるいは広告会社や宗教者といった、専門性をもつ一部の人々によって担われるものである。世の中は物語の「作り手」と「受け手」に分けることができ、専門性をもたないその他多くの人々は、物語を鑑賞し、その完成度を評価する「受け手」でしかない--。
一方で、20世紀後半から物語の「ナラティブ(narrative)」という側面が注目されてきました。ナラティブとは、一言で言うと「語り(ナレーション narration)」という行為に重点を置いた理解のことです。考えてみれば、大昔にはテレビも映画館もなければ活字すら発明されていなかったのですから、民間伝承によるストーリーの多くは口伝えで語られてきました。そもそもストーリーというものは、なんでもない日常を暮らしている市井の人々の「語り」からはじまり、受け継がれるものでもあったわけです。現代の私たちを振り返ってみても、「私の人生の物語」とか「私たち家族の物語」というように、誰にも知られていないが当人にとっては何よりも大切なストーリーを語ることがありますね(特に死を間近に控えた人はそうです)。各メディアから発信されるストーリーには影響を受けながらも、私たち自身がすでにストーリーを語り出している存在でもある。つまり、人間を単純に物語の「作り手」と「受け手」に二分することなどできません。むしろ、物語を語り出すという行為こそが、人間の生そのものを基礎づけるような役割を果たしているのではないか。ナラティブの視点が導入されることで、このようにより広がりを持った物語理解、ストーリー理解が可能になったのです。
ストーリーやナラティブの定義を含む物語論は、まず文学領域ではじまり、人文科学・社会科学全般に広がった後、今や臨床医療からゲーム業界、マーケティング分野に至るまで、さまざまな領域にわたって議論がなされている現状にあります。しかもそれぞれ微妙に文脈が異なるため、その全貌を整理することはとても私の手に負えないだけでなく、この連載の趣旨からも大きく外れてしまいます。そこで、ここでは去年出版された平易な物語論の入門書である、千野帽子『人はなぜ物語を求めるのか』(ちくまプリマー新書、2017)に依拠しながら、議論をまとめていきたいと思います。
人間は「物語る動物」である
この本では、ナラティブの視点を導入した物語理解、ストーリー理解がまさに展開されています。著者によれば、私たち人間は物語を外から摂取しているのではありません。そうではなく、人間は生きているとストーリーを合成してしまう。人間は物語を聞く・読む以上に、ストーリーを自分で不可避的に合成してしまうというのです。どういうことでしょうか。
人間とは「物語る動物」であり、ストーリーこそ人間の認知に組み込まれたフォーマットであるという、著者の主張を確認していきましょう。たとえば私が初対面の相手に自己紹介する場合、「日本人の男性の僧侶です」と一言で終わらせることもできますが、より詳しく伝えようとすれば「1985年に大阪の大蓮寺に生まれ、20代前半までほとんど仏教に関心がなかったんです。京都の大学を卒業した後、数年間は福祉関係の仕事についていましたが、2011年の東日本大震災や友人の死に大きなショックを受けて、それが転機になって僧侶になる決心を固めました。それから浄土宗のおしえを知ってーー」というように、特定のできごとを時間の流れの中で展開させて語らざるをえません。つまり、私は「じぶんは何者か?」ということをストーリーのかたちで理解しているのです。試しにやってみてほしいのですが、このようなことは「じぶんにとって家族や恋人はどのような存在か?」とか「じぶんが生きているこの世界とは?」といった問いについても同じです。たった一言で答えを言い尽くすことのできない問い、他ならぬじぶんに切実な意味をもつ問いに対しては、全てこの構造が当てはまります。ここで注意すべきなのは、上に語ったストーリーと全く関係ないできごと、あるいはそれに沿わない矛盾するようなできごとも、実際は私の人生に無数に起こっているにもかかわらず、ストーリーを語るときにそれらは自然と捨象されているということです。何が語られるべきできごとで、何が語られる必要のないできごとなのか、私たちは意識せずに取捨選択を行っています。
さて、上の段落で書き上げたストーリーをもう一度ご覧ください。履歴書のように箇条書きにするのではなく、「2011年の東日本大震災や友人の死に大きなショックを受けて、それが転機になって僧侶になる決心を固めました」と、因果関係、つまり原因と結果について言及しました。私の自己紹介のうち、特にこの部分に共感や納得を感じた方は多いのではないでしょうか。実は、もっともらしい因果関係を加えると、ストーリーの滑らかさ、説得力がぐっと増すのです。なぜかといえば、それはできごとが「わかる」感じがするからです。もしかすると、私が僧侶になる決心を固めた真の原因は、福祉の仕事をしていた時にクライアントの語りを延々と聞き続けていたことかもしれないし、京都の大学で就職活動を迎えた時にあまりの選択肢の多さに絶望したことかもしれません。実のところ、真の原因が何なのかは当の本人である私にもよく分からないのです。ただ、さしあたり「東日本大震災や友人の死が原因となって、僧侶になる決心を固めました」というストーリーをつくってしまえば、私は他人に対しても、そしてじぶん自身に対しても、自らの人生を説得的に紹介することができます。
なぜ、人はこのように物語を合成してしまうのでしょうか。教育心理学者の山鳥重さんによれば、人間とは、じぶん自身に降りかかってきたできごとの原因や他人の言動の理由がわからないと、落ち着かない生き物であるそうです。
「わかる、というのは秩序を生む心の働きです。秩序が生まれると、心はわかった、という信号を出してくれます。つまり、わかったという感情です。その信号が出ると、心に快感、落ち着きが生まれます」(山鳥重『「わかる」とはどういうことかー認識の脳科学』ちくま新書)
人間にストーリーという認知フォーマットがあることで、因果関係を読み込んで「わかった」と納得し、心を落ち着かせることができる。なるほど、もしこの機能が存在しなければ、人間がろくに社会生活を営むことも難しいでしょう。まるで人間が、他人やじぶん自身の納得を呼び起こす、完成度の高いストーリー作りに汲々とする存在に見えてきます。しかしながら、この「わかる」という感じ、ストーリーの滑らかさを求めるがゆえに、人は「ただの前後関係」を因果関係にこっそりスライドさせたり、強引な説明で「わかった気になる」危険性もあるのだといいます。納得して快感と落ち着きを得られるのなら、因果関係は別に真実でなくていい、真っ赤な嘘であっても一向にかまわないというわけです。ひいては、ストーリーが大きな苦しみを生み出すもとになる場合だってあります。

不適切な一般論=信念が苦を増幅させる
仏教でも「人生は苦であり、不本意なことに満ちている」と教えていますが、人間は特に不本意なできごとに出会うと「なぜじぶんは不本意な状況にあるのか?」と問うて、その理由を知ろうとします。思い通りに目的を達成した場合、誰も「なぜじぶんは思い通りに目的を達成できたのか?」とは問いません。誰しも不本意なことは嫌いですが、それはそのできごと自体が嫌いだというよりは、そこに納得できる理由がないことが嫌いなのです。すると不本意なことには、なにかしら納得できる因果関係があったほうが都合が良いということになります。
なぜ、この私がこんな目に合わなければいけないのか? 不本意な状況から生まれる問いに、皆さんならどのように対処するでしょうか。たとえば「じぶんはいつもうまくいかない、そういう星の下に生まれたのだ」というストーリーで納得するのもひとつですし、「じぶんが不本意な状況にあるのは、特定の人たちに有利なように世の中が設計されているからだ」というように、特定の人たちを敵とみなして怒りを掻き立てるストーリーで納得するのもひとつの道です。どんなストーリーであったとしても、「わかった」という感情を得ることは麻薬的安心につながります。不本意なできごとによって既存のストーリーに引き起こされた気持ち悪さは、良い具合の結末に向けて解消されなければならない。たとえ原因を捏造してでも納得のいく落とし前をつけようとする心の動きを、著者は「感情のホメオスタシス(平衡状態)」と名付けています。
勧善懲悪のストーリーが典型ですが、物語は道徳感情と結びつきやすいものです。納得のいく落とし前をつけるために、人は不本意なできごとを起こした存在の責任を問い、その存在に報いを与えたくなってしまう。要するに「正しい人には常に正しい評価があり、悪い人は常に罰せられるべきである」というわけです。残念ながら、そんな単純なストーリーは稀にしか実現されず、特に理由のないできごとだって人生には突然起こりえるわけですが、それがじぶんにとって不本意なできごとだった場合、その理由のなさをそのまま認めるのは難しいものです。すると私たちはつい、誰か責任をなすりつけられる悪い原因を作り出そうとしてしまう。先ほどのように「~であるべき、~すべき must」という過度な一般論を採用すれば、その枠に当てはまらない他者の存在を否定することができ、じぶんの既存のストーリーを一時的に安定させることは容易になります。
「~であるべき、~すべき」という過度な一般論は、つまるところ「人は私が欲するとおりに行動すべきである」という主張にまとめられる、と著者は書きます。既存のストーリーを守ろうとするあまり、他者をコントロールしようとする欲求が根っこにあるわけですが、しかしながら「私が欲するとおりに行動する他者」というのはまず存在しません(「私が欲するとおりに行動しているふりをする他者」はたくさんいますが)。こうした不適切な一般論=信念をじぶんのストーリーに採用することで、必然的に不本意なできごとに遭遇し、怒りの感情を覚える機会は増えていきます。皮肉なことに、不本意さを解消するために取ったはずの手段が、じぶんの苦しみをさらに増幅させつづけるわけです。
お気づきのように、物語論による著者のこうした考察は、苦を滅却する道を説く仏教のおしえに重なってきます。『人はなぜ物語を求めるのか』の後半で、ストーリーを不適切でなく書き変える手がかりとして、やはりブッダをはじめとする仏教の話題が登場する所以ですが、それについては次回触れることといたしましょう。ここまで『人はなぜ物語を求めるのか』の議論をまとめてきましたが、この要約も私のストーリーにとって都合の良い因果関係を捏造し、都合の悪い部分を捨象しているかもしれません。ご関心を持たれた方には、ぜひ直接本書を手にとっていただけたらと念じています。
人間は生きているとストーリーを合成してしまう。納得感のある滑らかなストーリーを書き上げるべく、それと矛盾するような無数のできごとを隠蔽しながら、私たちは生を送っています。とはいえ、そうして無数のできごとが隠蔽されているということは、逆に言うと、いまだ語られていないストーリーがありえるということ、私たちのストーリーが常に変わりうる可能性を示してもいます。それでは、仏教の思想と実践は「物語る動物」としての人間の性質にどう関係するのでしょうか。そのような限定された視点から、次回は初期仏教を見つめてみようと思います。
✳︎冒頭写真:mgr allergen0024 インスタレーション「(circle)」@浄土宗應典院
[amazonjs asin=”4480689796″ locale=”JP” title=”人はなぜ物語を求めるのか (ちくまプリマー新書)”]