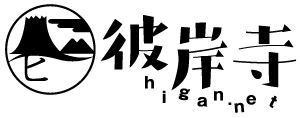あれは小学校何年生のときだったんだろう? 母の日に青い花の鉢植えをあげたことがある。花の色に惹かれたし、何より子どもに買える値段だった。
「みやこわすれ、っていうんよ。きれいねぇ」
母は、花の名前をよく知っていた。梅、ユキヤナギ、桃、海棠桜、八重桜、山吹、バラ、紫陽花、凌霄花、金木犀。庭には、母が好きな花がいつも咲いていた。「逝ってから、お母さんが好きだった木が次々にダメになる」と父は言う。やかましいほどに咲いた3本の八重桜も、今年ついに最後の1本が枯れてしまった。あんなに好きだと言っていたハナミズキも。「お母さんがみな持っていってしもた」と父は苦笑いをした。
「恭子のクレマチスも、枯れそうやったけど今年はたくさん咲いたよ。色はまだまだ薄いけどなぁ」
東京で暮らしていた頃、母の日にクレマチスの鉢植えを贈ったことがある。母は、とりわけこの花を気に入って「恭子のクレマチス」と呼んでいた。あのクレマチスも、母の死後は花をつけなくなっていたのか。父は、冬の間にひょろっと茎だけになったクレマチスの土を変え、肥料を与えて春を待ったという。
そこまで聞いて、ようやくハッとする。庭の木は、母が持っていったのではない。母を失い、父の気持ちが庭から離れていたから枯れていったのだ。
父は、母亡き後の暮らしを「全然さびしくない」と強がる。話したくなれば遺影に話しかけるし、日によって遺影の表情も違っているのだ、と。「お線香あげるの忘れた日なんか、ちょっと拗ねた顔しよるねん」とやや得意げな口ぶりで話す。父のなかには、いなくても会話できるだけの、母の面影がたっぷりと生き続けているのだろう。
しかし、意地の悪い娘は思う。お父さんは、お母さんのことを都合よく編集しているんじゃないの、と。亡くなる前の数年間、そんな穏やかな会話があなたたち夫婦の間にありましたっけ?という気持ちがむくむく湧いて、つい言ってしまう。
「もしも、亡くなる直前まで元気で、昔みたいにお父さんのお世話をパーフェクトにしていたら、もっと寂しかったかもね」
ふっと火が消えいるように、父は口をつぐんだ。晩年の母のことを、父は今どう思っているのだろう。一番ちかくで寄り添い、介護をしていたからこそ、味わっていた非常な苦しみと一緒にまるめて、認知症が進行していった母の姿も忘れようとしているのだろうか。母の言動にいちいちイラつき、声をあらげ、たびたび手を上げていたことも。
いやいや、状況を知りながらも同居をせず、仕事の合間にしか顔を出さなかったような私こそ、両親を苦しめたのだ。つらいことを忘れようとする父に、「事実はそうじゃないよね?」と突きつけるべきではない。父と娘のあいだに、感情を消した、無色透明な時間が流れていく。
生者は、死者との関係性を一方的に決めていいのか?という思いが、わたしにはある。
母が脳死状態になったとき、病院に駆けつけた親戚や母の友人たちは、それぞれの母の思い出を語ってくれた。ぐにゃりと横たわる母のうえに、関係性にのこる記憶が映し出され、一人ひとりのなかにいる母が立ち上がっていく。その語りのなかで、わたしと姉もひさしぶりに「元気だった頃のお母さん」のことを口にするようになった。
ただ、こちらの都合のよい「お母さん」を思い描くのは違うと思っていた。それに、生きている間は直接触れることで、まだ母の存在は確かだった。髪を洗ってあげたり、清拭したりすることを通して、あるいは直接話しかけることによって、母とコミュニケーションしている感覚がちゃんとあった。
むしろ、わたしが「どのお母さんを思い出せばいいのか」を悩みはじめたのは亡くなった後だ。母とのやりとりが遠ざかると、「もう、元気だった頃の母だけを思い出してもいいかな?」と甘えるような気持ちが出てきた。あるいは、母にしても「そんな、認知症になってからのことなんか言わんといて」と言うんじゃないかと考えてみたりもした。
葬儀から一年が過ぎた頃からだろうか。ごく自然に最晩年の母に語りかけるようになったのは。
確かにつらいこともあったし、めちゃくちゃなことを言われたこともあったけどーーやっぱり、会いたいのは最後の日々の母なのだった。古い記憶から死ぬ直前の母までを、ひとつながりの人生として受け入れられるようになったのかもしれない。「お母さん、認知症のまま出てきてかまへんよ」と言ったら、大阪のおばちゃんらしく、わたしの肩を突いてころころと笑うだろうか。
生と死を分けたことによって、この世では受け入れられなかった苦しみを、ゆるされることもあるのだと思う。ただ、死者との関係性のつくりかたに投影されるのは、この世における関係性でしかない。どんな風に死者を思うかということは、他者と共にどのように生きていきたいかということにそのまま接続している。
わたしは、これから自分が死ぬまでずっと、へろへろな母と生きていたい。