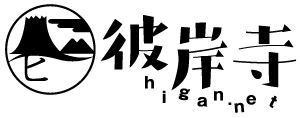母が救急搬送されたのは、2017年9月14日の午後だった。グループホームから一時帰宅した際に、フルーツ大福のぶどうを喉に詰まらせて窒息。救急措置により心臓は動いたが、ついに脳の機能を回復させることはできなかった。
病院にかけつけたとき、母はぐにゃっと横たわっていた。
母の髪や身体に触れる。言葉は出ず、涙だけが落ちた。
手を握ると、指の間に大福のかけらがくっついて乾いている。頬には血の跡もまだあった。看護師さんに清拭用の温かいタオルをお願いする。「明日になれば、髪も洗えますよ」と言ってくれたが、どうして明日までこのままでいいと思えるだろうか。「恭子、はよ拭いて」とベソをかく母の声が聞こえる気がしていた。
病院では、最後の望みをかけて脳低温療法を施してくれたが、ついに回復はなかった。私たちにできることは、ただ母のそばにいることだけ。そんななか、母の身体を拭いて髪を洗い、お化粧をしてあげられることが本当にうれしかった。髪を整え終わると、母の表情が少し柔らかく、気持ち良さそうに見えるのだ。ずっと、お母さんにはしてもらうことばかりを求めてきたけれど、「してあげられること」がある有り難さを噛みしめていた。
人間の機能のなかで、最後まで残るのは聴覚だという。
「脳死状態であっても、聞こえているかもしれない」という医師や看護師もいる。私はそれを信じて、ずっと母に話しかけていた。泊まりの夜には、今まで言えなかったことをたくさん話した。病室に来てくれる親戚や母の友人にも「聞こえていると思いますから」と伝え、「お母さん、○○さんが来てくれたよ」と取り次いだ。
「カヨちゃん、来たよ」
「がんばらなあかんよ!」
母の手を握りやさしく語りかけてくれる人。おそるおそる近づいて変わり果てた母の姿にそっと視線を投げるだけの人。母の完全な沈黙を前に、かえって母とその人の関係はあらわだった。
親しい人たちは、母と過ごしてきた日々の思い出を話してくれた。母の兄姉が数人いると、祖母の家での集まりみたいに陽気な会話が始まる。すると、寝ているはずの母が話の輪のなかに“いる感じ”がした。母が笑って「そんなん言わんといて!」と兄や弟の腕をこづく姿もありありとわかる。
お見舞いの人たち同士は、初対面であっても母を介して話が弾む。その場にいるといつも“母がいる感じ”を味わった。幼い甥や姪をかわいがっていたという若い母、友人たちとコーラスの練習に励んでいた母の姿もあった。グループホームで仲良くしてくれたスタッフの方達が来ると、つい先週に会った母がそこに”いる感じ”もした。
もの言わず横たわる母と、語りのなかに生き生きと立ち現れてくる母。
人は、いまここに生きている“自分”を、確固たる存在なのだと信じている。だけど、もの言わぬ母と語られる母の間で揺られて過ごすうち、人間の半分(あるいはそれ以上)は、誰かとの間で共有されているのだと思うようになった。きっと、母が逝ってしまっても、みなと共有してきた母はこの世に残り続けるだろう、と。
それと同時に、自分以外の誰かとの関係の上に成り立っている「私」という存在、思いおよばぬほどに他者に共有されている「私」についても思いを巡らせるようになった。「私」という存在の頼りなさ、ままならなさ、そして死してなおある確かさ、と――。
仏教では、「永遠に変わらず、独立的に自存し、中心的な所有主として支配能力があると考えられる霊魂的あるいは本体的実在」を「我」とし、すべてのものに「我」はないと「諸法無我」を説く(*)。
自分にとって唯一無二の母がこの世からいなくなることは、とてつもなく寂しく不安なことには違いなかった。そんなとき、膝の上にのせていた「諸法無我」という言葉が、母にしがみつく指をゆるめるように促してくれていた、と思う。
*法蔵館「[新版]仏教学辞典」による。