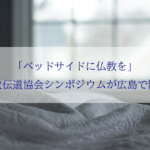夏が近づくと、子どもの頃に住んだ青い瓦屋根の家を思い出す。
お勝手から外に出ると、簀の子を敷いた土間に洗濯機があった。当時の洗濯機は二層式で、「洗い」が終ると洗濯ものを脱水槽に移さなければいけない。夏休みの朝、わたしの仕事は「脱水係」だった。「洗い」が終るときだけ手を出せばいいのに、洗濯槽にもくもくと立つ泡を眺めたり、すすぎの水に手を浸すのが好きでずっと洗濯機に張り付いた。
洗濯といえば、「毛布洗い」も夏休みのお楽しみだった。
家族全員の毛布を集めて、浴槽に放り込んで足で踏んで洗うのだ。このときばかりは、お風呂を泡だらけにしても、毛布の上で飛んだり跳ねたりして洋服を濡らしても叱られなかった。最後には、母も一緒になって冷たい水に足をつけ、重たくなった毛布の水気を絞って干した。
専業主婦だった母は、家族の衣食住をこまめに整えてくれた。家計のことも、夏休みの旅行も、父の身だしなみのことも、すべてのことに心を砕いていることは、幼いなりに理解して尊敬していた。
明るく面白い母ではあったが、子どものしつけにはなかなか厳しかった。毎日部屋を片付けないと叱られたし、キライなおかずを残そうとするとテーブルから下ろしてもらえなかった。怒った母は恐かったけれど、母に怯えたことは一度もない。
「あたかも、母が己が独り子を命を賭けても護るように、そのように一切の生きとし生けるものどもに対しても、無量の慈しみのこころを起すべし」(中村元訳『ブッダのことば―スッタニパーター』岩波文庫, p38)
子どもの頃の母は、まさに無量の慈しみをもって、命を賭けても姉とわたしを護ってくれる存在だった。今でもときどき、記憶のなかの母に甘えようと、手を伸ばすことがある。あんな風に、自分を慈しみ護ってくれる人が、今もいてくれたらどんなにいいだろうか、と。

新潟・小千谷に極楽寺というお寺に、麻田弘潤さんというご住職がいる。
麻田さんは、2004年に発生した中越地震の復興イベント「極楽パンチ」を、10年以上にわたって開催しつづけている。近年は消しゴムはんこ作家・津久井智子さんとのユニット「諸行無常ズ」の活動など、“消しゴムはんこのお坊さん”として知る人も多いかもしれない。
はじめて麻田さんに会ったのは、イベント取材と麻田さんへのインタビューのために訪れた2012年の極楽パンチ。以来、なぜだか気が合ってなんだかんだとおつきあいが続いている。この夏は、「盆参永代経法要」というお寺の大切な行事にわたしを招いてくれた。法要のあとに開かれる「いのちのつどい」でこのエッセイで書いているようなことを話してほしい、と言うのだ。
永代経法要のお話は、ふつうはお坊さんがされる。最初は「わたしなんかでいいのかな」と尻込みしたが、「この法要にお参りされるのは、誰かを亡くした経験のある人たちだから」と説明されて引き受けることにした。
前半は、自己紹介を兼ねて「なぜお坊さんにインタビューをするようになったのか」を話し、後半は母を亡くすプロセスのなかに見出した仏教のはたらきを話した。みなさんが、きゅーっと集中して耳をひらいてくださったのは、変わりゆく母をどう受けとめていたのか、わたし自身の体験を語っていたときだったと思う。
実際にどんな言葉で話したのかはさだかに思い出せないので、前回の記事から要約して引用する。
「以前のお母さんはこうだった」とか、「もともとお母さんはこんな人じゃなかった」と過去と比べている間にも、母はどんどん先に行ってしまう。今この瞬間にありつづけるのは本当に難しい。うつ病でも、認知症でも何病でも、お母さんはお母さんだ。「今、この瞬間を母とどう過ごすのか」ということだけを見ているほうがいい。そう思えるまで、数えきれないほど「なんでなん?」という思いが湧いたし、言葉にして母にぶつけてもいた。
プロジェクターで元気だった頃の母の写真を映しながら、「なぜ、友だちのお母さんは元気なのに、わたしのお母さんはこんなことになっちゃったんだろうと思った」と口にしたとき、不覚にもポロポロと涙がこぼれた。ああ、わたしはまだそのことに傷ついているのだな、と思う。
それはさておき。

実は、母の晩年において、わたしはずっと麻田さんの言葉を心の杖にしていた。少しずつでも、「今この瞬間を母とどう過ごすのか」に目を向けられたのは、麻田さんのおかげだと思っている。そのことを、麻田さんのお寺のお檀家さんに伝えることができたのはとてもうれしかった。
少し長いけれど、そのフレーズをここにも引用したい。
僕は「おばあさんは”できない”人だから手伝ってあげている」という感じでいたんですけど、「できる/できない」の判断はすごく自分勝手なものだったんだなと思ったときに、初めて習ってきた仏教がストンと落ちたというか。僕はたまたま身体条件が洗い物をするのに適しているだけに過ぎなくて。いろんな要素によってたまたまこの状態になっていて、そのおばあさんはまたいろんな条件が重なって認知症になっている。でも、おばあさんに「僕」という条件がひとつ加わるだけで、「洗い物ができる」状態になりますよね。
そう思うと、「できる/できない」は、実はものすごく些細なことだなと思えたんです。そうすると、阿弥陀さまの「誰もを認めていく」という教えってすごくいいなあと思えたし、仏教だったらもっといい介護ができるんじゃないかとも思って、身に落ちたというか。そこから、介護のしかたもすごく変わりました。
新しい本堂スタイルに挑戦の巻/極楽寺 麻田弘潤さん(2/3)
母の「できない」を「できる」にする“条件”でありたいと願い、母の身心と自らをつなごうとした経験は確実にわたしを変えたと思う。今のわたしは駅のホームで白杖を持つ人がいたらふつうに声をかけるし、段差のある場所に止まっている車椅子を見たら「押しましょうか?」とたずねる。以前はためらって足がすくんだのに、今は考える前から身体がそこに向かう。母の身心が私をそのようにした。こうして言葉にすると、とても些細な変化のようだけれど。
わたしの話を聞いた麻田さんはボソボソと言った(お経を詠むとき以外は声が小さい)。「介護やってて思ったのは、こっちが何かしてあげてるだけじゃなくて、こちらも育ててもらっているということだったんですよね」。そうか、母は今も私を育ててくれているのかな、と思うとまたホロリとしてしまった。
母とわたしの関係性は、会えなくなった人たちとわたしとのご縁はいつまでもつづくし、ずっとわたしにはたらきかけている。麻田さんの言葉が、6年間ゆっくりと静かにわたしにはたらきかけつづけてくれていたように。