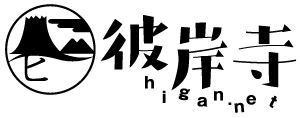考えてみれば、わたしたちが人生で求め続けるものは自分自身への深い納得であり、うなずきにあるのでしょう。
(『民衆の中の親鸞』平野修・浄土真宗僧侶)
香川県にある西蓮寺(浄土真宗本願寺派)の編集部に勤めている小西慶信です。前回は編集部が発行している布教しない仏教マガジン『 i (アイ)』に触れつつ、そこで関心を寄せてきた生きづらさについて簡単に紹介しました。今回は、本誌が創刊当初に企画した「生きる上で必要な素養とは」、「どうやって生きてく?」の特集にまつわる話をしたいと思います。
仕事、家族や友人関係など、わたしたちの生活は必ずしも思い通りにいくことばかりではありません。場合によっては、単に不運だとか失敗したという言葉におさまりきらないくらい深刻で不条理なこともあります。では、そのような思い通りにいかないことと、わたしたちはどう向き合うべきか。はたまた、思い通りにいくことばかりじゃない現実で、どうすれば後悔なく生きていけるのか。それを読者の方と話してみたいと思い、少々大それた特集を企画することになりました。
◼️宗教に欠かせないもの
ところで、基本的に宗教というのはある種の自己否定を伴います。仏教も例外ではありません。もし仮に、自分が信じる正しさの保証や願いの実現が救いであるというならそれは単なる個人的な満足にすぎません。そのような願望の起点にある自己そのものが問われ、転じられることで、はじめて絶対的な安心(頷き)が得られます。
たとえば、わたしが所属する浄土真宗の宗祖、親鸞聖人は他力をキーワードとして人々の苦悩に応答しています。しばしば親鸞は修行を否定したと言われますが、個人的には、修行というものを成り立たせている心理的な枠組みを否定していると言った方が適切な気がしています。つまり、将来の目的を達成するために現在を差し出すという「取引(自力)」の枠組みです。
そもそも親鸞は、従来の経典の読み方を意識的に踏襲しなかったことが知られています。普通、「南無阿弥陀仏」と口にするとき、念仏を称える主体は、それを口にした本人に他ならないわけですが、親鸞はその念仏を阿弥陀仏が称えさせたと解釈します。また従来の念仏には、他の行と同様に、極楽浄土を思い描くなどして往生を遂げるといったような目的が、当然想定されています。しかし、他力の念仏観によれば、念仏を称えるわたしを、その主体の座から引きずり下ろすわけです。すると、その念仏は、わたしが往生するために行う念仏ではなくなることになり、目的を消失します。そのため念仏の回数や質が問われる必要性もなくなり、目的に規定されることさえなくなります。それは、もはや自分自身が納得を得られたかどうかを問う必要のない、融通無碍な行為となるわけです。
しかし、こうした仏教観を知って「なるほど、じゃあ良かった」とはなりません。少なくともわたしはそうでした。というのも、わたしが現実に直面している問題を、仏教が解決してくれるとは到底思えなかったからです。
◼️大人になるということ
思えば、わたしは6歳ころから「自由に生きたい」という思いを自覚してきました。というのも、わたしはもともとお寺生まれで、一般的に長男がお寺を継ぐことが当たり前だとされることが多く、例に漏れずわたしもその立場にあったことが、その一因です。
小学生の頃、将来の夢を書く機会が何度かありました。なりたいものを自由に書いていいと言われながらも、将来を自由に考えるのはダメなことなんだという背徳感を感じていました。将来が出自によって規定されてしまうことにどうしても納得がいきませんでしたが、その気持ちとどう折り合いをつければいいのか、当時はわかりませんでした。
ただ、進学を機に地元を離れて生活するようになると、その悩みがひどくバカらしく感じるようになりました。親元を離れたこと以上に、自分自身にまつわる選択の意思決定の訓練ができたからかもしれません。
例えば、大学でどういう講義を受講するか、何を研究テーマに据えるかを決めるためには、自分が何に興味を持っているか、あるいは将来どんなことをしたいかという自分自身の欲求に自覚的にならなければなりません。また、わたしが大学に入学したのが3.11の直後だったこともあってか、社会活動に積極的に関わる学生が多く、ギャップイヤーを取って校外活動に取り組む人たちも少なくありませんでした。そういう人たちの影響を多分に受けてか、いち個としての自分が社会にどう関わっていくかを絶えず問われるような経験が得られました。
最近読んだコラムの中でこんな一節を目にしました。曰く、
他人(あるいは世間)が課してくる義務を履行し続けることで「世間」における身を保つこと(=他律)は子どものあり方である、と。他方、個々人が自身の幸福を己の責任で追求する営みを通じて、「個」や「わたし」を確立し、「公共」へと参画していくのが大人である。
(「私たちは幸せになるために生まれてきたはずだった」ニー仏・note)
幼少期の苦悩がひどくバカらしく思えたのは、おそらくそれがここで言われる子どもっぽさそのものだったからです。「そうだ、わたしはひとりの“大人”として生きていいはずだ」という、当時の心情が改めて言葉にされた気がして思わず膝を打ちました。
◼️生の一大事か、生死の一大事か
さて、改めて考えてみますと、長らくわたしにとっての喫緊の問題は、他者の期待や周囲の規範とどう向き合うかにありました。息苦しさや苦悩のリアリティは、わたしを取り巻く人間関係や環境にあり、ままならない現実の中で、いかにして自分自身に納得のいくような選択や結果を得られるかにわたしの関心だったと言えます。その点、ここで述べた過去の経験については、試行錯誤を経て自分なりに納得のいく結果が得られたような気がしています。
ところが、「わたしたちが人生で求め続けるものは自分自身への深い納得」にあると述べた平野は、次のように問いかけてもいます。
自ら納得しようとして計らい、そして計らって納得しようとするありさまは、結果にかかわらず、それ自体が、われわれの不安の叫びなのではないか
(『民衆の中の親鸞』平野修)
と。この問いかけが、妙に胸に残り続けています。
そもそも仏教が扱うわたしたちの問題とは、「生活上の諸問題」ではなく「生死(しょうじ)の問題」であると、しばしば言われます。それは、日常に起こる不都合なことや受け入れられない出来事を問題として扱うのではなく、都合の良し悪しを生じさせる源泉としての、言い換えるならば、頷きを求めてしまう存在としての“わたし”そのものを問うていく発想でした。
しかし“わたし”そのものを問うと言っても、現実の生活ではそう簡単に割り切れないことが多いのも事実です。そのアンバランスな立場から、日常生活の中で直面する困難や葛藤、そして他者との関わりの中で感じる不安や苦痛をどう語ることができるのか。次回からは、より具体的な話題を提起しながら、身近な生きづらさを扱っていく予定です。
ーーーーーー
参照:
『民衆の中の親鸞』平野修、東本願寺出版部 (1991/4/15)