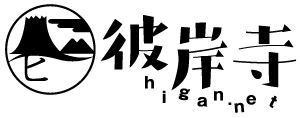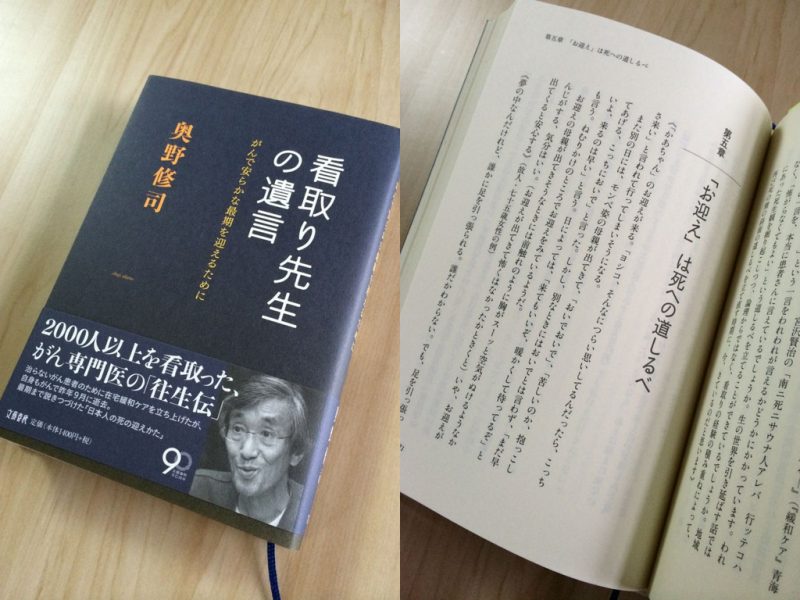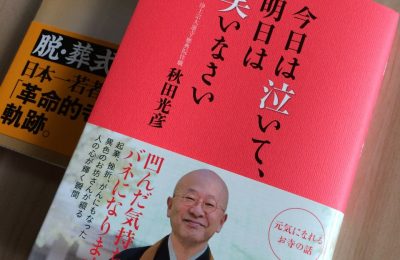余命が限られた終末期を自宅で過ごしたい人は80%、しかし現実には病院で死を迎えるだろうと考えている人はその内の60%。あるアンケート結果ですが、多くの日本人の感覚を表しているのではないでしょうか? 国が医療費削減を目的に病院死から在宅死へ大きく舵を切り、在宅で看病し、介護し、看取るという流れが加速しています。しかし医療者や家族がどのようにして患者を看取るかという死生観が欠落し、患者本人や家族の不安を受け止める経験も地域の文化も消失しています。かつては地域に根ざしていた看取りの文化が、ここ30年ほどの間に完全に忘れ去られてしまったからです。
宮城県の岡部健医師は呼吸器外科医としてガンを治療しながらも、治せない多くの患者に出会う内に病院での治療に限界を感じました。そこで終末期のガン患者を中心に、在宅緩和ケアをする岡部医院を設立。ガン患者を在宅で看ることは不可能と言われた当時から、一人でも多くのガン患者の「住み慣れた自宅で死にたい」という願いを叶えるべく奮闘し、在宅緩和ケア専門の診療所としては国内トップクラスの看取り数を誇るようになりました。しかし岡部医師自身にガンが見つかり、余命10カ月と宣告されるという事態に。本書は、看取る側から看取られる側になった岡部医師の遺言とも呼ぶべき記録です。
岡部医師がいざ死んでいくにあたって、どのように闇の方に降りていけばいいのか、その「道しるべ」がないことに愕然としたという述懐に、宗教者はいかに答えられるでしょうか。「死への道しるべ」を示すには医療者と宗教者が協力する以外に方法がないと岡部医師は考え、宗教者が在宅緩和ケアに関われるように日本版チャプレン(病院やホスピスなどで活躍する聖職者)ともいえる『臨床宗教師』の誕生に全精力を注いだことも宗教者は忘れてはなりません。さらに、死に瀕して患者が「お迎え」体験によって穏やかな最期を迎えることに注目し、アンケート調査を通して正面から「お迎え」現象の研究をしたことも宗教者は頭が下がる思いです。特に僧侶はつい最近までお年寄りから頻繁に耳にしていた「お迎え」の言説を受け止めつつも、対外的に公表して社会にその価値を還元してこなかったことを反省すべきではないでしょうか。
病状が進む中でも岡部医師は舌鋒鋭く医療界や社会保障制度の問題点を指摘しますが、同時に宗教者にも「もっと死の現場に入ってこい」と発破をかけているように思えてなりません。日本人の「あの世」観と倫理観が宗教的基盤に支えられていることを自覚し、宗教者は臨床の現場で恐れずに死を語り、患者と「お迎え」や「あの世」を共有すべきという提言を肝に銘じる必要があります。古くて新しい「お迎え」現象を看取りの現場に取り戻し、日本人伝統の死生観を再構築する役目を宗教者が担う。そうなれば在宅死が患者本人や家族に無理な負担を強いることなく、当たり前の最期になる。それこそ岡部医師が命をかけて私たちに遺したメッセージです。
岡部医師の悲願であった『臨床宗教師』が東北大学で寄附講座としてスタートし、既に修了者が各地で活躍し始めています。本書を手にした多くの人が手を携え、一人でも多くの患者が「死への道しるべ」を得ることを願ってやみません。一般の方や終末医療に携わる方はもちろん、宗教者にとっても必読の書です。ぜひご一読ください。