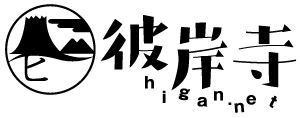2017年9月26日の朝7時頃、母は心臓を止めた。
急の知らせに家を飛び出したが始発には届かず、一本後の電車で病院に駆けつけたとき、母の身体はまだ温かいのに唇からは血の色がまったく抜け落ちていた。母の容態を知る唯一の手がかりだったモニターの波形は平たくなり、絶望のラインを超えている。
「朝7時頃」というのは、父や親戚、そして病院のスタッフのみなさんが、私が母に触れる瞬間までは臨終の宣告せずに待っていてくれたから。
「紅顔むなしく変じて、桃李の装いを失いぬるときは」
蓮如上人の「白骨の御文章」の一節がよぎる。本当にそれは、むなしく変じた母の姿だった。「お母さん、よくがんばったね。ありがとうね」と声をかけた。母が脳死状態になってから12日が過ぎていた。
アイルランドの言葉、ゲール語では通夜を「wake」といい、埋葬の前夜に人々は集まって死者のことを語らって楽しく飲み明かすそうだ。また、英語の「wake」は「軌跡」「余波」「結果」などを意味する名詞としても使われる。
私のなかで、母の死による余波はまだ続いている。ビリー・ホリディが歌った「These Foolish Things(Remind Me of You)」ではないけれど、ぼんやりしていると目に映るすべての、ほんとうにどうでもいいようなことですら、母の記憶につながっていく。親しい人といると、つい母を語ることが多くなる。
まるで、この世のすべてと母について語らっているようだ。ときに楽しく懐かしく、ときに引き裂かれるような後悔や、自責の念にさいなまれながら。それは、私にとっての「wake」なのだと思う。
いつもは、ライターとして、他者の語りに耳を傾けてその思いを言葉に紡ぐ。でも今は、この世の事物との交感において紡がれてくる、胸のうちの言葉に耳を傾けてみたいと思う。また、近親者の葬儀を通して出会ったお寺と仏教は、私が親しんできた仏教(*)とはまったく違っていた。初めて出会う「家の宗教」としての仏教についても、感じたことを書き留めておきたい。
*彼岸寺で連載したお坊さんインタビュー「坊主めくり」では、お坊さんたちに個人として出会ってきた。また、友人となったお坊さんたちとは「ひとりの仏教者」として、互いに模索する仏道について共に語らってきた。そのようなフラットな関係しか知らなかった私にとって、檀家制度の内側に巻き込まれることは非常に興味深く、驚きも大きかった、ということです。詳しくは、次回以降の記事にて書きます。