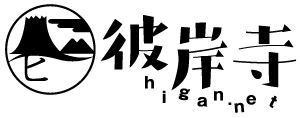- 私が秋田さんに出会ったのは、学生時代に見た映画『狂い咲きサンダーロード』を通してです。後に、友人から「大阪に『呼吸する寺・應典院』オモロい寺がある」と教えてもらって、そのお寺の住職が秋田さんだとわかったときは本当にビックリしました。今回のインタビューでは、秋田さんの映画プロデューサー時代、お寺に戻られて自らの立ち位置を確立し、應典院を若いアーティストたちの寺にしようと構想されるまでのこと、そして再建から13年後の應典院を秋田さんがどう見ておられるのかについてをじっくり伺いました。
映画とともに80年代を駆け抜けて
——最初に映画に触れられたのはいつごろだったんですか?
父が映画好きでしたから、小さい頃からよく連れていってもらってたんです。黒沢明の『天国と地獄』や『赤ひげ』も小学生の時にリアルタイムで見ましたね。当時は、映画はたいてい二本立て上映ですから、行けば4時間近く過ごせるわけです。映画館は、僕にとって唯一の憩いの場でした。高校時代は、映画サークルに入って年間200本以上見てましたよ。
高校を卒業すると東京の大学に進みました。シナリオを勉強して身を立てるんだという思いを持ってね。当時の東京は、学生運動の火は消えていて、大学へ行っても何の刺激もない。だから、学生が集まれば麻雀か自主映画だったんです。そこで、大学を超えて連携する映画サークル『狂映舎』に参加して、そこで石井聰亙という凄い才能に出会うんです。
——石井聰亙監督の初期名作『狂い咲きサンダーロード』や『爆裂都市 Burst City』で脚本とプロデュースをされていましたが、当時、映画を通して表現したいテーマは、どんなものだったんですか?
あの2作品は石井聰亙の感性ですね。当時、石井は自分でシナリオを書かなかったから、彼のモチーフを聞き取りながら僕が代筆していたという感じです。いずれも映画としては素晴らしい作品だし、『爆裂都市』なんて20年早かった。でも、あの映画は僕の感性ではない。
——両作品とも、「とにかくどこかへ突き抜けよう、走り抜けていこう」というイメージが非常に強かったです。すごくスピード感があって。

映画『狂い咲きサンダーロード』DVDジャケット
それは僕たちの共通項です。今は、若者中心にマーケットが動いていくのは当たり前のことになっていますが、若者たちを初めて「消費者」としてとらえて餌付けしていったのが70年代後半から80年代にかけてのバブル前夜の頃。そんな時代の雲行きに、不満や衝動、抑制できない暴走を抱えていました。 60年代から続いた政治の季節は終わり、当時の若者に流行っていたのは無気力・無感動・無関心の「三無主義」。一切の情熱を表さない時代の気分を、なんとか祝祭的なものに持ち込もうとしたのが新しい企業文化だったんだと思います。映画でいえば、角川映画の登場です。僕らの映画は、80年代のどうにもならない時代のベクトルに乗り遅れたかのごとくずっとイラついていた。強烈な違和感とともにね。 だから、なんとか体制には頼らずに、自分たちの手で作った映画で食っていくということを実現しよう。配給から宣伝、上映運動まで全部やりましたから。インディーズの原型のようなものを自分たちで切り拓いたという自負はあるんですね。そのときに一緒にやっていたのが情報誌の『ぴあ』です。だから、僕は『ぴあ』でも仕事していました。もうみんながとんがっていて、貧乏でしたが「俺たちが時代を変えて行くんだ」という野心だけは燃え立っていました。
人生のどん底に響いてきた父の言葉
——その頃に作られたのが『狂い咲き』ですね。
自主制作した『狂い咲き』は、大ヒットしてメジャー公開されて。「これからは映画だけでやって行こう」と、『ぴあ』もやめて、作った『爆裂都市』が全くヒットしなかった。『爆裂都市』は事業としてやっていたから、予算が尽きたらフィルムも買えなくなります。それでも、映画が当たればすべてはチャラだったんですけど、興行的に失敗したら残るのは借財、しかも若者が背負うにはあまりにも大きな借財だった。残念ながら、映画に自爆したわけです。それが26歳か27歳の頃ですね。
でも、お金のことよりも人間関係がズタズタに切り裂かれてしまったことが、いちばん大きなショックでした。若さゆえの無理解や誤解がたくさんあって石井とも別れましたし、周囲にいた大人たちも手のひらを返したように裏切って去っていきました。
そんなときに父が上京して「おかげさまできたんだから、おかげさまを返さなければいけない」と。不思議なもので、それまで寺の息子として吹きこまれてきた言葉なんて、馬耳東風で体に入ってこなかったのに、ボロボロになっているときには同じ言葉がすーっと落ちてきて。「ああ良かった、自分には帰るところがあるんだぁ」って思いました。父は、いいタイミングで来てくれて、僕が離脱していく道筋を上手に作ってくれたのかもしれませんね。
——でも、その後『アイコ16歳(今関あきよし監督/富田靖子主演』のようなヒット作も手がけておられます。もう少し、映画でがんばろう、やってみようとは思われなかったんですか?
-

應典院の階段に置かれた石のお地蔵さん
僕の独立プロとして作ったのは『狂い咲き』と『爆裂都市』の2作品だけで、『アイコ16歳』はアミューズの社員として作ったものですから。角川映画からも誘われていましたし、居坐る覚悟があればやっていけたかもしれない。でも、人間関係はズタズタになっていたし、もう少し距離をおいて自分を見つめ直したいという思いもあって、29歳で大阪に戻りました。自主映画を一緒に作っていた仲間たちから見れば、僕はそれなりのものでしたから、みんなに言われましたよ。「お前は裏切るのか」ってね。 僕はある意味ではどこかで敗北した。それは、僕の強烈なコンプレックスでもあるし、いま僕がやっていることの原点でもあります。
——じゃあ、お寺に戻られたときは「お坊さんになろう」というよりは「家に帰ろう」という気持ちで?
お坊さんをやるしかないかと。父も活躍していましたから、カバン持ちをやりながら好きな原稿を書いたりね。当時、僕はマンガの原作も書いていて、賞をとって100万円もらったこともあるんですよ。「マンガの原作なら大阪でもできるな」と。
ただ、帰ってきて仏教界なるものとつきあいはじめると「なんだこれは?」って感じで。それまで、映画を作っているときも、『ぴあ』にいるときも、自分の会社をやっているときも、基本的にすごく感性の高い人たちと出会っていて、時代の先っぽに自分は立っているという自覚はあったわけです。だから、旧態依然とした世界とまったくかみ合わなくてね。
このまま、適当にこなしていけば、気軽にやっていけるんじゃないか。そう思いながらも、東京で作られてきた自分の物差しみたいなものがその環境になじむことを許さない。そのズレに悩んでいる間は、ずいぶん遊んだりして不埒なこともやっていました。
すべてをそぎ落として仏と向き合えた瞬間
——自分と仏教界のズレやかみ合わなさは、どう解消していかれたんですか。
非常にオーソドックスですが加行(けぎょう)体験です。浄土宗の修行なんて、他宗派に比べればわりとインスタントなんですが、一切の俗なるものを介入させない環境で、ひたすら念仏と五体投地を繰り返すうちに、いわゆる倍音体験をするんです。自分たちの唱える念仏の声を追いかけるように、澄み切った声が降り注いできてね。
映画では「ブッ殺してやるーッ!」とかやっていたわけですよ。大阪に戻ってからは、俗なるものが取り囲んでしまった仏教に対してズレを感じてきて。ところが、削り取って削り取って最後に残った自分という存在と、仏教を取り囲む一切の俗なるものをそぎ落としたところに現れる仏という存在が対峙したときに、自分が初めて「信」なる関係に置かれたことに気づいて。もう、涙が出るくらいに感動したんです。
それで、真剣にお坊さんをやろうと思った。当時はまだ、應典院なんて構想は何もないです。ただ、真剣にお坊さんをやろうと決意しました。
——それで、加行後に『教化センター21の会』などの活動を始められたんですね。
そうです。浄土宗の有志と『教化センター21の会』を立ち上げて、葬儀や後継者など現代仏教の問題を取り上げた『現代教化ファイル』などの出版活動を始めたり、『仏教サウンド考現学』や『宗教メディア進化論』などのイベントを開いて。僕は、30代前半の頃、京都新聞では「宗教メディアプロデューサー」なんて紹介されたんですよ(笑)。「都市と宗教」をキーワードに、新宗教の人たちともどんどん付き合い始めて。社会を読むことも、メディアも好きなので、現場で勉強しながら「自分がやっていくのはこういうところなんだな」と立ち位置を見いだしていきました。
仏教界でのインディペンデントな立ち位置を
——当時、一緒に動いていたのはやはり同じ30代の僧侶の方々ですか?
-

應典院本堂のご本尊・阿弥陀如来像
お察しいただけるかと思いますが、僕のポジションはちょっと異色すぎて。育ちも違えば言葉も違うし、つきあっている人も全然違う。やはり多くの僧侶は、宗門の大学を出てそのまま地元の仏教青年会に入って、いわば純粋培養で育っていく。本人はそんなつもりはなくても、外から見ると明らかに宗派や教団のヒエラルキーの下部構造を支えている。そのなかにいたら相対的なものの見方もできなくなる。30代は、仏教界のなかにどうやってインディペンデントな立ち位置を確立するかで悪戦苦闘していました。 たまたま、宗門の上の世代の人たちに、僕の言うことややることが面白いから面倒を見てやろうとか、もがいている僕を上手に受け入れるクッションの役目になってくださった人がいた。それを見て、みんなが「何かわけわかんないけどやるらしいよ」とついてきてくれたという感じかな。20代の映画時代もそうでしたが、「君の言うことはわからない。でも、君たちのやっていることには何か可能性があるから」とポンとお金を貸してくれた人もいる。当時はまだ、大人がリスクを負って若い人を育てようという気概があったんだと思います。
——そういう経験もあって、若いお坊さんの活動が各宗派で押さえ付けられることをご心配されているんですか?
意識はしていませんが、そういうものは僕の体質のひとつになっているんじゃないですかね。たとえば、『彼岸寺』の活動もまた、教団の持つマスな力からはみ出していく力ですよね。それを吸収していく幅や深みはあるのか、あるいはある境界を超えたところで「異安心(異端)」として排除していくのかは紙一重です。でも、教団の囲いのなかから育まれて、そこに列座するだけでは面白くないですよね。宗教なるものを背負っているということは、何かの秩序・規範からはみ出しつつ、またどこかで調和されていくということじゃないかと思いますし。
反規範・反秩序となると、それはオウム真理教になってしまうので、そういうものを照射する別な力を放ちながら、僕たちの生き方や思想をもっとクリエイティブにしていくというか。違うものの見方、他者と出会うと僕は元気になりますよ。なりませんか?
——なりますね。
僕はね、「ヘンなやつ」って言われるのがいちばんうれしいんですよ。「変わったやつやなー」と言われて、たびたび元気になったし。應典院はヘンな人と出会うためにやっているようなもんです(笑)。ヘンな人と付き合いながら、僕はかろうじて呼吸を続けることができたというか。
生き方を模索する、規定の生き方に対して何かを反転させる力を持つことは、どの時代においてもすごく勇気のいることだと思うんですね。僕もその一人であって、僕がなぜもがき続けられたかというと、仲間たちとそれを支えてくれる少数の大人がいたからです。大人は社会の象徴です。でも、たとえ1000人に一人でもいいから、「間違ってない、がんばっていけよ」と若者言える大人がいるかどうかで、社会の創造力は変わってくると思うんですね。
社会の創造力を育てる存在に
——今は、秋田さんが「少数の大人」の立場で、僧侶だけでなく應典院に集まる人たちに「間違ってないよ」と。
-

應典院入口すぐのスペース。若者たちの息づかいが感じられる
そうですね。若い人の生き方に関わると言えばすごくかっこいいけど、どこかですごく重い課題を彼らと一緒に抱えながら……。何もしてあげられないですけど、ただ「この場所に来たらいいよ」とね。家庭では息苦しい、学校には居場所がない、会社にはなじまない。どこにも行き場のない彼・彼女らが、たまる場所としての寺を目指してくる。その寺が、彼らの表現や創造のために開かれていることが大事なんです。表現というのは、「最大の気づき」だと思っていますし、その場に阿弥陀さまがいらっしゃる、窓の外には無数のお墓が見えるということが重要なのではないかと思うんですよ。
——應典院の再建プロジェクトが始めったのは30代の後半ごろからですよね。
はい。30代後半から40代にかけてです。ちょうどオウム真理教の話題がピークの頃で。同じ宗教というカテゴリーの中で起きた事件としてとらえると、これまで以上に我々の在りようや立ち方を考えさせられました。應典院再建プロジェクトが立ちあがったのも同じ頃で、「寺とは何か、仏教とは何か」を考えなさいと、父は僕にこのプロジェクトを任せてくれたんです。
特に、これだけ効率を目指して、市場化していく社会のなかで、本当の意味での公益性を保ちながら、寺がこの都心に在りつづけることができるのはまさに奇跡のようですね。いつだって、ここに駐車場や葬儀会館を作ることができるけれど、そうしないでいるにはこの場所に何を埋め込んでいくのかという、強烈な「信」がなければいけないと思います。應典院は、僕にとって「ここになくてはならない」というひとつの存在証明なんですよ。
應典院は、僕自身の二つの出発点を通過して再建されています。第一の出発点は、映画で敗北したことですよね。第二の出発点は、オウム真理教事件と同じく95年に起きた阪神淡路大震災を見てしまったことです。そこで初めて「ああ、そうだ。劇場だ。NPO型の寺なんだ」という着想を得ました。
関係性を編集するメディア=應典院
——震災で死者を前に悲しむ人たちと対面することで。
本当に恥ずかしながら、40歳の手前にして人間の生死(しょうじ)なるものに出会ったという感じですね。それまでの僕は、役割や役職、制度とか、自分が位置づけられたもののなかにいて、自分の感性や思考が後付けになっていたと思うんです。寺の人間は、宗派、お寺、教区など、すべて属性で語られていますしね。
でも、震災の被災者の人は誰ひとり「あなたは何宗のお坊さんですか?」とは聞かない。「あなたはお坊さんでしょ?」と、そういう風に聞かれたのは初めてだったんですね。「私は浄土宗ですけどいいんでしょうか?」「そんなん関係ない、何でもええからお経読んでくれ」って言われてね。
ああ、そうか。僕らはもともとの出発点はソロなんや、と。でも、それは勝手にやってていいというわけではないんですよ。ソロでやるという強烈な自覚をひとつの磁力にしながら、どういうコミュニティを形成していくのか。ミッションあるいは「信」なるものが核にあり、それを具現する単独者=ソリストがいて、その人が持つ響きに応答する関係をどう多様に作っていくのか。それを震災の現場のNPO活動から学んだんです。だから、僕は「編集者」という言葉を使っています。非常に能力のある編集者であろうと。
イベントは関係性をくみ上げる「装置」
——應典院という場=メディアを編集する、編集長がご住職の秋田さんであると。
そう言われるといちばんうれしいですね。 僕は、應典院でイベントをするとき、終了後の関係作りに最大のエネルギーを使っています。交流会をする、ファンクラブのようなネットワークを作るとかね。イベントそのものよりも、きっかけに出会った私たちの関係性を大事にしていくことのほうが尊いということが、應典院のメッセージなんです。
だから、大きな場より小さな場をたくさん作っています。若者が、應典院に魅力を感じるとしたらそこですよ。小さいものは5人、10人という場のなかで、都市の夜の時間帯に作られていく関係性の深さや厚み。それが、應典院というメディアの小さな記事を作っています。大きな見出しの特集記事じゃないんですよ。小さなベタ記事がパッチワークのように貼りだしてあるところに、應典院的な面白さがあると思います。僕は『ぴあ』にいたからね(笑)。
ほんのささやかな関係でも、たったひとつの小さな糸口が、これからの生涯を決定してしまうようなこともある。関係性とは何かと出会う場です。そういう関係性を盛り込むために、寺や僕たちの生き方をどう開いていくのかが問題であって、集客するとかイベントすることが目的ではないのですよ。
——縁、ですよね。
-

應典院の窓からは墓地、そして上町台地が見える
そう、大きな意味での縁ですよね。その縁のなかで、自分が坊主であるということを、強烈に自覚していく13年間だったと思っています。問われ続けてきましたから。空間や関係から汲みあげてくるもののなかに、自分を預けていくというか。そのことのほうが、教義そのものの理解よりも尊いんじゃないかという場面が多かったです。 それは、従来の寺檀制度のなかからは、まったく考えられないことです。「お葬式はしない! ここはアーティストと若者だ!」と言い切ったことで、考えられないような組み合わせが始まったわけでね。應典院が始まって3?4年は、まだ何が起きているかわからなかった。10年くらい経ってやっとわかってくるんです。来ている人たちが変わっていく、育って行くプロセスを見つめ続けて「ああ、僕たちがやってきたのはこういうことだったのか」と、後から見えてきました。
表現者の祈りが僧侶の願いにクロスする
非常に逆説的なんですが、應典院はお葬式をやらないことによって、むしろ都市のなかにおけるいちばん聖なるもの、スピリチュアルなものを汲み取っていく装置になったのかもしれない。そこには葬儀はないが、祈りはある。法事はないが、願いはあるんです。そういうものが13年の間にたまりたまって、ひとつの應典院のエートスみたいなものを作っていると思います。だから、わかる人はその場所に立っただけで空気を感じる。内田樹さんも言ってましたよ、霊的スポットやなぁって(笑)。
僕が、いちばん應典院らしいと思う場面は、公演の仕込みが始まる朝に劇団の連中に5分間の法話をするときなんです。
——公演の準備が始まる前に法話を?
-

秋田さんが園長先生をつとめる「パドマ幼稚園」の庭
そう。機会があったらぜひ一度見に来てください。多いときは40人くらい、若者たちが床に胡坐をかいてワーッと座っているわけ。そこで彼らは、生まれて初めてお坊さんの話を聴く。劇団の連中は、みんなフリーターしながらお金かせいで、いよいよこの三日間が自分たちのステージでしょう。当然、祈りたい気持ちも高まりますよね。自分たちの表現に対する純粋な気持ちを発揮したい、伝えたい。そんな深い願いを持つ人たちには、自ずと僕の話に反応するのかもしれない。應典院での劇団公演は年間40本以上、それが13年続いているわけですから、同じ話をしないように「どの劇団にどの話をしたか」を記録してある(笑)。 寺は建物だけでいえば、所詮ハコです。目に見える装置だけでなく、参加した人の願いや思いがあって、それが風や土となって寺を寺ならしめる。人は自ずとそういうものに感化されていくんだと思います。 仏教は死者回向だけではない。表現することを通して、私たちは目に見えないものとつながれる。それを伝えるとか分かち合うとかしながら、深い願いを染み渡らせていくことが、宗教的な共同性の入り口となるのではないでしょうか。それって、仏教と若い人たちが関わり合っていくひとつの回路になっていくと思います。でも、これは日常的な関係があってこそ成立する場ですよ。突然お坊さんがやってきても「誰や?」っていうことになりますよね。
——たしかに、親しいお坊さんから聴く/伝わる仏教にはすごくリアリティがあります。
関係性のないところで、言語だけで言い切ろうとしても対岸は果てしないです。言葉だけなら学者にはかなわないね。たぶん、そこではないところに、現代の仏教者のポジションがあるはずなのに、布教すること以外考えられなくなっているところが問題だと思うんですね。
お坊さんは入口ですよね。そして、お坊さんが語る仏教がそれを聴く人にとっての死生観の基本用語になると思います。だから、そういうお坊さんがもっとたくさんいて欲しい。お坊さんは、肩書きではありません。やはり、その人の生きざまやメッセージやと思いますよ。
坊主めくりアンケート
1)好きな音楽(ミュージシャン)を教えてください。特定のアルバムなどがあれば、そのタイトルもお願いします。
エレニ・カラインドルー「エレニの旅」。大好きなアンゲロプロスのサウンドトラック。
2)好きな映画があれば教えてください。特に好きなシーンなどがあれば、かんたんな説明をお願いします。
キェシェロフスキの「ふたりのベロニカ」。人形が「変態する」シーン。
3)影響を受けたと思われる本、好きな本があれば教えてください。
最近でいえば、島薗進「スピリチュアリティの興隆」かな。
4)好きなスポーツはありますか? またスポーツされることはありますか?
意外にサッカーが好き。稲本最高!。いまは毎日のストレッチのみ。
5)好きな料理・食べ物はなんですか?
何でも。
6)趣味・特技があれば教えてください。
編集マニア。場や関係を編集するのが得意。
7)苦手だなぁと思われることはなんですか?
幼稚園の保護者との個別面談(園長先生、しているので)。
8)旅行してみたい場所、国があれば教えてください。
とりあえず北京、ベルリン、ニューヨーク。映画で何度も行ったけど。
9)子供のころの夢、なりたかった職業があれば教えてください。
映画監督。
10)尊敬している人がいれば教えてください。
友人の詩人、上田假奈代
11)学生時代のクラブ・サークル活動では何をされていましたか?
自主映画製作。
12)アルバイトされたことはありますか? あればその内容も教えてください。
出版社の編集庶務、映画会社の宣伝庶務。非常に重宝がられました。
13)(お坊さんなのに)どうしてもやめられないことがあればこっそり教えてください。
ないです。
14)休みの日はありますか? もしあれば、休みの日はどんな風に過ごされていますか?
オンとオフの境がないので。映画館で月3本以上がノルマ。
15)1ヶ月以上の長いお休みが取れたら何をしたいですか?
原稿を集中して書く。
16)座右の銘にしている言葉があれば教えてください。
愚者に還れ。
17)前世では何をしていたと思われますか? また生まれ変わったら何になりたいですか?
意外に学校の先生とか。生まれ変わるなら、地味な作家。
18)他のお坊さんに聞いてみたい質問があれば教えてください。(次のインタビューで聞いてみます)
「お坊さんのハゲ頭と剃頭は、やっぱり違うと思いますか。」
19)前のお坊さんからの質問です。「最近ワクワクしたことはなんですか?」
やっぱサッカーのカメルーン戦直前ではないでしょうか。
プロフィール
秋田光彦/あきた みつひこ
1955年大阪市生まれ。明治大学文学部演劇学科卒業。現在は大蓮寺住職・應典院代表、パドマ幼稚園園長。情報誌『ぴあ』にて自主映画の登竜門『ぴあフィルムフェスティバル』事務局を経て、石井聰亙監督と『ダイナマイトプロ』を創設、最若手プロデューサー兼脚本家として『狂い咲きサンダーロード』『爆裂都市』を送り出し、日本映画界にインディーズ旋風を巻き起こす。30代で加行、浄土宗教師として『教化情報センター21の会』の事務局長として、数々の宗教イベント・メディアのプロデュースを手がける。97年、大蓮寺塔頭・應典院を、NPOを若いアーティストの拠点として再建。共著に『生命と自己』『つながりのデザイン』など。
浄土宗 大蓮寺 塔頭 應典院
http://www.outenin.com/
1614年、大蓮寺三世誓誉在慶の隠棲所として創建。1997年に再建される際、一般的な仏事ではなく、かつてお寺が持っていた地域の教育文化の振興に関する活動に特化した寺院として計画。「気づき」「学び」「遊び」をコンセプトとした地域ネットワーク型寺院として生まれ変わった。音響・照明施設を備えた円形型ホール仕様の本堂をはじめ、セミナールームや展示空間を備えており、演劇活動や講演会など様々活動に用いられるほか、一般に開放された交流広場(玄関ロビー)には芝居や講演会のチラシが置かれ、文化情報の発信および人々の交流の場として機能している。また、『應典院寺町倶楽部』の拠点施設として、コモンズフェスタや寺子屋トークの舞台にもなっている。
[amazonjs asin=”4167838796″ locale=”JP” title=”仏教シネマ (文春文庫)”]