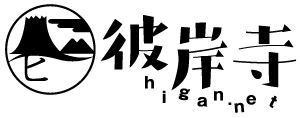皆さま、改めましてあけましておめでとうございます。本年も彼岸寺をどうぞよろしくお願いいたします。
さて、毎年恒例となっております干支にちなんだ「仏コラム」、今年で9回目、2026年は「午年」ということで、馬にまつわる仏教のエピソードを味わっていきたいと思います。
人類の歴史において、馬は農耕や輸送、あるいは戦争にも用いられ、人間にとって非常に重要なパートナーでした。世界のいろんな地域の神話にも、数々の馬が登場しますし、お正月といえば神社に初詣に行って「絵馬」を奉納した、という方もおられるかもしれません。今では馬と直接触れる機会というのはそれほどなくても、馬が私たちに身近な存在であるということは、いろいろな場面で感じることができるでしょう。
仏教が起こった古代インドでも、やはり馬は重要な存在でした。王族の象徴ともされ、シャカ族の王子であったシッダールタも「カンタカ」という名の愛馬がいたことが、仏典にも記されています。
また、馬を比喩として用いた教えもいくつか見られます。一つは「御者の喩え」という教えです。御者とは馬車を操るものですが、御者は修行者、馬は私たちの持つ感覚器官を表しています。私たちの感覚器官は、仏教においては「眼・耳・鼻・舌・身・意」の六根として理解されていますから、六頭だての馬車ということになるでしょうか。
私たちの感覚器官は、それぞれ覚知する対象があり、その対象となるものに馬のようにまっしぐらに、一瞬にして向き合おうとします。それによって、私たちは様々な認識や価値判断をすることができるのですが、しかしそれによって、好悪や欲望といったものが生じ、煩悩の発生源ともなってしまいます。そこで、御者が馬車の馬を制御して正しい道を進めるように、私たちもまた感覚器官の主として、しっかりとそれをコントロールし、感覚と煩悩に振り回されないように生きることの大切さを教えてくれる。それがこの「御者の喩え」ということになるでしょう。
一方で、私たちの教えに対する姿勢や理解する力を馬に例えた教えもあります。それが「四種の馬(四馬)の喩え」です。こちらは「馬には四種類の馬がいる。一つは鞭の影を見て驚き御者の意に随う馬。二つには鞭が毛に触れ、驚いて御者の意に随う馬。三つには、鞭が肉に触れて驚く馬。そして四つには、鞭が骨に達して驚く馬である」と説かれ、如何に「無常」であることを理解するか、という比喩になっています。
ところが興味深いことに、お経によって例え方が少し異なっているようで、『雑阿含経』では、最初の馬は他の村の人の死を聞いて無常を理解する者であり、二番目の馬は自分の村の人の死を知って無常を理解するものであり、三番目の馬は自分の親の死によって無常を知る者であり、四番目の馬は、自分の身に死が迫ってようやく無常を知る者として例えられています。一方、『大般涅槃経』では、最初の馬は「生」を説かれることで仏教の教えを理解する者であり、二番目の馬は「生老」を説かれることで理解する者、三番目の馬は「生老病」を聞いて教えを理解し、四番目のものは「生老病死」まで聞いてようやく理解できる者である、と例えられています。
どちらも、どれだけ早く自分自身が無常の存在であるかを理解できるか、あなたはどの馬ですか?ということが問われ、早く無常の身であることに目覚め、仏道を求めよということが説かれている教えでした。
他にも、地獄には馬をモチーフにした鬼「馬頭」も登場したり、逆に「馬頭観音」という、観音菩薩の化身の姿もあります。穏やかなイメージのある観音菩薩ですが、この馬頭観音は、忿怒の相を持つ姿であり、馬が雑草を食い尽くすように、煩悩を食べ尽くし、悪を砕く力を持って、畜生道に落ちた命を救う菩薩であると言われています。いずれにせよ、馬という動物からもまた、私たちはいろいろなことが学ぶことができそうです。
午年のこの一年、自分自身の自分勝手な煩悩に振り回されてしまうことに気をつけながら、「馬の耳に念仏」とならないように、しっかりと仏教の教えを聞いていけるような年として過ごしていきたいものですね。