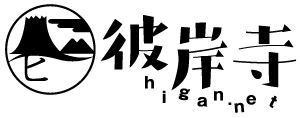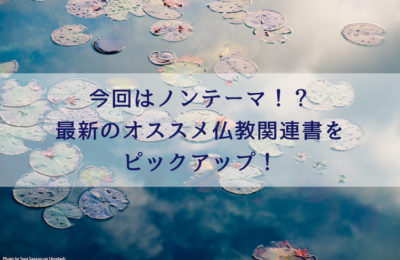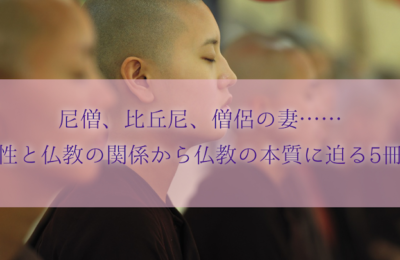今回は親鸞です。ある意味、日本を代表する僧侶と言えるでしょう。現代日本では僧侶の大半が戒律フリーで、これは約2500年におよぶ仏教の歴史でも、かなり例外的な状況です。親鸞は、そんな私たちの国のお坊さんの、シンボル的な存在だと思います。
とはいえ、国民的な存在になったのは、わりと最近といえば最近です。この100年かそこらでしょうか。大正時代に倉田百三の『出家とその弟子』という親鸞を取り上げた戯曲が出版されて、ベストセラーになりますが、親鸞が宗派を超えた人気を獲得していくのは、だいたいこの頃からです。
いずれにせよ、この100年ぐらいのあいだ、親鸞に関する本は、ほかのどの僧侶に関するものよりも、たくさん書かれてきました。日本人は、この一人のユニークな僧侶をめぐって、実にいろいろなことを語り、論じてきました。そうした、たくさんの言葉のうち、ごくごく一部を紹介しましょう。
① 『歴史のなかに見る親鸞』 平 雅行 著
現在の代表的な日本仏教史研究者による親鸞論です。学術的なハードさもありますが、一方で、著者が親鸞(と法然)の生き方や思想に大きな共感を抱きつつ、その魅力を語っているため、引き込まれるように読み進められる、優れた本になってます。
浄土真宗という教団が立ち上がっていく過程で、フィクションを多分に含む伝説的な存在となっていった親鸞。その「盛った」部分を削り取り、中世の一時代を生きた親鸞の実像を明らかにするのが、本書の最たる目的です。下級貴族の生まれという親鸞のリアルな立場を見据えつつ、親鸞が名高い高僧である慈円に弟子入りしたという説は「完全な作り話」といったような、批判的な検証がなされます。
親鸞の妻帯は仏教の歴史における画期だった、という主張も完全否定します。中世社会では、有力な寺院の僧侶が妻帯し、実子に寺を継がせる風習が公然とまかりとおっており、親鸞の結婚には、新しさは何もなかったわけです。とはいえ、そうして「出家者」ですらナチュラルに「女犯」する人間の業の深さへの反省力が、親鸞は別格でした。
京都の六角堂にこもり観音からのメッセージを受信した親鸞は、「女犯」を「宿報」ととらえ、これを個人の意志を超えた人間の普遍的な罪業の問題として受けとめます。さらに、人が罪業を抱えたまま救われる世界に気づいた親鸞は、同様の気づきを先に得ていた法然のもとに向かったのです。
罪業にまみれた人間を救う、浄土教の念仏の世界。親鸞は、その真実を説いた「悪人正機」の思想家だという誤解があります。著者は、それがいかなる誤解なのかを、丁寧に説明します。念仏は「悪人」のための仏教だというのは、実は当時の仏教界では一般的な発想です。しかし、それは知的な仏教がわかるエリートと違い、程度の低い連中=「悪人」は念仏や浄土教でしか救われない、といった、人をバカにした考え方としての「悪人正機」でした。
これに対し、親鸞(と法然)は、すべての人間は愚者で悪人だからこそ、他力の念仏でしか救われない、というラディカルな思想を突きつけました。こうした人類平等の救済論は、当時の身分社会では一種の革命思想であり、ゆえにこそ、彼らは強い批判を被り、弾圧されるに至りました。
人類の普遍的な罪業と、その救済の可能性を説いた親鸞の教えは、彼が生きた当時から、だったら何やっても別に悪くないんじゃないか問題(=造悪無碍)を生み出します。この問題は、たとえば「女犯」を罪業と思っていない人が僧侶のなかにもたくさんいる現代日本でも、いまだ深く考えるに値するテーマだと思います。
②『親鸞:主上臣下、法に背く』 末木 文美士 著
親鸞を、何があっても仏教の真実を守り通そうとした、「闘う念仏者」として描く論考です。まず注目すべきは、念仏弾圧による越後への流罪を受けて、「非僧非俗」を称するようになった親鸞の心中です。目前の権力から僧侶としての生き方を否定された現実を、彼はひとまず受け入れます。「非僧」です。しかしなお、自分こそが正しい仏法を伝える者だという自信は、決して揺るぎません。「非俗」です。親鸞は生涯にわたり剃髪して、袈裟を脱ぎませんでした。
実際、本書のサブタイトルに引かれる「主上臣下、法に背き義に違し、怒りを成し怨みを結ぶ」という憤激の文言を、親鸞は主著『教行信証』の後序に書き付けます。(法然や自分を弾圧した)天皇も役人も仏法の教えに背いており、マジでF○CKだぜっ!!といった感じでしょうか。親鸞の仏教への揺るがぬ信念と、それを害する「敵」に向けた強烈な対抗意識がうかがえます。
親鸞の和讃(仏菩薩や高僧を称える歌)には、彼のパンチの効いた仏教思想が、よく反映されています。師の法然は、現世を超えた神的な存在として描かれ、その延長に、世俗権力を超越した仏法の絶対性が主張されます。一方で、聖徳太子関係の和讃では、世俗権力と仏法が一体化した仏教国家の樹立が目指され、その実現のためには武器を取ることさえ肯定されています。今日的な視点から見ると、かなりヤバい仏教者に思えます。
著者は、親鸞の思想を伝える書として現在よく読まれている『歎異抄』には、親鸞のこうした仏教原理主義的な見解が含まれておらず、同書を読んだだけでは、親鸞思想の本質はつかめないと、注意を促します。他方で、『歎異抄』には著者の唯円が師の親鸞から主体的に受け取った教えが明確に示されており、この点は非常に大事だと述べます。都会の知的な仏教理解とはまったく異なる、日々の生業に追われる人々の視点から受容した親鸞の思想が、『歎異抄』には確かに込められているのだと。
知られるとおり、親鸞は晩年に息子の善鸞を義絶(勘当)します。その背景にもまた、浄土仏教の原理をゆがめて広める息子に対する激怒と、正しい仏法を伝えることへの根源的な願いがあったようです。正しい教えの伝達を邪魔するのであれば、家族も「敵」。「闘う念仏者」の徹底ぶりに、恐れ入ります。
③ 『親鸞と清沢満之:真宗教学における覚醒の構造』 伊東 恵深 著
前半で親鸞、後半で清沢満之を論じ、両者をとおして現代を生きる自己にとっての「覚醒」の内実を探る本です。清沢満之は、明治時代に親鸞思想のアップデートに挑戦し、同時代のみならず後世に多大な影響を与えた、近代の仏教者です。本書では、清沢やそのフォロワーの見解を吸収しながら親鸞を読み直し、ひるがえって、清沢が試みた親鸞思想の近代的アレンジの意義を問います。
親鸞の思想の核心を、著者は、「内在」と「超越」のあいだに見出します。いま・ここの苦悩する自己の現実から一歩も離れない救いとしての「内在」と、その現実を超える次元での救われとしての「超越」です。一般に、宗教は「超越」に傾きがちですが、「内在」への志向を決して失わないのが、親鸞思想のキモと言えるでしょう。
ここでキーワードになるのが、「横超」すなわち「よこさまにこえる」ことを目指す、親鸞の教えです。自力によって苦悩する我が身を乗り越え、垂直方向の解脱へと向かう通常の仏教に対し、親鸞は、どこまでも「凡夫」の地平を保ち続けます。ただし、単に「凡夫」のままであるのではなく、阿弥陀如来のパワーに後押しされながら、水平方向の救いの扉を開きます。如来の「超越」を受けとめながら、人間の「内在」の世界にとどまり続ける。それが親鸞的な救済の境地です。
近代の清沢満之は、この「内在」と「超越」の問題を、「有限」と「無限」というタームを用いて考察し直しました。人間は有限な存在なので、定義上、無限な宗教の世界を体現することはできない。だが、有限なはずの人間なのに、ときに無限の救いを生きられる。この不可思議な現象の構造を理詰めで考え続け、親鸞思想の哲学的な再解釈を進めたのが、清沢でした。なにか理屈っぽすぎる感じもしますが、とはいえ、そうした知的な営みがなければ、この100年ぐらいのあいだ、親鸞が知識人にも高く評価される状況はもたらされなかったでしょう。
かくして親鸞と清沢満之の教えや思想を丁寧に読み取った著者は、親鸞が開示した浄土真宗の「覚醒」の世界を、次のように結論します。言葉遣いがちょっと重たいですが、とても印象的かつ真に迫った文章かと思います。
親鸞が明らかにした浄土真宗の救済とは、日々、私たちを迷惑せしめる貪愛・瞋憎の雲霧(煩悩)の向こう側に、太陽の明るみ(真実信心の天)を信受して、有限の我が身を生きていくことである。無明の闇に再び埋没してしまうのではなく、かといって悟りすますのでもなく、常に発起する煩悩を逆縁としながら、阿弥陀の本願他力の救済を念々に感得していく歩みこそが、浄土真宗における覚醒の内実である。
④ 『肉食妻帯考:日本仏教の発生』 中村 生雄 著
この記事の冒頭に述べたとおり、現代日本の僧侶の多くは、戒律フリーの「肉食妻帯」僧です。東南アジアの仏教国から来日した方などには、ときにその事実にショックを受け、きっと何かの冗談だと考える人もいますが、むろんただの現実です。ともあれ、この「肉食妻帯」という現実にこそ、日本仏教の真相があるのではないか。そうした観点からの著者の論考を集めた、すごく面白い本です。
いまでは僧侶の「肉食妻帯」はあまりにも自明ですが、江戸時代は違いました。幕府から妻帯と世襲を公認されていたのは、浄土真宗(と修験)だけです。ほかの宗派の僧侶については、「女犯」がバレた場合には、島流しなどの厳しい処罰が課されました。ただし、取り締まりの厳密性はなかったようで、真宗以外の宗派でも、妻帯僧は一定数いたようです。とはいえ、少なくとも名目上は、真宗とそれ以外で扱いが違いました。
そのため、他宗派の僧侶から真宗僧侶に対し、お前等は「女犯肉食」のろくでもない連中だという批判がけっこうあったようです。このレッテルを払拭するために、真宗僧侶は「肉食妻帯」というフレーズを強調しつつ、そこに肯定的なニュアンスを込めようと奮闘しました。
たとえば、真宗の「肉食妻帯」は惰性でやっているのではなく、「慙愧の徳」(自分の恥をめっちゃ反省してますから!)をそなえており、その証拠に真宗僧侶は男色もせず「一人ノ妻」だけに満足してて凄いんだ、などと述べています。こうした発言をもし親鸞が聞いたら、絶望的な気分になるでしょうか、あるいは、これも罪業を抱えた人間の諸行だと、当然視するでしょうか。
いずれにせよ、明治時代になると、あらゆる僧侶の「肉食妻帯」が公的に「解禁」され、真宗だけが特別な存在ではなくなります。すると、真宗以外の宗派でも「肉食妻帯」する僧侶がナチュラルに増加していきます。その結果、日本仏教は「真宗化」したのだと、著者はすごく鋭い指摘をします。表向きは真宗ではなく別の○○宗と言っているが、寺院や僧侶の現実の姿は、実質「真宗」になっているではないか、と。
そして重要なのは、著者がこの変化を「内容なき真宗化」と評している点です。要は、「肉食妻帯」という形式だけが採用され、親鸞が突き詰めた教えや思想の「内容」は欠如している、というわけです。これは、真宗以外の宗派に限った話ではありません。真宗もまた、親鸞没後から現在まで、いや親鸞が生きた時代から既に、「内容なき真宗化」に陥ってはいないでしょうか。
⑤ 『最後の親鸞』 吉本 隆明 著
戦後日本の最大の思想家と目されている吉本隆明(1924~2012)の、代表作の一つでもある親鸞論です。本書解説で中沢新一氏が述べるとおり、親鸞は自らの思索を突き詰めた結果、「いつのまにか浄土思想そのものがいぜんとして抱えていた、「宗教」としての枠組みまで解体」しました。そうして浄土思想や宗教の彼方を見抜いたであろう、「最後の親鸞」の思想とは、いかなるものであったのか。
それは端的に言えば、<非知>です。宗教であれ学問であれ経験知であれ何であれ、人間が自らを高めるには、<知>が不可欠です。その<知>を増やし深める過程で、自信を得たり、他人にものを教えられるようになったりします。けれど、<知>の究極の目的は、自己確立や教育・教化にはありません。むしろ、「そのまま寂かに<非知>に向って着地する」のが、<知>の最終形態だと、吉本は述べます。
ところが、この<非知>の地点へと降り立つのが、人間には難しい。通常の人間は、<非知>へと向かう<知>の習得、という矛盾した実践に取り組むほかないからです。しかし、「最後の親鸞」は、あるがままに<非知>への着地をやってのけていた。吉本はそう理解します。
具体的には、たとえば「念仏をとなえれば、浄土へゆける」という因果論的な<知>から抜け出ることによってです。人は自己が救われるために、何らかのアクションを起こしたがる、というより、起こしてしまうものですが、その種の「はからい」を、親鸞は自然に否定します。であれば、果たして救いはいかにもたらせされるのか? この種の問いに対し、因果論的な回答を出さないというか、そもそも問わないというか、問おうとする「はからい」の彼方を生きるのが、親鸞の<非知>の境地でしょう。
かくして、浄土思想や宗教の世界が終わった後に、親鸞のもとには何が残ったのでしょう。吉本はこう推測します。
最後の親鸞を訪れた幻は、<知>を放棄し、称名念仏の結果にたいする計いと成仏への期待を放棄し、まったくの愚者となって老いたじぶんの姿だったかもしれない。
一見すると救いがないです。しかし、仏教の悟りとは、常識的な「救い」などとは別次元の問題です。そして、吉本が示した「最後の親鸞」のイメージは、ありがたくつまらない親鸞に関するお説法などとはまったく異なる、仏教の本質に、はっきりと触れた何かのように思えます。
以上、親鸞の多面性や、それを受けとめる側の多元性について論じてきました。上に紹介したもの以外にも、親鸞と右翼思想との結びつきを考察した本(中島岳志『親鸞と日本主義』新潮選書)があれば、マルクス主義に感化された左翼思想家による親鸞の受容を検討した本(Melissa Anne-Marie Curley, Pure Land, Real World: Modern Buddhism, Japanese Leftists, and the Utopian Imagination, University of Hawaii Press)もあり、親鸞の解釈は右から左まで、ほんとうにさまざまです。
多様な解釈を導くのは、それだけ親鸞の教えや思想が奥深いからです。浅薄な思想からは、一義的な理解しか出てきません。その奥深さにはまり込むのは、おそらくたいへんなことですが、しかし、一つの生き方としてはアリかもしれません、ね。