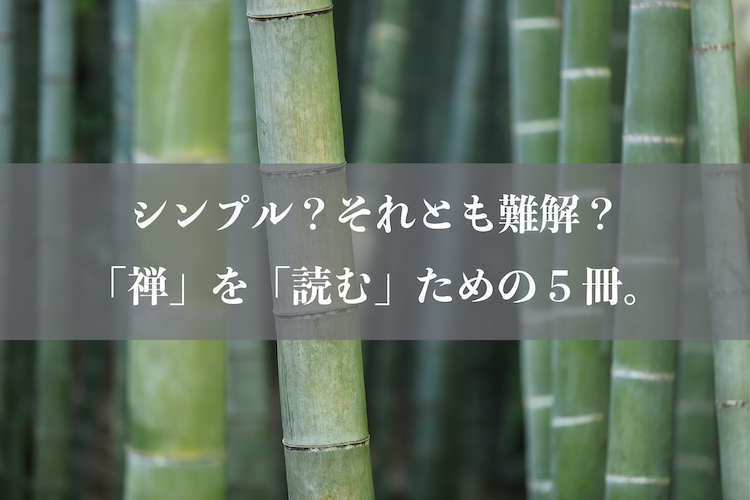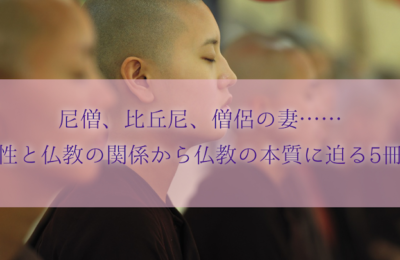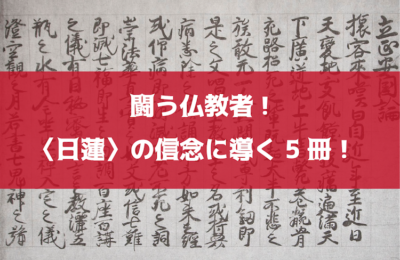zen 今回のテーマは「禅」です。坐禅、禅問答、禅寺の庭園、欧米で人気のZen。さまざまなかたちで表現される禅ですが、その本質は何なのでしょうか?
禅は、難しいと思います。伝えようとしている内容は、実はけっこうシンプルなのかと考えますが、その伝え方が、しばしばとても難解です。常識を超えたロジックやレトリックに満ちた表現が多いのです。
いっそのこと「不立文字」主義に従い、坐禅で一気に真理へGOという方向もありえるかと思います。とはいえ、ここは本の紹介コーナーです。あくまで、文字による伝達にこだわりたいと思います。
禅が正直よくわからない人(me too)でも、禅がわかる、あるいは、禅がわかったような気になるための本を、以下にいくつか見ていきましょう。
①『禅問答入門』 石井 清純 著
[amazonjs asin=”4047034630″ locale=”JP” title=”禅問答入門 (角川選書)”]
禅の真理を伝えるために開発された、禅問答。とはいえ、一般的には「わけのわからない問答」を皮肉る際に使われる言葉になっています。禅の難解さを象徴していると思います。
その禅問答について、おそらく最も明快に解説しているのが本書です。しかも、禅がなぜわかりにくいのかを、最もわかりやすく説明している本でもあります。見事な入門書です。
中国の唐代の禅僧、趙州にある僧侶が質問しました。「犬には仏性〈仏としての本質〉がありますか?」 趙州は答えます。「有る。」
別の僧が同じように、趙州に「犬には仏性がありますか」と質問しました。趙州は答えます。「無い。」
・・・!?
禅問答の難解さの一例です。AはBであり、非Bでもある。通常の論理を超えています。しかし、この種の表現にこそ、禅のエッセンスがつまっていると、著者は丁寧に論じていきます。
ある事実や考え方を、なるべくストレートな表現を用いて、相手が理解しやすいように教える。これが普通の教育です。しかし、禅の真理は、普通の教育方法では教えられない。なぜなら、その真理は個々の人間が自分の頭で悩み、全身で考えるなか発見する必要のあるものだからです。
ゆえに、禅マスターはあえて超論理的な回答や、婉曲的な表現をして、質問者自身がそれぞれの答えを見つけるように促すのです。ときには質問者の問いに対して沈黙をもって応じたり、質問者の鼻をつかんでひねったり、棒で叩きまくったりもします。体罰と紙一重というか、はた目には体罰そのものですが、そうした変則的なアプローチを採用してこそ、たどり着ける真理が確かにあるようです。
加えて、禅問答がわかりにくいのは、「その時・その場」でのみ伝わりうる表現を、現代の読者が「その時・その場」から離れて読まざるを得ない点にもあると、著者は述べます。かなり濃密な文脈を共有してはじめて意味をなすのが、禅問答であり、文脈を共有していないと意味不明なのは当然なわけです。
さらに、禅には「模範解答」や「スローガン化」を嫌う傾向が強いようです。型にはまった思考法では、いまの自分の問題を解決できないと考えるからです。ときには釈迦の教えすらも、それがマニュアルとして通用しそうになったら、あっさり捨て去ります。結果、どこに真の答えがあるのかが、ますます解りづらくなるわけです。
こうして、表面的なわかりやすさを意図的に避けている禅問答ですが、その目的ははっきりしてます。すなわち、「自分とは何か?」を明らかにすること。自分が一番わかっているようでいて、実は全然わかっていない、自分の本質。それをわかるための、わかりにくい方法が、おそらくは禅問答なのでしょう。
②『禅思想史講義』 小川 隆 著
[amazonjs asin=”4393138023″ locale=”JP” title=”禅思想史講義”]
おもに中国で発達した禅の思想史を、ずぶの素人のために「ざっくり」と講じてくれる本です。禅のはじまり、唐代の進展、宋代の確立と停滞、そして日本近代での独自アレンジ=鈴木大拙、という流れで講義が行われます。
著者によれば、禅思想は、大きく二つの方向性に分かれます。
①「ありのままの自己をそのまま「仏」として肯定する」
②「ありのままの自己を否定しのりこえたところに「仏」としての本来の自己を見出そうとする」
さらにざっくり翻訳すれば、①は「おまえは既に悟っている」、②は「悟っていないので修行せよ」という話になるのかと思います。最初期の禅は基本的に②の方向で、「迷える自己を、坐禅という行によって克服し、もともとあった仏としての自己を回復する」という趣旨でした。納得しやすい考え方です。
しかし、唐代には特に①の方面で多様な見解が示され、それにより禅思想がだんだんと深まっていきます。たとえば、こつこつがんばって悟る(=漸悟/ぜんご)のではなく、時間も段階も超えて、もともと悟っている自己を見よ!という発想(=頓悟/とんご)。あるいは、自分の一つ一つの感覚や動作はすべて仏のあらわれにほかならず、ゆえに修行は不要、ただ「平常」「無事」でいなさい、といった思想が生まれます。こうして、唐代は①の側が主流になったようです。
ところが、宋代になるとまた一転します。再び②の修行派が優勢になるようですが、ここで重要なのは、その修行方法が、同時代に禅の制度化が進んだのをうけ、著しく標準化したことです。先に、禅はマニュアル化に抗うと述べましたが、宋代には一定のマニュアル化が進行したようです。もろもろの生活規則が「清規」という名で成文化されたり、古典的な禅問答の記録が「公案」として整理されます。さらに、その公案の規格化の徹底の果てに、「看話禅」という修行システムが確立されたとのこと。
つまり、②の方面で禅思想/修行のマニュアル化が完成したわけで、これは禅の広い世界への普及に貢献した一方、その後の柔軟な発展を阻害するようにもなりました。これに対し、①でも②でもない新たな思想を切り開いた禅僧として位置づけられるのが、日本の道元です。
道元の論理は、なかなか奇妙です。いわく、「本来仏だから修行する」あるいは「修行しつづけているから本来仏なのだ」。①のはずが修行を不可欠とする、あるいは修行をしているからこそ①である、というわけで、①と②の、本来は両立しないはずの思想を、調停しています。というか、実践によって両者の矛盾を乗り越えています。①をまず前提としながら、それだと修行が不要になるので、実践上はあたかも②であるかのように振る舞うのです。この実践による論理的矛盾の解決を、道元は「本証妙修」といいました。悟りは修行のなかでのみ示されるのだ、と。
こうした論理的矛盾の解決のための思想を、日本近代で提示した人物として、著者は鈴木大拙を取り上げています。大拙が向き合ったのは、伝統と近代、あるいは日本と西洋の矛盾です。西洋文明を模範とし、それに必死で追随せざるを得ない日本。しかし、伝統的な価値の持続ときしみを内に抱え込んだ日本。その引き裂かれた自己の困難さを克服するために、大拙は禅に由来する「空虚の感」に基づく、はからいを超えた日本人の自己確立を唱えたのではないかと。なかなか興味深い指摘です。
禅思想が時代ごとにダイナミックに変遷していくプロセスを、大づかみに教えてくれる、優れた禅入門書の一つと思います。
③『禅:沈黙と饒舌の仏教史』 沖本 克己著
[amazonjs asin=”4062586681″ locale=”JP” title=”禅 沈黙と饒舌の仏教史 (講談社選書メチエ)”]
タイトルはそのものズバリですが、副題に「仏教史」とあるとおり、禅の解説に入る前に、ブッダから龍樹や唯識までの教義・教学の歴史がかなり詳しく述べられます。その上で、「沈黙と饒舌」のはざまで展開する禅の思想史を、道元、白隠、鈴木大拙らを中心に論じています。
仏教と禅の展開を解説する著者の語り口は、きわめて饒舌です。とりわけ、ある対象について批判的に語る際に、その饒舌さは顕著になります。たとえば、教理の定型化を避ける禅宗は、法系つまり人脈によって仏法を伝えるシステムを形成したがゆえに、やがて集団性や規範性が強まり、個々の創意を抑圧するようになってしまった点を、「人の世の皮肉」と批判的に語ります。言葉による真理の固定化を回避しようとした結果、今度は人間関係による真理の固定化が生じてしまったわけです。
こうした著者の批判精神が最も強く出ているのが、大拙について論じた部分でしょう。なにか私怨でもあるのかと思わせるほどに、大拙を徹底的にやり込めています。特に、伝統から自由に禅を語り、ひたすら超越的な真理の場を目指した大拙の思想が、戦時下には体制迎合的な性格を持ってしまった事実をつかまえ、その誤りを難詰します。
いちおう注釈をはさんでおくと、戦時下に体制迎合的だったのは、何も大拙に限らず、禅の関係者のほとんどすべてであり、もっといえば日本仏教界のほぼ全体なので、大拙だけを取り上げ戦争との関係を批判する著者の語りは、まったくフェアではないです。とはいえ、大拙の近代的な禅思想が、近代の戦争を肯定するのに応用しやすかったのは確かと思います。
著者の大拙論としては、むしろ、「禅」でもって日本文化を説明し尽くせるかのような大拙の論調への批判のほうが、より的確でしょう。大拙は、剣道や茶道や俳句など、いかにも日本っぽい文化を、すべて禅の精神から語る傾向がありました。確かに、現在の日本文化の重要な一部は、中世以降に禅僧が大陸に留学して持ち帰り、日本化したものです。が、「それは大陸文化であって禅文化ではない」と著者は正しく述べます。「日本は、決して禅だけの国ではない」のだと。
とはいえ、欧米などではいまだに「日本=禅」というイメージがわりと強固に存在していると思います。なぜでしょうか? この問いに一つの回答を与えてくれるのが、次に紹介する本です。
④『禅という名の日本丸』 山田 奨治 著
[amazonjs asin=”4335551010″ locale=”JP” title=”禅という名の日本丸”]
欧米とりわけアメリカでは、「禅(Zen)」がきわめて多義的な意味を持たされています。仏教の一派、あるいは日本的な何か、といった意味合いはもちろん、「入門的」「本質的」とか、さらには「格好良い」といったニュアンスで使われる用例も少なくないようです。
著者は、それらの例として、多種多様な本のタイトルをあげています。たとえば『禅とインターネット』、『ゴルフにおける禅』、『禅とストリート・ファイティング』(!)、『禅と旅行』、『禅とおむつ交換』(?)、『小説作法における禅』、『禅とカジノゲーム』(!!)、などなど、ものすごくいろいろと出版されているようです。
こうした「禅」の多様な用法を導いた決定的な本の一つが、ドイツの哲学者オイゲン・ヘリゲルの『弓と禅』であったことは間違いありません。1948年に出版され、各国語に翻訳されて世界的ベストセラーとなった同書は、日本の弓術を神秘的に描き、また弓術だけでなく日本の文化はすべて禅だと述べた著作です。1953年に刊行された英語版には、鈴木大拙が序文を添え、同書のベストセラー化を後押ししました。
本書は、その『弓と禅』が誕生するまでの過程を、ヘリゲルの人生史にそって跡付け、また、同書が広い読者を獲得した背景を読み解いています。ヘリゲルが弓道をならったのは、かなり短期間であり、彼の禅理解は、神秘主義思想への憧れや、日本語能力の不足による誤解から生じたことなど、詳しい検証がなされています。しかし、その歪んだ禅理解は、欧米で好意的に受け入れられ、ひるがえって、欧米からの評価を重んじる戦後の日本人にも認められていきました。
こうした禅の創造的誤解のダイナミズムを、本書はまた別の事例を通しても検討しています。京都の龍安寺の石庭の例です。現在、観光客に絶大な人気を誇るお庭ですが、戦前まではたいして注目されてませんでした。拝観料もなく、いつ行っても閑散としていたみたいです。ところが、1950年代になり、この庭が禅の悟りの世界を表現した素晴らしいものとして、海外に宣伝され、外国人が押し寄せるようになります。ちょうど、『弓と禅』がベストセラーになったのと同時期です。
そして、この日本庭園=禅思想という公式が海外で広がったのにも、どうやら大拙の影響があったらしい。大拙おそるべし、ですね。しかも、大拙の禅思想は、専門家がよく指摘するとおり、伝統的な禅ではなく、西洋哲学に呼応するかたちで形成された、一種の「西洋思想」だったわけで。つまり、西洋化された日本の禅を西洋人が高く評価し、その評価を西洋に憧れる日本人が受容した結果、今日の龍安寺は大盛況、ということになります。
近現代の禅をとりまく、グローバルな文脈の面白さを痛感させてくれる話ではないでしょうか。
⑤『禅の教室:坐禅でつかむ仏教の真髄』 藤田一照・伊藤比呂美 著
[amazonjs asin=”412102365X” locale=”JP” title=”禅の教室 坐禅でつかむ仏教の真髄 (中公新書)”]
最後に、やはり坐禅の本は取り上げておきましょう。実践しなければ意味がない坐禅ですが、書物からでも、その本質はある程度は学ぶことができます。なかでも、手に取りやすく、またとても現代的な観点から坐禅の本質を解説してくれるのが、本書です。
曹洞宗の禅(マ)スターである藤田一照氏と、般若心経などの現代語訳を行っている詩人・伊藤比呂美氏の対談本ですが、藤田氏による坐禅の解説が基調です。まず、坐禅はメンタルなエクササイズの一種ではなく、「人間が人間を超えて仏をやっている」実践だと、はっきり主張しているのが、たのもしいです。 健康や精神統一が目的ではなく(付随はしますが)、人間をやめて仏になるために坐禅はある、と。
藤田氏いわく、坐禅はクリエイティブな営みです。決まった作法を繰り返す、ルーティンワークではないのだと。しかも、それは何かを意識的に操作して別の何かをつくり出すクリエーションではなく、自己や自然がその内に隠しもった何かが、自ずから生み出す何かをつかみとるタイプの創造行為であるとのこと。この辺、実に道元っぽい感じです。
そんな坐禅の特徴は、瞑想との比較を通しても語られます。近年ブームになっている、マインドフルネスなどの瞑想は、「身で坐る+心で何かをする」という足し算であるのに対し、道元が定式化した坐禅は、「身で坐る=心で坐る=身心脱落」となっており、新しいものを何も付け加えていない。「坐ったらそれで終了」、にもかかわらず、そこに「仏」がクリエイトされている。あらゆる言葉を削除して、最も切り詰められた「仏教」の創造力が、そこには見えます。
なお、坐禅の正しい坐り方のような実用的な説明も、本書では具体的になされています。実際に坐禅にチャレンジするには、きちんとした禅寺やセンターで指導してもらったほうがいいと思いますが、基本的なやり方や各種のコツは、本書でも知ることができます。
⑤の本の最後に藤田氏は、仏教は「学ぶ」ものではなく、「する(do)」ものだと主張しています。「仏教は身心をフルに使って実地にするものなんですよ」と。むしろ「学ぶ」のが大好きな人間としては、自己の仏教に対する向き合い方の欠陥を思い知らされてしまいます。
とはいえ、「する」を深めるためには、「学ぶ」のも大事かと考えます。そうした文武両道路線は、たぶん藤田氏も含め、仏教についてバランスのよい考え方を持っている人は、みな共有しているはずです。そして今回紹介した本はいずれも、禅という仏教を「学ぶ」のにとても適しているかと思います。